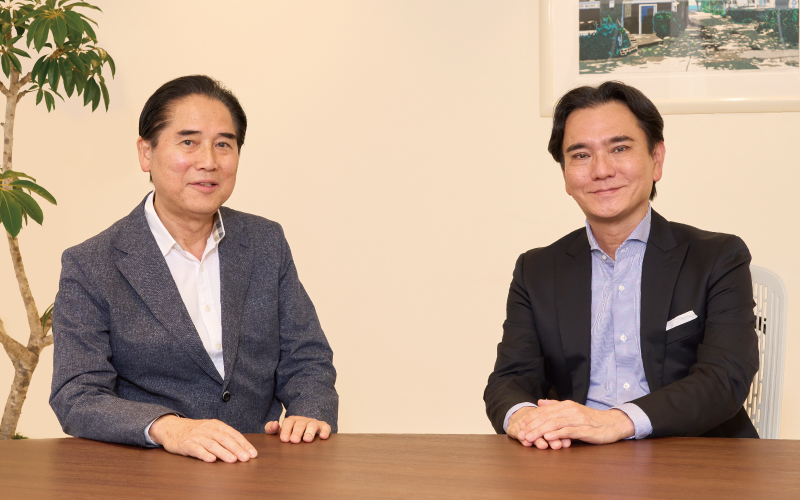委託研究を請け負う技術研究所として創業
若松 タナベコンサルティンググループ(以降、TCG)の経営コンサルティングや研究会、「トップ会」などで長いご縁をいただいていることに感謝します。独自のコア技術を軸に、デシカント除湿機※1やVOC(揮発性有機化合物)濃縮装置※2などの製造販売から空調システムの企画、開発、販売、メンテナンスまでを一貫して手掛ける西部技研は、国内のみならず、スウェーデンやポーランド、米国、中国、韓国にも拠点を構え、海外売り上げ比率が66%超のグローバル企業でもあります。また、2025年7月には設立60周年という節目を迎えられます。おめでとうございます。西部技研の創業の経緯についてお聞かせください。
隈 こちらこそ、いつもありがとうございます。当社の始まりは、創業者で父の隈利實が1961年に立ち上げた隈研究室にさかのぼります。父はもともと九州大学工学部で研究者をしていましたが、より実践的な技術を志向する性格で、企業から委託研究を受けて研究開発に取り組んでいました。隈研究所は、そのための個人の研究室でした。父は委託研究のいくつかが成功すると、大学の学術的な研究よりも実業に魅力を感じ始め、1965年に研究所を法人化して西部技術研究所を設立。おかげさまで、2025年で60周年を迎えることができました。
若松 請負開発型のベンチャー企業、隈利實という研究者アントレプレナーによる創業期ですね。事業は順調に成長していったのでしょうか。
隈 いいえ。研究開発で成功するのは10のうち3つほど。委託研究は成功しないと報酬を得られないため、すぐにお金が回らなくなりました。事業として成り立たせるには、自ら製品を開発して販売するメーカーにならなければならないと考えた父は、1972年に社名を西部技研に変更。当時の委託先とライセンス契約を結び、ヒーター製品のOEMメーカーとして再スタートを切りました。
若松 私自身の臨床研究では、事業の多くは、創業者の固有技術を武器に請け負いや下請け型の開発機能から始まります。次にスポット受注型製品の開発モデルか、OEM開発モデルへと転換します。西部技研の成長過程をお聞きしていると、OEM開発モデルへの転換です。当時のOEMヒーター製品の事業は拡大しましたか。
隈 最初こそ売れましたが、1973年にオイルショックが起こると材料の入手が困難になった上、電力不足の影響でヒーター製品の売り上げが落ち込みました。省エネへの対応が社会的なテーマとなる中、大学時代の先輩の紹介でハニカム構造※3の全熱交換器※4を目にした父は、約2年の歳月を掛け、1975年に「全熱交換ローター」を商品化。1976年には独自のハニカム加工技術を確立し、委託加工事業をスタートさせました。
若松 開発型製品は成長のきっかけをつくるビジネスモデルですが、売上高がスポット(受注)型事業に陥りやすいです。現在の西部技研のコア技術となっているハニカム加工技術の確立で、ベース(見込み)型の委託加工事業に転換したわけです。1975年と言えば、会社設立から10年目の節目に当たりますね。成長過程において1つ目の転機を迎えられました。
隈 商品化にこぎつけたものの、実績も信用もない中小企業の製品を買ってくれるメーカーは国内にほとんどありませんでした。そうした中、JETRO(日本貿易振興機構)の機関紙に出稿した広告が、ある韓国メーカーの目にとまって取引を開始。そこから国内の空調メーカーにも採用されるようになり、事業が軌道に乗っていきました。
委託研究型メーカーからOEM開発メーカーへ脱皮し30億円を超える
若松 部品メーカーとして事業を開始したと同時に、国内より海外企業の方が技術を見る目があったわけです。日本の超大手企業は、前例主義が常ですからね。優れた技術は簡単に国境を超えます。戦後に立ち上がった日本の優良企業は海外で評価され、成長したところも多くあります。ソニーや本田技研工業がまさにその例です。
隈 最初に取引した韓国メーカーの経営者が日本語に堪能だったおかげで、商社を通さずに取引できました。今でも、海外のほとんどの取引先と商社を通さず直接取引しています。
若松 商社を通さずに海外企業と直接取引を選択された点に、ハニカム構造の技術力の高さと、自社で値決めができる独創的なニッチトップモデルへの道を予感させます。ハニカム構造の除湿機で他社にはない特徴や強みはどこにありますか。
隈 素材の違いです。当社が1984年にデシカント除湿ローターを商品化する以前は、湿度をコントロールするために液体の吸収剤が使われていましたが、湿度が上昇すると分離したり、飛散したりするなど課題がありました。そこで、同業各社は固体の吸着剤を使ったローターの開発に着手。その中で当社が世界で初めて開発に成功したことが、海外市場拡大の足掛かりとなりました。
若松 世界初の開発は、グローバルニッチトップの始まりですね。10年に1回の節目でイノベーティブな技術が生まれ、事業がグローバルに拡大しています。1985年にはスウェーデンのDST社と、1988年にドイツのクラフタンラーゲン社と業務提携を結ばれています。隈社長が入社されたのは何年ですか。
隈 1987年です。その当時の売上高は約6億円とニッチな部品をつくる中小企業で、従業員数はパートタイマーも含めて50~60名程度でした。私は大卒で入社し、2年ほど工場に配属されました。その後、1989年に米国市場の開拓を任されて渡米。3年後に帰国し、1994年から3年間は東京で国内営業を担当しました。当時の売上高は約20億円、海外比率は30~40%程度でした。そうした中、父が体調を崩し、1997年に他界。急遽、母の隈智恵子が社長に就任しました。
ブランド開発モデルへ転換。値決め力で100億円を突破し中堅企業の道を開く
若松 中規模企業であった西部技研に隈社長が入社され、米国市場開拓という経験を生かしつつ、事業承継によって先代の研究者的な経営スタイルから中堅企業経営スタイルへとギアを上げることになり、会社として新しい成長ステージに入ったと感じます。
隈 おっしゃる通りです。母が社長に就任し、2002年に私が社長を承継したことで、経営方針は大きく変わりました。父は、あくまで機器の心臓部をつくる部品メーカーに徹することにこだわっていました。周囲から完成品の開発を勧められたものの、取引先と競合するため父は反対していましたが、母と一緒にその方針を転換。決断した一番の理由は社員でした。当時、私と同世代の社員が増えており、その層が「挑戦したい」と声を上げました。完成品になると付加価値もおよそ10倍になりますし、社員のチャレンジ精神に応えたいと思い、腹をくくりました。
若松 中堅企業の条件は、売上高30億円を超えたあたりから「ブランド開発型モデル」へ転換していくことです。「挑戦したい」といってくれた技術者の皆さんも会社にとって大切な財産ですね。完成品ブランド開発と販売は強烈なビジネスモデルの転換であり、値決め力の強化であり、中堅企業になるために避けては通れない道です。今の西部技研は隈社長の正しい決断力と実行力にあったのですね。
隈 完成品を開発したことで事業が広がりました。一方、グローバル化はスウェーデンの取引先のM&Aを皮切りに、2002年に米国、2008年は中国に現地法人を設立するなど、現地に販売会社やサービス拠点を設立して拡販する方針を明確化しました。
若松 部品メーカーから完成品に事業を広げ、海外拠点の設立によって規模が拡大した時期です。次の成長の節目である売上高が100億円を超えたのはいつごろですか。
隈 2015年に設立50周年を迎えたころです。2003年から2007年ごろまでは西部技研単体で売上高が約40億円に達しており、50億円を軽く超えるだろうと思っていました。しかし、その矢先にリーマン・ショックに見舞われ、売り上げが激減。事業拡大に向けて中国をはじめ積極的に投資していた時期と重なり赤字に転落しましたが、1年で業績が戻りました。
若松 本当に経営は山あり谷ありですね。TCGの成長メソッドに「1・3・5の壁」という理論があります。「会社は30億円、50億円、100億円、300億円、500億円、1000億円…と、1・3・5が頭につく年商規模で成長の節目を迎え、そのたびに条件整備をしなければ持続的成長はない」という成長理論です。その点からすると、当時の西部技研は年商50億円の壁という試練が訪れました。
隈 結局、50億円を達成したのは2015年ごろです。その成長を支えたのは積極投資をしていた中国の工場でした。もう1つは、事業領域の拡大です。部品や完成品の販売に加え、施工まで一貫して手掛けるソリューション事業を2009年にスタート。最初こそ伸び悩みましたが、2014年から事業が拡大。それが100億円の壁を超える原動力になりました。2024年12月期の売上高は、西部技研単体で183億7400万円、連結では320億6900万円を実現しています。
若松 企業の成長モデルは、下請受託モデルからOEM部品モデルへ、そこから完成品ブランドモデルへと成長していきますが「言うは易く行うは難し」のビジネスモデル転換です。現在では、ブランド部品や完成品の販売に加え、施工まで一貫して手掛けるソリューション型事業を2009年にスタートされています。専門領域を極めていく中堅企業の正しい姿であり、1・3・5の成長の壁を全て突破して中堅企業へと成長されました。業界の常識を恐れずに新たな価値に挑むスピリッツはどこからくるのでしょうか。
隈 若い世代が「挑戦したい!」と言ってくれたからです。その声に応えて事業を広げてきました。当社はデシカント除湿機という特殊な装置を販売しており、施工現場にも頻繁に足を運んでいます。その際、顧客である設備担当者から「施工まで手掛けてみたら?」と言っていただくと、社員は挑戦したくなるのです。もちろん新規参入した当初は軋轢があったものの、なんとか乗り超えることができました。
グローバルな価値創造モデルへ、東証スタンダード市場上場を決断。300億円を実現
若松 顧客からの声に耳を傾ける現場主義が大切ですね。コア技術を軸に新たな市場を創造されました。業界のパイオニアと呼ばれる中堅企業モデルです。
隈 ニッチでコアな部品が当社の原点であり、強みとなっています。そこから完成品へ、そしてサービスや施工、建設といったソリューションまで広がりましたが、今でも原点となる部品事業を継続しながら一気通貫のビジネスモデルを築いています。そこがコアバリューだと考えています。
若松 顧客へ専門価値を届けるバリューチェーンを構築されました。経営コンサルタントとしても中堅企業を数多く支援してきましたが、経営者が自社の在るべき姿、ビジョンを描き切れないと、中堅企業への脱皮は実現しません。隈社長はその証明として、2023年に東証スタンダード市場への上場(IPO)を果たされました。いつごろ決断されたのでしょうか。
隈 株式上場の決断をしたのは2018年でした。50周年を迎えたころ、一気通貫のビジネスモデルは今後も拡大するだろうと手応えを感じました。もっと大きな投資を見据えて資金調達の選択肢を多様化し、一流の信用を得ることが1つ目の目的です。2つ目は、人材採用です。事業拡大に伴いマネジメント人材の増員が不可欠ですが、当社は福岡で創業した会社であり、事業領域が非常にニッチですから全国区の知名度はありません。上場されたオーナー経営者の方々に話を伺うと、そろってメリットに挙げるのが人材採用です。全国から良い人材を集める手段として上場を選びました。
3つ目が、事業承継です。今後も親族のみで承継していく選択肢はリスクが高いと言えます。事業規模が大きくなった今、社員をはじめ会社に関わっている人材が変化と成長を実感できる組織にしたいと思いました。
若松 株式上場には明確な目的と勢い、運が必要です。私自身もTCGの社長として、社員とともに2016年に東証1部(現プライム市場)に上場を実現したこともあり、隈社長の決断を理解できます。上場したいと思って準備をしても、それを果たせる社長はひと握りです。上場会社は約3000社ですからね。決断後、上場の準備はどのように進められたのでしょうか。
隈 IPOプロジェクトチームを立ち上げ、外部から人材を入れて準備を進めました。コロナ禍もあって当初の想定よりも準備に1年多く掛かりました。
IPOを機に経営者人材を強化。挑戦を恐れない企業文化を取り戻す
若松 株式上場の前後で、隈社長ご自身にも会社にも変化はありましたか。
隈 上場する前は、オーナー企業の色合いが強かったと思います。今は、投資家や株主から意見をいただく環境になり、事業計画や中期経営計画の信頼性に対する意識が格段に高まりました。また、配当の原資を確保するためにも会社を成長させないといけません。そのような成長志向の高まりが会社を経営する上で非常に大切なのだと思います。会社を公器(パブリックカンパニー)として見ることができるか、それが本質です。
一方、ステークホルダー、特に社員の意識を変えていく必要があると考えています。上場前後に入社した社員は成長や変化への意識を強く持っている半面、組織には成長より安定を求める社員もいます。どちらが良い、悪いではなく、マインドの格差が広がるというジレンマです。これまでも成長を遂げる過程や中途社員の採用時に社員間のマインドの違いを感じることはありましたが、上場後はさらに鮮明になっていきます。
若松 今は、隈社長ご自身が会社の成長意欲を持ち続けることも大切です。上場会社として、社員一人一人が「自分たちの会社は自分たちがつくる」という組織エンゲージメントを醸成するためには、私自身の経験を振り返っても10年は必要です。
10年は長いようで短いものです。隈社長はそのような中で、経営者人材育成にも取り組まれていますが、人的資本に投資することで風土変革の期間も短縮されるはずです。
隈 今はTCGにも協力いただきながら企業文化を改革しています。具体的には、ビジョンとコアバリューの策定に取り組むと同時に、人材マネジメントを重要な経営課題と位置付け、「人材育成会議」を設置。HR(人的資源)領域の経営課題を協議する仕組みを導入することで、上場企業としてのガバナンス強化と組織戦略の実効性を高めているところです。
若松 企業成長とともに社員やグループ企業も増えてくると、どうしても組織が官僚化していきます。しかし、そうした葛藤を乗り超えることで、結果的に会社は強くなると確信しています。互いを尊重し、融合していく人材育成や人事制度は、持続的に成長する組織へ転換する上で不可欠ですね。
環境に優しい空気のソリューション企業を創造し、500億円ビジョンへ
若松 IPOによってグローバルなパブリックカンパニーへの歩みを進められています。2030年に向けた今後のビジョンについてお聞かせください。
隈 持続的に成長し、より社会に貢献できるよう、組織の形を変えることも必要です。パブリックカンパニーにふさわしい企業文化も醸成されていくと考えています。一方、事業については、心臓部のハニカムの技術から始まり、部品、モジュール、完成品、ソリューション、施工、企画へと領域を広げてきました。このようなバリューチェーンを組む会社は他にありませんし、各機能を一気通貫することで事業をもっと広げていけると考えています。
例えば、工場内のプロセスまで踏み込んで担当するなどもそうです。当社が工場内の各工程に最適な空調をまとめて設計し、機器メーカーとタイアップしながら導入するイメージです。
若松 工場内の空調(空気)をプロデュースできる、社会貢献価値の高いビジネスモデルです。西部技研のパーパス「環境に優しい空気のソリューションを届ける。」の実現ですね。
隈 もう1つの方向性は、ハニカムの用途を広げること。通常は湿度や熱、排ガス中に含まれる有機溶剤を吸着させて除去する用途で使用されていますが、その技術を必要な要素を供給するために使用する。その手始めとして、ビニールハウス向けのCO2(二酸化炭素)供給装置を発表しました。
簡単に説明すると、大気中で集めたCO2を適切な濃度にしてビニールハウスに供給する装置です。農作物によっては、CO2濃度を高めることで収穫量が増えるそうです。これまでは、ボンベでCO2を供給したり、ビニールハウス内で石油ストーブを点けたりしてCO2濃度を上げていましたが、当社の装置を使えばクリーンに最適な環境をつくり出せる。独自技術を応用することでハニカムの用途を広げられると考えています。
若松 強みである空気ソリューションのバリューチェーン戦略でその専門的用途と技術を掘り下げながらグローバル戦略を推進し、社会課題を解決し続ければ、中期経営計画で掲げている「2030年に連結売上高550億円」も達成できると期待しています。
隈 TCGにも支援をいただいていますが、目下の課題は後継者人材の育成です。組織が大きくなると、組織を守ることに注力する力が働きますが、それは組織を安定させる一方で将来に向けて伸びようとする力を削り取ってしまうのではないかと危惧しています。組織に揺らぎを与えていくことが大事だと考えています。
若松 その通りです。今回の対談を通して、創業の委託研究事業から部品開発メーカー、OEM開発メーカーへ、ブランド開発メーカーを経て、技術ソリューション型メーカーへと変身され、その過程でIPOを実現。TCGが提言する1・3・5の成長理論を、自らの変化と成長で突破されたグローバルニッチトップ中堅企業の軌跡として再確認できました。
経営者人材を育てるには、若い世代がチャレンジできる環境をつくるなど、意図的に組織を揺らし、社員の体験価値を高めていく必要があります。良い意味で組織を引っかき回しながらも、創業の精神でもある果敢に挑戦する組織と人材を創造し続けてください。それが、隈社長のこれからの大事な仕事になってきます。隈社長ご自身がそうであったように、事業承継は最大の事業戦略ですからね。本日はありがとうございました。

福岡県古賀市にある西部技研の本社エントランス。
同社の主力製品であるハニカム構造を用いたVOC濃縮ローターが展示されている
※1 乾燥剤(デシカント)を利用して空気中の湿気を除去する除湿機
※2 VOC(揮発性有機化合物)を含む排気ガスを濃縮し、効率的に処理するための装置
※3 小さな穴を隙間なく並べた蜂の巣のような構造体
※4 室内温度の変化を最小に抑えながら効率的に換気を行う省エネルギーシステム

西部技研 代表取締役社長執行役員 隈 扶三郎 (くま ふみお)氏
1964年福岡県生まれ。1987年福岡大学法学部卒業後、西部技研入社。1990年米国のニチメンに業務研修のため出向。1993年西部技研営業部、1994年東京営業所で勤務後、1997年専務取締役営業本部長に就任。2002年より現職。
(株)西部技研
- 所在地 : 福岡県古賀市青柳3108-3
- 創業 : 1962年
- 代表者 : 代表取締役社長執行役員 隈 扶三郎
- 売上高 : 320億6900万円(連結、2024年12月期)
- 従業員数 : 779名(連結、2024年12月現在)
若松 孝彦 わかまつ たかひこ
タナベコンサルティンググループ タナベコンサルティング 代表取締役社長
タナベコンサルティンググループのトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種・地域を問わず大企業から中堅企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーから多くの支持を得ている。
1989年にタナベ経営(現タナベコンサルティンググループ)に入社。2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て2014年より現職。2016年9月に東証1部(現プライム)上場を実現。関西学院大学大学院(経営学修士)修了。『チームコンサルティング理論』『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。
タナベコンサルティンググループ(TCG)
大企業から中堅企業のビジョン・戦略策定から現場における経営システム・DX実装までを一気通貫で支援する経営コンサルティング・バリューチェーンを提供。全国800名のプロフェッショナル人材を有し、1957年の創業以来17,000社の支援実績を持つ日本の経営コンサルティングのパイオニアであり、東証プライム市場に上場しているファームである。