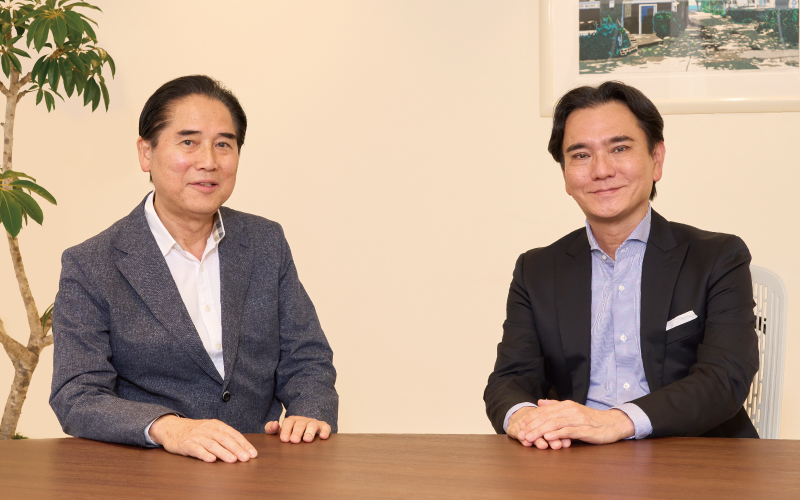アダストリア、5回目のチェンジで人々の生活を豊かにする Play fashion!プラットフォーマーを目指す アダストリア 代表取締役社長 木村 治

独立、子会社社長を経てアダストリア社長に就任
若松 30を超えるファッションブランドを擁するアダストリアは、国内外で約1630店舗を展開するほか、近年はECモール「and ST(アンドエスティ)」を中心とするウェブ事業が約728億円に拡大。グループ売上高は2931億1000万円(2025年2月期)に上るなどの成長をしています。
木村社長は2022年からアダストリアの代表取締役社長を務め、2024年からは次の成長のエンジンとなるプラットフォーム事業をけん引するアンドエスティの代表取締役社長 CEOも兼任されるなど、社会情勢が大きく変化する中で経営者リーダーシップを発揮されてきました。ただ、経歴を拝見すると、一度は退社されて独立した後に再びアダストリアに復職されているのですね。
木村 私が最初に入社した1990年は、まだ福田屋洋服店という社名でした。当時は10店舗ほどしかなく、そこで店長やエリアマネージャー、本部でバイヤーや営業部長などを経験させてもらいました。
その後、2001年に独立してワークデザインを設立しましたが、アダストリアの代表取締役会長である福田三千男に呼び戻される形で2007年に復職。ワークデザインはドロップ(現トリニティアーツ)と経営統合され、2011年にトリニティーアーツの社長に就任した後、2016年にアダストリアの常務になり、2018年の代表取締役副社長を経て2021年に取締役社長、2022年に現職に就きました。
若松 起業され、子会社の社長を経験した上で社長に就任されたわけです。自身も経営コンサルタントとして創業者と多くの仕事をしてきましたが、創業の経験は、業績はもちろん仕入れや資金繰り、人材の面など貴重な経験になります。経営はバランスとタイミングと集中であるなど、さまざまなことを体得されたと思います。
木村 自分のお金で起業した経験は大きな糧となりました。経営については福田から多くを学びました。実は最初に入社した際の面接官も福田でした。当時は従業員数も少なかったので接点が多くありましたし、復職後、特に副社長時代からは二人三脚で経営に当たっています。

「niko and …」「GLOBAL WORK」「LOWRYS FARM」など30を超えるファッションブランドを展開するアダストリア。
国内外で約1630店舗を展開するほか、「and ST(アンドエスティ)」を中心とするECモール&メディア事業にも注力している
4回の変化を繰り返し紳士服小売からSPAへ成長
若松 アダストリアはミッションに「Play fashion!」を掲げ、ファッションは「毎日をワクワクさせること」「誰かと新しいものを創ること」「それぞれの人生を楽しむこと」と発信されています。そこから続くビジョンやバリューも、「もっと楽しい」や「ワクワク」といったポジティブで身近な言葉が多く使われており、社員の皆さんも大いに共感されているでしょうね。
木村 「Play fashion!」は、社内でかなり浸透していると感じています。福田が一貫して追求しているのは、「ワクワクするようなファッションとは何か?」。日ごろから、「ワクワクする会社にしたい」と発信しています。その思いを込める形で、今の役員クラスの人材が集まって「Play fashion!」というミッションを策定しました。当社にとって、ファッションとは洋服だけではありません。食や住環境、カルチャー、アートなど、自分らしい人生を楽しむためのモノやコト。それら全てをファッションと捉えています。
若松 それを具現化するように、アパレルにとどまらずインテリアや食にも事業領域が広がっています。「中期経営計画2030」では、変わらないものとして「Play fashion!」を挙げる一方、変わるものとして「SPAからPlatformer(プラットフォーマー)への進化」を宣言されています。特に、「買い物はモノを得る手段ではなくコト、トキを楽しむエンターテインメントに広がる」というメッセージに非常に共感しました。
今回を中期経営計画の「5回目のチェンジ」と位置付けていらっしゃいますが、その話を伺う前に、これまでの4回のチェンジについてお聞かせください。
木村 1953年、紳士服小売店である福田屋洋服店を茨城県水戸市で開業したことがアダストリアの始まりです。1回目のチェンジは、20年後の1973年。メンズカジュアルショップ「ベガ」を開店し、紳士服店から水戸市では空白マーケットだったメンズカジュアル市場に進出しました。
2回目のチェンジは1982年。ジーンズカジュアルショップ「ポイント」を開業し、1984年からチェーン化を進めました。私の原点もポイントです。米国から輸入した衣類を中心に販売しており、スニーカーブームもあって成長。私自身、当時は米・ロサンゼルスで買い付けもしていました。また、「アメリカンカジュアル(アメカジ)」はメンズファッションとレディースファッションの垣根が低いため、この時期から女性のお客さまが増えていきました。
3回目のチェンジは1997年。女性向けブランド「ローリーズファーム」のストア展開をスタート。OEM(製造委託)・ODM(企画、製造委託)型ファッションカジュアルチェーンとして、自社ブランドのOEM生産を開始しました。
そして、4回目のチェンジが2010年。他社との差別化を図るため、垂直統合型SPA(製造小売業)体制を導入。自ら企画、生産、販売まで手掛けることで、トレンドを捉えた商品を提供する体制へとシフトしました。
若松 SPAに移行することで、自社ブランドを複数手掛けるマルチブランド化が促進されました。現在のブランド数はどれぐらいありますか。
木村 EC専用のブランドも含め、年間1億円以上を売り上げるブランドは45あります。また、アパレルアイテムのうち自社生産比率は約半数まで上がっています。
5回目のチェンジで「プラットフォーマー」へ
若松 現在は、グループ売上高2931億1000万円のうちEC売上高比率は約28%と、非常に高い比率を実現しています。EC事業に参入されたのはいつごろですか。
木村 and ST(旧.st)を全面リニューアルして公式ウェブストアを開始したのは2014年ですが、業界でECを始めたのはかなり早かったと思います。アパレルの場合、ECによって顧客のサイズや好みがデータとして蓄積されます。特に、当社はマルチブランドですから、顧客層が幅広く、多様なデータの収集が可能です。
2024年12月にアンドエスティを独立させ、EC事業を承継させましたが、これは5回目のチェンジの布石と言えます。Platformerへの転換に向けた一番の軸。リアル店舗とEC、SNSなどを連携させ、コアなファンをつくり、継続的な購入につなげていることが当社の強みです。
最近ではリアルの良さとウェブストアの良さを融合させたOMO(オンラインとオフラインの併合)型店舗「and ST」の出店も積極的に行っています。
若松 国内は人口減少によるマーケットの縮小が大きな課題ですが、それでも国内のアパレル市場規模は約8兆円です。その中でアンドエスティの会員数は約2000万人であり、優位性や競争力が高い事業領域です。アンドエスティに蓄積される膨大なデータをいかに活用するかが、顧客生涯価値(LTV)を上げる鍵になりますね。
木村 AIやデータ分析への投資も含めたDXの推進によって、垂直統合された当社のバリューチェーンをアップデートしています。何十年にわたって蓄積してきたデータが心臓部であり、データを分析する社内のプロジェクトチームが2030年以降の世界像や当社が進むべき方向性について研究・開発しています。つまり、アパレルの小売店から「Play fashion! プラットフォーマー」への転換こそ、5回目のチェンジが目指す場所です。
若松 ライフスタイル全般の「Play fashion!」をつくるプラットフォーマーを目指すわけですね。ただ、これまでのチェンジは、紳士服からカジュアル衣料、ストアブランド展開、そしてSPAと既存事業を発展させる形でしたが、プラットフォーマーを目指す5回目のチェンジはステージが異なりそうですね。
木村 おっしゃる通りです。これまでは、言わば自社の洋服を売るためのモデルチェンジでしたが、今回は未知の領域への変革と言って良いでしょう。ここ数年は全国店長会議(国内外の店舗の店長が集まり企業戦略などを共有する社員総会)などの場でも、「かつては洋服店だったと言われるような会社になりたい」と言い続けています。すでに、アンドエスティでは他社ブランドも出店するなどオープン化を進めていますが、他社と組むことで新しい「Play fashion!」を生み出していくような場にしたいと考えています。
若松 トップメッセージでも、「アパレルカンパニーからグッドコミュニティ共創カンパニーへ」と発信されていましたが、このメッセージにステージそのものを変えていこうとする木村社長の意気込みが伝わってきます。
木村 少し前まで各社が利益を独占してきましたが、今後はサステナブルも含めて協働・共創が重要になります。他社と組むことで、「業界を一緒に盛り上げていこう」「利益をシェアしよう」という時代になっていくと思います。そのための場をつくりたいと考えています。
ファッションは平和の象徴的ビジネス。
海外でもプラットフォームを展開する
若松 EC上に共創の場をつくるのは面白いですね。新しい価値が生まれるでしょう。デジタル専門の流通モデル企業がリアルな小売店を買収していますし、その逆も増えていきました。プラットフォーマーの中でも、アダストリアはリアル(店舗)を持っていることが強みになると思います。
木村 おっしゃる通りで、リアルは重要です。コロナ禍を経験して、私たちはリアルの大事さを痛感しました。「Uber Eats」で食べ物を頼んで1人で食事を済ませてばかりでは、気分が上がりません。もともと、ファッションは平和の象徴的ビジネスだと思っています。気分を上げて、平和を生み出していくためにも、みんなが集まる場をつくることは重要です。プラットフォーマーはそのための場づくりだと考えています。
若松 海外展開についても、プラットフォーム事業が鍵を握ることになるのでしょうか。
木村 各ブランドを海外に広げるのが従来の戦略でしたが、プラットフォーマーを掲げた以上、新たな海外戦略を進めないといけません。アンドエスティのプラットフォームを海外、特に東南アジアに広げたいと考えています。すでに台湾では展開を開始しており、グローバルブランドから興味を持ってもらっています。
プラットフォーマーのビジネスモデルをいかに海外へ広げていけるかも、5回目のチャレンジの柱です。現在、全体の売上高に占める海外比率は8%ですが、2030年までに10%まで上げたいと考えています。
若松 海外売上高比率が20%を超えるとグローバル企業と言えます。挑戦していただきたいですね。1回目のチェンジから約10年おきにチェンジを繰り返しています。次々と新しいビジネスモデルに転換する決断力とチャレンジ精神に敬意を表します。
高い修正力と撤退基準が挑戦する人材と企業文化をつくる
木村 挑戦だけでなく、失敗できる文化がアダストリアの特長かもしれません。毎年新しいブランドを立ち上げますが、一方で撤退するブランドも多くあります。店舗についても、毎年50~60店立ち上げますが、退店も同じぐらいあります。中には、開店から半年で退店した店舗もありますが、そうした決断のおかげで赤字の店舗はほとんどありません。
若松 「槍の名人は、突く時よりも引く時の方が速い」と言われます。決断は社長の仕事ですが、撤退は決断の中でも難しい部分です。それを実行できるのは、優秀な経営者(名人)の証しなのです。
木村 社長に就任したのはちょうどコロナ禍でしたが、最も悩んだのは決断についてです。私見ですが、新しいことを始める決断よりも、やめる決断の方が難しい。そこは福田に勉強させてもらいました。
正直、誰しも自分が関わる事業はやめたくありません。特に、現場は売り上げを何とか上げようと頑張ってくれますが、状況が改善しなければ将来を見据えてやめる決断をしなければなりません。今は、やめる基準が共有されており、私以外も判断できる体制になっています。
若松 撤退できるからこそ、ブランド数も維持できているのです。営業利益率5%を維持されている理由がうかがえます。撤退できるからこそ挑戦できる。活発な新陳代謝は企業の成長を促します。
木村 以前あるメディアから取材を受けた際、「アダストリアは修正力が高い」と言っていただきました。大事なことは、修正しながら利益を出していけるブランドに育てていくことです。当社には、新しい挑戦を推奨した上でうまくいかなければ修正する。それでも駄目なら撤退する文化がある。それが独自の強みになっています。
変化と成長に挑み続け、2030年グループ売上高4000億円を目指す
若松 変化には、修正や撤退も含まれます。修正する文化と、やめる基準がチャレンジを保証してくれる。挑戦だけでなく、修正や失敗を経験できる組織は人を成長させます。2025年9月にはホールディングス体制への移行を控えていますが、今後の人材育成についてお聞かせください。
木村 ホールディングス体制に移行し、各事業会社をつくる中で経営者を育てていきます。社長の育成だけでなく、子会社の中の取締役についても、若手社員を登用して次世代を担う人材育成に取り組んでいきますが、その際、最も重要なのは権限委譲です。
若松 権限を与えないと人材の成長は限られます。木村社長ご自身も独立や子会社の社長を経て社長に就任されました。
木村 社長を増やす目的で、社長就任後に子会社を積極的に設立してきました。子会社の社長を育て、今後はグループをまとめる経営者へと育てていく。私自身、子会社の社長をした経験が非常に役立っているので、同じような機会をつくっています。機能会社も含めて、各分野のプロフェッショナルが経営者として育っていく仕組みが出来上がりつつあると手応えを感じています。
特に、当社には「失敗しても良い」と挑戦を応援する文化や、再度チャレンジできる社風があります。失敗して、降格しても、もう一度挑戦して昇格できる。私のような“出戻り社員”もたくさんいますよ。
若松 再チャレンジや復職も含め、人が成長できる仕組みが組織に備わっています。木村社長の経験が良い形で社内の人材育成に浸透すると、次世代を担おうと志す人材も増えていくでしょう。非常に楽しみです。
最後になりますが、今後の展望についてお聞かせください。
木村 2030年にグループ売上高4000億円、営業利益率8%を目標に掲げていますが、ビジネスモデルの転換なくして国内市場で生き残るのは難しいでしょう。利益構造も含めて変えていく必要があります。
アダストリアはDXや物流、M&Aも含めて中長期の成長を目指して積極的に投資をしてきました。グループ売上高が3000億円に近付いているのも、これまでの投資が実を結んだ成果だと捉えています。今後、さらなる成長を目指すには、主力となるアパレルブランドのシェアをさらに上げていくと同時に、ライフスタイル全般にカテゴリーを増やし、各領域でシェアを拡大していく必要があります。
当社がチェンジを繰り返すのは、変化が企業を成長させ、社員やお客さまの幸せにつながるからです。その実現に向けて、Play fashion!のプラットフォーマーになるべく5回目のチェンジを推進したいと考えています。
若松 修正力があり、撤退基準があり、再挑戦できる文化がある。それが失敗を恐れずに挑戦する企業風土を生み、人材を育て、事業の成長につながっていますし、「Play fashion!スピリッツ」なのだと感じました。商品力の高さやブランド力、生産や物流機能の充実など強さの理由はさまざまですが、社員の皆さんのスピリッツをこれからも育ててほしいと思います。本日はありがとうございました。

アダストリア 代表取締役社長 木村 治(きむら おさむ)氏
1969年茨城県生まれ。1990年に福田屋洋服店(現アダストリア)入社後、店長・エリアマネージャー・本部バイヤーを歴任。2001年に独立後、福岡市でワークデザインを設立。2013年にアダストリアグループに参画後、2018年に代表取締役副社長、2021年に取締役社長に就任。2022年より現職。
(株)アダストリア
- 所在地 : 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ27F
- 設立 : 1953年
- 代表者 : 代表取締役社長 木村 治
- 売上高 : 2931億1000万円(2025年2月期)
- 従業員数 : 6944名(2025年2月現在)
※ アダストリアは、2025年9月1日付で持株会社体制へ移行し、社名をアンドエスティホールディングスに変更予定
若松 孝彦 わかまつ たかひこ
タナベコンサルティンググループ タナベコンサルティング 代表取締役社長
タナベコンサルティンググループのトップとしてその使命を追求しながら、経営コンサルタントとして指導してきた会社は、業種・地域を問わず大企業から中堅企業まで約1000社に及ぶ。独自の経営理論で全国のファーストコールカンパニーから多くの支持を得ている。
1989年にタナベ経営(現タナベコンサルティンググループ)に入社。2009年より専務取締役コンサルティング統轄本部長、副社長を経て2014年より現職。2016年9月に東証1部(現プライム)上場を実現。関西学院大学大学院(経営学修士)修了。『チームコンサルティング理論』『100年経営』『戦略をつくる力』『甦る経営』(共にダイヤモンド社)ほか著書多数。
タナベコンサルティンググループ(TCG)
大企業から中堅企業のビジョン・戦略策定から現場における経営システム・DX実装までを一気通貫で支援する経営コンサルティング・バリューチェーンを提供。全国800名のプロフェッショナル人材を有し、1957年の創業以来17,000社の支援実績を持つ日本の経営コンサルティングのパイオニアであり、東証プライム市場に上場しているファームである。