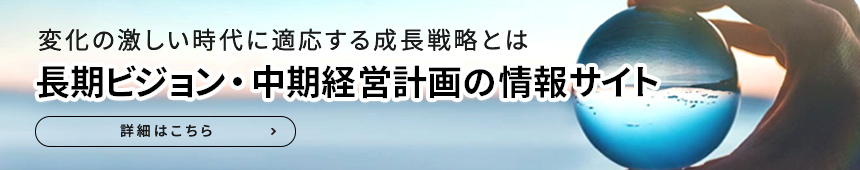左から、日本航空 人財本部意識改革推進部統括マネジャー 花岡晶子氏、部長 清水かおり氏、主任 鈴木駿氏、寺井美紀氏
「全社員の意識改革」が企業再生に不可欠
日本航空が大きな試練を迎えたのは2010年1月のことだった。東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請して破綻。これを受け、企業再生支援機構が日本航空の支援を決定した。翌月には京セラの当時名誉会長、稲盛和夫氏が日本航空の会長に就任。そこから新生・日本航空の改革がスタートした。
経営破綻に至った理由はさまざまあったが、2010年3月設置のコンプライアンス調査委員会では、経営陣を含む社員の意識が指摘されている。「誰かがやってくれるだろう」という責任感の欠如、現場と本社、部門間の一体感の欠如、採算意識の欠如などが一例である。稲盛氏は、そこにメスを入れた。
「まずリーダーの意識改革を行うことが再生の第一歩と考え、52名の経営幹部へのリーダー教育がスタートしました。車座になって再建の道を検討するその対話の中で、日本航空にも社員の心の拠り所であり行動の指針となるフィロソフィをつくりたいと、当時の社長をはじめとするリーダーが考えるようになったのだと思います」
JALフィロソフィが生まれた背景を説明するのは、JALフィロソフィを含めた企業理念などの浸透を図るための施策の立案・運営を担う人財本部意識改革推進部部長の清水かおり氏だ。その後、迅速にフィロソフィ検討委員会やフィロソフィ策定ワーキンググループが立ち上がり、JALフィロソフィは生まれた。
JALフィロソフィを社員に腹落ちさせる取り組みとは
破綻から1年後の2011年1月には、新しい企業理念が制定され、「JALフィロソフィ手帳」が発行された。このJALフィロソフィは、社員が大切にしている意識・価値観・考え方をまとめたもので、全40項目からなる。日本語だけでなく英語、中国語など多言語化して全世界で働く社員に向けて発信。第1部は「すばらしい人生を送るために」、第2部には「すばらしいJALとなるために」必要なことが明文化されている。
例えば、第1部の第1章では「成功方程式(人生・仕事の方程式)」として、「人生・仕事の結果=考え方×熱意×能力」とある。第2部では「一人ひとりがJAL」「採算意識を高める」「心をひとつにする」といった仕事に対する姿勢が言語化されている。
「企業理念や行動指針を策定しても、思うように浸透しなかった過去の経緯を踏まえ、JALフィロソフィは継続と社員参加を意識した取り組みとしてスタートさせました。その代表的なものが、2011年4月に始めた全社員を対象とする『JALフィロソフィ勉強会』です。勉強会は1回で終わるのではなく、毎年繰り返して開催することで社員への浸透を図りました」
そう当時を振り返るのは人財本部意識改革推進部統括マネジャーの花岡晶子氏だ。JALフィロソフィ勉強会は年4回開催。そのプログラムは、フィロソフィ検討委員会のメンバーが東京・羽田、千葉・成田をはじめ各拠点でファシリテーターを務めて、フィロソフィが必要とされる背景、その必要性や内容、そして各職場での事例などを紹介しながら理解を深めていくものだった。
「正直なところ、最初はJALフィロソフィに対して懐疑的な社員が多かったと思います。調達部門に在籍していた私も同様でした。しかし、再建を果たすには一部門の利益だけではなく、全体的な視野に立って最適な調達の仕組みを再構築しないといけないと考えるようになり、JALフィロソフィにある『採算意識を高める』『公正明大に利益を追求する』といった全社員の行動の結果が収支につながることを学び、調達改革の施策に反映していきました」(清水氏)
このJALフィロソフィ勉強会は、各地域の拠点で全部門が参加して行われた。それまで、多くの社員は自部門については理解していたが、他部門の業務や実態までは把握していなかった。実は組織間の壁も経営破綻の一因になっていたのだが、勉強会の開催により、他部門への理解という変化が生まれた。それを可能にしたのが、上司と部下のタテの関係や同部門内・同期などのヨコの関係に加えて、異なる部門の管理職と一般社員といったナナメの関係だ。
日本航空は約3万8000名の社員が協働して1機の飛行機を飛ばすバリューチェーンであり、全ての部門の連携が大切である。JALフィロソフィ勉強会での交流が、それまで知り得なかった他部門への理解を生み、社員一人一人に会社の全体像を知る機会を与えたのだ。

グループ全社員向けに毎年開催される「JALフィロソフィ勉強会」。フィロソフィの理解・共有・浸透を目的にスタートし、以降、年々進化しながら継続されている(左)。2023年7月に開催された「JALフィロソフィ発表会」(右)
発表や選考プロセスを学びや共有の機会に
JALフィロソフィの勉強会が始まって約13年が経過したが、この間も状況の変化を踏まえ、社員の行動変容につながるよう、工夫を凝らしてきた。コロナ禍ではいち早くオンライン開催にシフトし、世界中の仲間がつながれる場をつくった。現在は、社員同士の対話を重視し、テーマについても当初とは変化させている。
「かつてはJALフィロソフィに書かれている項目を1つ取り上げ、そのテーマに沿った事例を紹介していくという勉強会でした。近年は、一人一人のJALフィロソフィの学びと実践が、中期経営計画の実現につながることを理解できるようなテーマを選定し、テーマと自身の業務を結び付けて対話しています。
企業理念や中期経営計画を実現するためにJALフィロソフィがあるわけですが、一人一人が日々の仕事にどう向き合っていくか、より具体的な対話を行っています」
JALフィロソフィ勉強会の進化について説明するのは、人財本部意識改革推進部の寺井美紀氏である。
また、日本航空ではJALフィロソフィの実践事例を発表する「JALフィロソフィ発表会」を2011年から毎年開催している。社員が各自の取り組みを応募し、その中から選考された事例を全社に向けて発表する会である。しかし、2023年からその選考プロセスが変化している。人財本部意識改革推進部主任の鈴木駿氏は、狙いを次のように説明する。
「各職場で事例を選考してもらった後に、人財本部意識改革推進部に推薦してもらう形式に変更しました。選考プロセスも含めて全社の学びの場にしたいという思いがあったからです。これまでは自分の部署がどんな事例をエントリーしたのかが見えづらく、せっかく良い取り組みをしているのに部門内に広がらないというケースもあったので、そこを改善したかった。つまり、選考プロセスを部門内での学びの共有の機会につなげるため、応募者には自身が感じた困難や達成に至った理由などを中心に共有してもらい、より良い仕事をするためのヒントを各部から全社に広げていく発表会にしたいと考えています」

経営破綻からわずか2年で史上最高の営業利益を計上し、再上場を果たした。企業理念・JALフィロソフィの社内浸透が果たした役割は大きい
浸透のポイントは「継続すること」
JALフィロソフィ発表会の選考プロセス改善のように、企業理念やJALフィロソフィが浸透するためには、何が必要なのかを検討・実践してきた日本航空。同社のこうした丁寧な取り組みが、JALフィロソフィが多くの社員に浸透している秘訣といえる。
「JALフィロソフィの本質である人間として何が正しいかで考える軸を育むためには、継続性が大切だと考えています。一方で施策については周囲の声や状況を取り入れて、変化させることを心がけています。今年度は自身の体験や考えを自分の言葉として発することで、自分にも周りにも気付きや刺激を与えることに力を入れています」(清水氏)
例えば、2024年度もいくつか新しい施策に取り組んでいる。「JET CAFE」と名付け、社員が自身の取り組みを自分の言葉で全社に向けて語る施策の初回では、退役機のラストフライトにお客さまに搭乗していただくという「伝説のツアー」を実現した若手社員が登壇した。同世代の社員に対しては、「業務で抱く理想や疑問、不満は金の卵。それに気づいているのはあなただけ」と語りかけ、自身の上司に対しては、前代未聞かつ所属の業務と無縁の企画を最初から否定せず、どうしたら実現できるかを一緒に考えてくれたことに感謝を述べた。
また、国内外のJALグループ各組織からの代表者約80名の集まりである「PHILOOP(ふぃろるーぷ)」も立ち上げた。この名前には“仲間をつなげる、輪を広げる”という思いが込められている。
破綻後、上位層から始まった横連携の場作りを組織単位まで落とし込んでいくための「草の根活動」。今年度は各組織の良いところをキーワード化する活動を通じて、まずは自分の組織や仲間を知ることから始めている。こうした取り組みが実り、社員を対象にしたES(従業員満足度)調査の結果では、JALフィロソフィに関する浸透度の項目は、確実にポイントが上がっている。
さらに社外との交流にも積極的だ。パーパス経営を実践する同社には、さまざまな業種の企業から見学や交流のための打診が多くあるが、こうした機会をありがたく受け止め、互いが意見交換や取り組みを共有することで学び合う機会を創出。JALフィロソフィ勉強会で定着した学び合う文化は、今では社外へと広がり、他企業にも大きな影響力を及ぼすまでになっている。
日本航空(株)
- 所在地 : 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
- 設立 : 1951年
- 代表者 : 代表取締役社長執行役員 鳥取 三津子
- 売上高 : 1兆6518億円(連結、2024年3月期)
- 従業員数 : 3万7869名(連結、2024年3月現在)