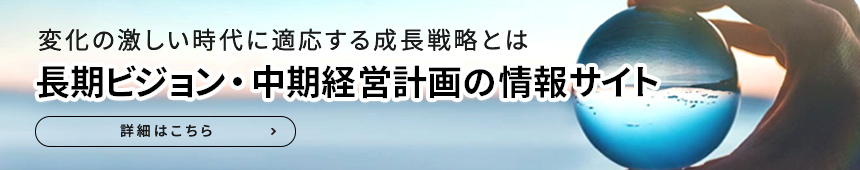そもそも何のためのビジョンなのか
日本のGDP(国内総生産)は、人口減少と高齢化の影響を受けて成長率の低下が続いている。結果、主要産業における国内市場は成熟し、今後、国内において大きな成長は望めない。
また、内需縮小によりほぼ全ての産業が成熟、衰退傾向にある中、労働者の減少にも歯止めがかからない。人手不足を補うためのDX投資の加速が指摘されているが、思うように進んでいないのが現状である。
今、日本は100年、1000年に1度の出来事が毎年発生するような変化の激しい時代。「VUCA」(将来予測が困難な状態)という言葉も定着しつつある。このような経済環境において、企業は「短期的な投資と回収」よりも、「長期的成長」を目指す傾向が強まっている。
企業は環境に適応し、変化し続けなければ永続発展できない。発展のためには、中長期的な方向性(ビジョン)を打ち出し、ステークホルダーに強く示す必要がある。
現在は、ビジョンだけでなく会社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)として体系化したり、世界でビジネスを行うためのPurpose(パーパス)を策定したりする企業が増えている。会社の在るべき姿を定めることは、社員のエンゲージメントを高めるだけでなく、人材採用や人材の定着など人的課題の解決においても効果を発揮する。
ビジョンと組織が連動していない企業
しかし、MVVやパーパスを掲げている企業の実態を見ると、良いとは言いがたい状態が目立つ。策定したアクションプランが現在の業績を生み出している業務と乖離しており、単に今ある仕事に新しいアクションが追加されているだけで、ワクワクする未来どころか、社員エンゲージメントは下がり続けている。このような状態が続くと、結果として責任だけが前に出て、「今より頑張る」ことでしか目標を達成できなくなる。
時間と費用をかけてつくった中長期ビジョンが形骸化し、数年に一度、内容を確認するだけになっていないだろうか。
人事・ESG領域に特化した課題解決支援サービスを展開するコーナーの「MVV浸透実態調査レポート」(2024年5月)によると、MVVの認知度に関する質問について、約45%が「MVVがあるかどうかわからない」と回答している。
取り巻く環境と自社の現状を分析し、今の延長線上にない未来を描いたはずなのに、これでは何も変わらず、現状の延長線上の経営にとどまってしまう。
いったいどこに問題があるのだろうか。実は多くのケースで、実装を見据えた落し込みの弱さが原因となっている。1週間先すら見通すことができず、日々の業務に追われている部門長、ワクワクする未来の意味すら分からず、作業に追われている社員など、さまざまなケースが考えられるが、まずは、自社のどこで根詰まりを起こしているのかを把握することが重要である。
それは、「つもり」という意識からの脱却である。会社は伝えた「つもり」、上司は伝えた「つもり」、部下は知っている「つもり」など、日本企業はビジョン実装においてコミュニケーションという部分に目を向けることができていない。
本稿では、ビジョンを策定した会社側の思いと社員との認識ギャップを明確にし、企業の人的課題解決においても効果を発揮するビジョン推進の手法について提言する。
「ビジョン実装サーベイ」で2つのギャップを明確にする
タナベコンサルティングでは、「実装」という言葉を「広く社員に浸透し、実際の行動に反映されている状態」と定義している。
そこでタナベコンサルティングは、「ビジョンは策定したが、社員に認知されていないように感じる」「前向きな未来をイメージして策定したのに、社員との間に温度差を感じる」「大半の社員がビジョンの存在を知ってはいるが、実際の行動に結び付いていない」といったクライアントからの相談をもとに、「実装」というキーワードを主軸に置いたコンサルティングサービス「ビジョン実装サーベイ」を開発した。
ビジョン実装サーベイでは、「ビジョンを策定した会社側の思いと社員の認識ギャップ」と、「ビジョン実装に向けたマネジャー層と一般社員層のコミュニケーションギャップ」という2つのギャップを明確にする。
まず会社側には、タナベコンサルティングが定義したSTS(Step to Success)に基づき、ビジョンの取り組み状況をチェックする。そして社員には、会社が策定したビジョンに対して、次の順番で質問を行い、階層・事業別での会社との認識ギャップを明確にする。
〈社員への質問項目〉
❶ 認知:ビジョンを知っているか
❷ 理解:ビジョンの内容を理解しているか
❸ 共感:ビジョンに共感しているか
❹ 体制:ビジョン実現に向けた推進体制は整っているか
❺ 行動:ビジョンに基づく行動ができているか
❻ 評価:ビジョンに基づいた行動が評価される仕組みがあるか
マネジャー層と一般社員層とのギャップを把握することも重要である。マネジャー側のビジョン実装に向けた取り組み姿勢やマネジメント能力について、自身の回答と部下の回答を見比べることでギャップが見えてくる。
ビジョン実装サーベイの結果、策定した会社側の思いと社員との認識ギャップがあった場合、解決策としてビジョン実装における推進体制を再構築することが必要である。次にアクションプランの例を挙げる。
〈アクションプラン例〉
❶ 現状の阻害要因を抽出
❷ 優先順位を決めて権限移譲と責任者の明確化
❸ 社内・社外に向けた認知方法の見直し
❹ ビジョン実装に向けたKFS(重要成功要因)とKPI(重要業績評価指標)の設定
❺ 現状の評価制度と組織体制の見直し、再構築の提案
また、ビジョン実装サーベイでは次の項目の課題も抽出できる。
❶ Purpose:自社の社会的な存在価値が明確になっていると感じるか
❷ Brand:自社の商品・サービスに対して誇りを感じるか
❸ Marketing:自社の価値はクライアントに明確に届いているか
❹ Sales:営業部門は自社の商品・サービスの価値を正しく伝えられているか
❺ DX:自社のDXは推進されているか
❻ SDGs:自社のビジネスは社会貢献できているか
❼ Accounting:正しく業績把握ができているか
❽ Engagement:ビジョン実装が自身の成長につながっているか
これらを抽出することで、ビジョン実装に向けて強化したいテーマが明確になるのだ。階層・テーマを絞った展開が可能となり、適切な実装策を打ち出すことができる。
企業の人的課題解決に向けて、人事部主導の下で進めるのも悪くはないが、自社が掲げたビジョンを実現させる手段、つまり全社の経営課題として捉え直していただきたい。
冒頭に掲げた「現状の延長線上にない未来」を創るため、実装を加速化させ、次のビジョン構築につながる一手を打つことが重要である。

エグゼクティブパートナー
大手印刷業界でマーケティング・顧客開発担当を経て、タナベコンサルティングに入社。企業のトップと業績に向き合い、常に新しい方法を模索して、地域の特色を生かした成功事例を次々に生み出している。中堅企業をメインに、中期ビジョン・中期経営計画の策定、BtoBブランド戦略立案、人材開発体系構築、動画を活用した技術伝承、ジュニアボード運営支援など、幅広い分野で多くの実績を残している。また、幹部や若手社員育成も得意としており、クライアントから高い評価を得ている。