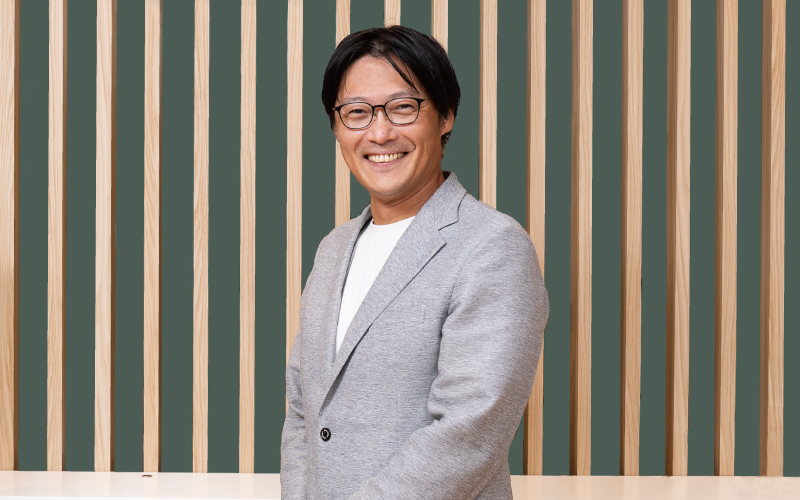心の健康を支えるデジタルメンタルヘルスの可能性 ~東京大学大学院医学系研究科特任教授 川上憲人氏に聞く~ 東京大学大学院 医学系研究科 特任教授 医師、医学博士 川上 憲人
同分野の最前線で研究を続ける東京大学大学院医学系研究科特任教授の川上憲人氏に、
デジタルメンタルヘルスの現状とその展望を聞いた。

デジタルメンタルヘルスの3つの役割
メンタルヘルス分野でデジタルサービスが拡大している。WEF(世界経済フォーラム)では、2021年にデジタル技術の精神保健への応用を広く「デジタルメンタルヘルス」と呼ぶことを提案しており、e-メンタルヘルスおよびその他の科学技術を含めた「デジタルプラットフォームを通じてアクセスされる、精神障害の予防・治療または人々のウェルビーイングを向上するすべてのサービス」と定義している。
デジタルメンタルヘルス分野で早くから研究者として活躍してきたのが、東京大学大学院医学系研究科社会連携講座デジタルメンタルヘルス講座特任教授の川上憲人氏だ。川上氏はデジタルメンタルヘルスの役割は大きく3つに分類されるという。
「1つ目は測定です。具体的には従業員などのメンタルヘルスの状態をデジタル技術を活用して測定すること。2つ目は予測で、デジタル技術を使って対象者のメンタルヘルスの将来予測をするというもの。3つ目が介入で、平易な言い方をすれば、ストレスを軽減する向上プログラムやストレスマネジメントなどのメンタルヘルス対策になります。
私は当初、大規模調査を通じた精神疾患の予測に関する研究を実施していたのですが、研究過程の中で対策の重要性を感じ、2000年代前半からデジタル技術を使ったメンタルヘルス対策の研究も行ってきました」(川上氏)
例えば、読書がうつ状態の改善に役立つという研究成果がある。川上氏はその方法にヒントを得て、漫画を活用したe-ラーニングプログラムの開発などを手掛けてきた。その後、AIを活用した認知行動療法プログラムなども開発してきた実績を持つ。
社会連携講座を開設して企業と研究開発に挑む
2022年に東京大学大学院医学系研究科に設置されたのが、社会連携講座の「デジタルメンタルヘルス講座」である。同講座では、15の企業グループと「測定」「予測」「対策」に関連するデジタルサービスの開発を手掛け、プロジェクトを推進してきた。
例えば、測定における共同開発では、注意力、計画力、空間認識力を把握するゲームにより、メンタルヘルスやワークエンゲージメントを予測できることが分かった。
同様に予測では、ストレスチェックの結果から、職場における1年後のうつ病の発症率やワークエンゲージメントのシミュレーションができるアルゴリズムの開発が行われている。
また、対策でも認知行動療法などを活用したe-ラーニングが開発され、効果評価が進行中である。
「長年にわたってデジタルメンタルヘルス分野でさまざまな研究を行ってきた成果を企業に提供したいという思いから講座を開設したのですが、いざ共同開発を始めると予想外の気付きがありました。中でも、科学的な研究結果をどのようにサービスへ落とし込み、実装していくかについては、多くの学びがありました。
通常、研究者は研究結果を論文として発表すれば終わりですが、社会に直接的に役立てるにはサービスとしての実装が不可欠です。そのためのノウハウを学ぶことができ、産学連携の必要性をあらためて実感しました。
2025年にはデジタルメンタルヘルス講座第2期がスタートしていますので、引き続き企業および社会のメンタルヘルスに貢献できるサービスの開発に取り組んでいきます」(川上氏)

2025年には東京大学大学院医学系研究科でデジタルメンタルヘルス講座第2期がスタートしている
産官学が連携してデジタルメンタルヘルスを推進
産官学連携を推進することでデジタルメンタルヘルスの発展に寄与してきた川上氏は、2025年7月に「心の健康投資推進コンソーシアム」の代表理事に就任した。
同コンソーシアムは、メンタルヘルス関連サービスを提供する事業者など67の会員団体の賛同を得るとともに、企業の人事担当者やメンタルヘルス分野をリードする学識者らで構成する16名のアドバイザリーボード、経済産業省、厚生労働省、その他民間団体の協力を得て設立された。
設立の狙いは、産官学のステークホルダーが協力し、職域での「心の健康」投資を拡大することで、企業の人材・組織に関する課題を解決し、個人の仕事の生産性やワークエンゲージメントの向上、組織のパフォーマンスの向上を図ることである。
企業経営に与える「心の健康」の影響は大きく、日本全体で年間およそ7兆6000億円の経済的損失があるといわれている※。これは日本のGDP(国内総生産)の1.1%に相当する額であり、企業経営においては極めて重要な課題といえるだろう。
心の健康投資推進コンソーシアムの発足は、2023年に経済産業省の委託事業でNTTデータ研究所が研究会をスタートさせたのが発端だ。当時、企業側からデジタルも含んだ職場のメンタルヘルスサービスを利用したいが、どれを選べばよいか分からないという意見が多く上がっていた。加えて、デジタルメンタルヘルスサービスは8~9割が効果を評価されておらず、質を担保しなければならないという課題もあった。
これらを解決するために研究会がスタートし、サービス内容、価格など開示すべき情報のリストを作成。2024年にはウェブサイトでサービス提供者を閲覧できる仕組みを構築し、2025年10月には「ウェルココ」という名称のデジタルメンタルヘルスサービス比較サイトをローンチした。
「企業は、メンタルヘルスの社内体制構築をしたい、エンゲージメントを高めたいといったように、各社で利用目的が異なります。そこでウェルココでは、自社の目的を選ぶと、100前後のサービスからニーズに合ったサービスが一覧で表示される設計にしました。ウェルココ運営とともに、職域における『心の健康への投資』の普及、実効性の向上という課題に向けた幅広い活動をカバーするため、2025年7月にコンソーシアムが立ち上がりました」(川上氏)
加えて、サービスの効果に関する根拠や満足度について情報を開示しているのも特徴だ。例えば、利用した企業の満足度、理論に基づくプログラムかどうか、実際に実験を行って効果があったかどうかなどの開示を義務付けた。これにより、サービスの質を担保していく方針である。
「当コンソーシアムはウェルココの運営と併せ、『日本の職場におけるメンタルヘルスをさらに良くするためにはどうすればよいのか』というシンクタンク機能を持ちたいと考えています」(川上氏)
科学的な根拠を提示して質の高いサービスを提供
デジタル技術の急速な進歩と、ステークホルダーが歩調を合わせた仕組みづくりにより、確実に企業に浸透してきているデジタルメンタルヘルス。今後の課題について、川上氏は、①科学的根拠の不足、②実装手順、③生成AIを利用したサービスの課題、の3つを挙げた。
「科学的根拠の不足について言及すると、どのくらいメンタルヘルスに効果があるのかを研究していないサービスも多いのが現状です。顧客満足度を高めたり、サービスの差別化を図ったりするためにも、効果検証や科学的根拠の開示は必要だと思います。そういう意味でも、ウェルココでの根拠の提示は重要な施策だと捉えています」(川上氏)
2つ目の課題は、企業などにおける明確な導入手順が定まっていない点である。現在のサービスはターゲットや目的が明確でないものが多いと川上氏は指摘する。例えば、「いつ、誰に提供するか」「導入後の利用促進」「導入後の効果検証方法」などの枠組みとサービスとがうまくかみ合っていない例が散見されるいう。
デジタルメンタルヘルスサービスを利用する企業のニーズに的確に対応でき、実効性を感じられる導入方法を検討する必要がある。例えば、1年目は何を測定し、2年目は何を改善していくべきかといったPDCAを回す使い方のできるサービスが求められている。
「3つ目として、生成AIを利用したサービスの課題が挙げられます。すでに生成AIを利用したサービスが登場していますが、人間のように振る舞う生成AIの受け答えによって、ユーザーが間違った学習や行動を引き起こす可能性もあります。生成AIの回答はあくまでも参考程度に捉えて活用する、といったユーザー側のリテラシー向上や、ユーザーが安心して使えるガイドラインが必要です」(川上氏)
こうした課題をクリアすれば、デジタルメンタルヘルスは企業の生産性向上や従業員の幸福度向上に寄与する具体的なツールとして、より大きな役割を果たすだろう。
※ Hara, K., Nagata, T., Matoba, M., & Miyazaki, T. (2025). The impact of productivity loss from presenteeism and absenteeism on mental health in Japan. Journal of Occupational and Environmental Medicine. DOI: 10.1097/JOM.0000000000003431.

社会連携講座
デジタルメンタルヘルス講座
特任教授 医師、医学博士
1981年岐阜大学医学部医学科卒業後、東京大学大学院医学系研究科(社会医学専攻)入学。医師、医学博士。1985年東京大学医学部助手、1992年岐阜大学医学部助教授、2000年岡山大学医学部教授、2006年東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野教授。2022年3月東京大学定年退職。同年4月一般財団法人淳風会理事、6月東京大学大学院医学系研究科デジタルメンタルヘルス講座特任教授、7月東京大学名誉教授。2020年紫綬褒章受章。2023年6月一般財団法人淳風会理事長、2025年7月一般社団法人心の健康投資推進コンソーシアム代表理事。