ハードウエアに精通する同社ならではのDXプロジェクトが続々と生まれている。
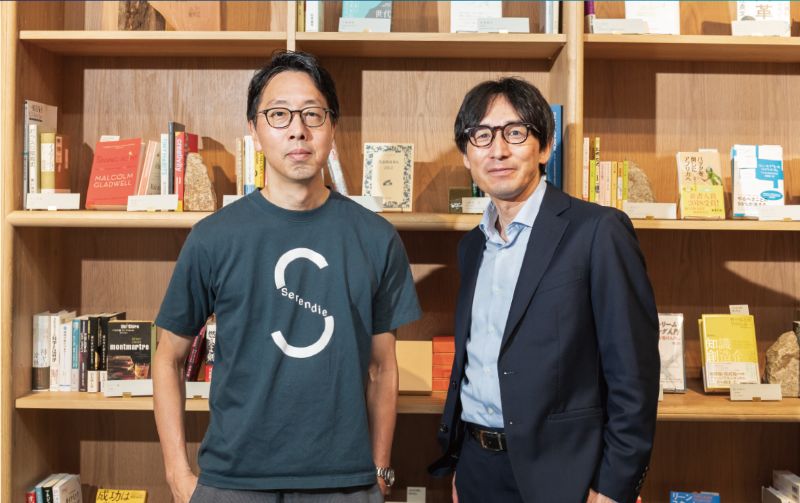
三菱電機 DXイノベーションセンター 副センター長 竹田 昌弘氏(左)
グローバル人財部 人財開発センター長 兼 DXイノベーションアカデミー教室長 西川 孝典氏(右)
循環型 デジタル・エンジニアリング企業へ
三菱電機の創業は1921年。100余年の長きにわたって、ハードウエアを中心に幅広く電気製品を作っている日本を代表する総合電機メーカーである。2025年1月に公開された新オフィス「Serendie Street Yokohama」では、全国から集結した多様なバックグラウンドを持つ社員が縦横無尽に交流しながら、データ・ドリブンの事業創出を推進。2025年3月期の売上高は5兆5217億円、営業利益は3918億5000万円と、共に過去最高を更新している。
一方で、日本は、IMD(国際経営開発研究所)の2024年度版「世界デジタル競争力ランキング」で67カ国中31位。「ビジネスの俊敏性」「上級管理職の国際経験」「デジタル・技術的スキル」などの項目で最下位という結果を突き付けられている。
そうした厳しい国際競争の中、三菱電機が2022年5月に掲げた経営戦略の柱は「循環型 デジタル・エンジニアリング」だ。その意義について、DXイノベーションセンター副センター長の竹田昌弘氏は、次のように語る。
「私たちが目指す循環型 デジタル・エンジニアリングとは、当社の強みである高度な技術力によって作られたハードウエアから信頼性の高いデジタルデータを取得し、そのデータから顧客の課題を分析。新しいソリューションサービスを生み出して、ハードウエアの価値をさらに高めていくというものです。デジタルソリューションサービス市場では、刻一刻と変化するゴールに応じて数週間から1カ月単位での開発サイクルを繰り返し、アジャイル(俊敏)にプロジェクトを進めていかなければ顧客のニーズを満たせません。
そこで、意思決定を俊敏に行い、リスクを恐れず新しい発想で価値を創出できるイノベーティブカンパニーを目指して、組織の構造や人の配置を抜本的に変革する方針が打ち出されました」
事業横断の鍵を握るデータオフィサー
2024年5月、まずは組織的な構造変革の前段階として、データの活用を通じて事業横断型サービスを創出するためのデジタル基盤「Serendie®(セレンディ)」を構築。
12の事業領域で展開している自社製品から、ありとあらゆるデータを一元的に集約できる環境を整えた。
「データの登録・管理・利活用の推進は、約20の事業単位ごとに指名された事業ドメインデータオフィサーが担っています。ビジネス立案者やデータサイエンティストが多様なデータをいつでも検索でき、事業横断的に分析できるようデータカタログを整備しているところです」(竹田氏)
例えば、鉄道事業では、運行車両のさまざまな情報を収集・活用できるシステムや車上機器・受変電設備などのコンポーネントを鉄道会社に提供している。ここから得られるデータをSerendie®に集約・分析した結果、電車がブレーキをかけた時に発生する余剰電力(回生エネルギー)を沿線地域の駅ビルや工場で再利用してはどうかというアイデアが浮上した。「社会システム事業本部」「ビルシステム事業本部」「FAシステム事業本部」など、複数の事業本部が連携して「鉄道エネルギーの最適化」という新しいソリューションサービスを提供する道筋が見えてきたのだ。
竹田氏は、「本事例を展示会で紹介したところ、非常に大きな反響をいただいております。顧客との連携を深めながら、鉄道沿線エリアの価値を向上させていけたら」と、新事業の将来性に期待を寄せる。
オフィス空間からマインドセット改革
同社は、このような事例を積み重ねて、2030年までに1兆1000億円のSerendie®︎関連ビジネスを創出する目標を掲げている。2025年4月には「デジタルイノベーション事業本部」を新設。その中に循環型 デジタル・エンジニアリングの推進を担う「DXイノベーションセンター」を編入して、グループ内に分散していたIT・DXに精通する人材を集約した。さらに、部署横断で約500名のDX推進担当者を招集。Serendie Street Yokohamaを拠点として、所属やバックグラウンドの違う多様な社員がオフラインで交わり合い、データを活用したさまざまなプロジェクトを推進できるオフィス空間を整備した。
「当社グループでは、連結で約15万人もの社員が働いています。これまでは数十年働いていても、他の事業本部に所属する人と接触する機会はあまりありませんでした。Serendie Street Yokohamaは、その縦割りのカルチャーやマインドを抜本的に変えていくことを強く意識してデザインした共創空間なのです」
そう語るのは、グローバル人財部の人財開発センター長である西川孝典氏だ。Serendie Street Yokohamaは、①事業アイデアを育成するため議論や検証を行うプロジェクトルーム【field】、②自由にアイデアを試すための実証実験を行う【garage】、③100人規模のイベントを実施できるカンファレンスホール【circle】、④偶発的な出会いを創出する交流エリア【yokocho】という4つの空間で構成されている。
また、社外の顧客やパートナー企業との交流も圧倒的に増えた。DXイノベーションセンターが人・データ・技術の新しい出合いを創出するさまざまなプログラムを企画運営し、事業創出の種まきを行っているという。
「これまでは営業担当者が顧客やパートナー企業を訪問するのが常でしたが、今ではSerendie Street Yokohamaに迎える機会の方が多いです。月40組以上のお客さまにお越しいただいています。コーヒースタンドやキッチン&カフェ、バーもあり、打ち解けた雰囲気で対話が弾みます。
イノベーティブカンパニーになるためには、どれだけ多くのアイデアを生み出せるかが勝負です。失敗を恐れず、仮説検証プロセスを繰り返しながら挑戦するマインドを全社に浸透していきたい。ここは、そのための拠点なのです」と、竹田氏は語る。
アカデミーで挑戦する風土を醸成
Serendie Street Yokohamaは、Serendie®︎を活用した新規事業創出の拠点であると同時に、担い手となるDX人材を育成する拠点としても位置付けられている。同社は、2030年までに2万人のDX人材を育成することを目標に掲げ、デジタルイノベーション事業本部の新設と同時に、「DXイノベーションアカデミー」という社内教育機関を開校した。
「私たちは、潜在的な顧客ニーズのマーケティングから事業化した後のサービス品質管理まで、循環型 デジタル・エンジニアリングのプロセスで求められるスキルセットを7つの役割(ポジション)に分けて整理しました。アカデミーでは、初級・実践・アドバンスとレベルを区分し、受講者それぞれの役割・レベルで学習すべき講座をパッケージ化。集中的かつ効率的にDXスキルを開発できるよう設計しました」(西川氏)
ここで特筆すべきは、データの分析・管理やシステムの設計・開発といった、いわゆる理数系の高度な専門性を必要とするコースだけではなく、マーケティング、ビジネスの企画・推進、UI/UXの設計などさまざまな専門性を土台としてDXの知識やスキルを磨いていけるコースが用意されているという点だ。
「DXと言われても何をすれば良いのか分からない人にも『1回チャレンジしてみようかな』と思ってもらえるよう、初歩から気軽に学習できる仕組みをつくりました。また、学んだ分だけキャリアアップにつながるよう認定制度も準備中です」と、西川氏。2025年度は1100名をアカデミー受講生として迎えた。うち50名は営業部門やスタッフ部門からの参加だという。
「DX=理数系というイメージを抱く人が多いかもしれませんが、事業化に向けては人文学や社会科学の視点も重要となります。いかに多様な人々を巻き込んでいけるかが最大の課題です」(西川氏)
2025年3月には、その課題感を共有する早稲田大学データ科学センターと協定を締結。早稲田大学の教育プログラムを活用して最新の技術と理論を習得する講座をアカデミーに組み込み、その成果をフィードバックして、双方の価値向上を目指すという。2026年初旬には、Serendie Street Yokohamaと同じビル内に、DXイノベーションアカデミーの学びの拠点を新設する予定だ。
「DXイノベーションセンターでは、すでに70前後のSerendie®関連プロジェクトが動いています。DXイノベーションアカデミーとの連携を深めながら意志を持ってデータを活用し、課題を解決していける人材を増やしていきたい。それこそが、100年以上にわたって蓄積してきたハードウエアの事業そして製品を強くしていくために歩むべき道だと考えています」(竹田氏)
人口減少、地域格差、気候変動、エネルギー高騰など、乗り越えるべき課題は山積している。同社の掲げる“Changes for the Better”(常により良いものを目指し、変革していく)というマインドが、地域、社会、そして世界に広がるよう、期待が寄せられている。

「Serendie Street Yokohama」は国内外数十にもおよぶオフィスを見学し、人と人が出会える場として創設された。事業アイデアを育成するため議論や検証を行うプロジェクトルーム【field】、自由にアイデアを試すため実証実験を行う【garage】、100人規模のイベントを実施できるカンファレンスホール【circle】、偶発的な出会いを創出する交流エリア【yokocho】という4つの空間で構成されている
三菱電機(株)
- 所在地 : 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
- 設立 : 1921年
- 代表者 : 代表執行役 執行役社長 漆間 啓
- 売上高 : 5兆5217億円(連結、2025年3月期)
- 従業員数 : 14万9914名(連結、2025年3月現在)





