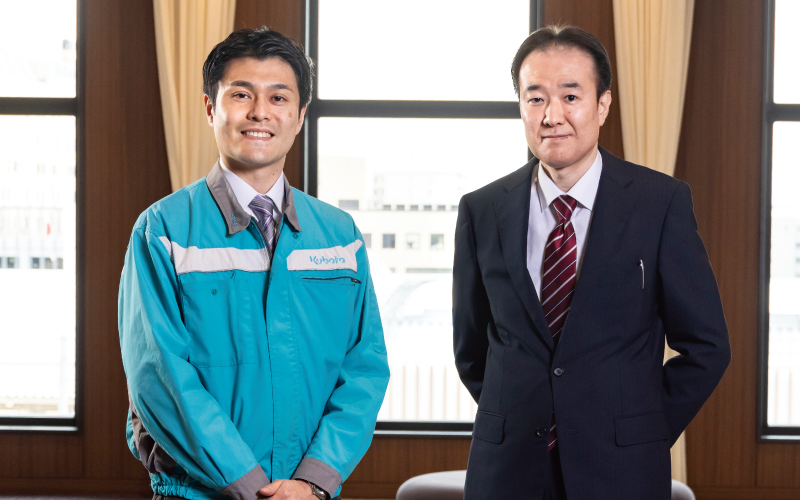年間300社超の新規開拓に成功
刃物の町・岐阜県関市に本社を置く福田刃物工業の創業は1896年。創業者の福田吉蔵氏が日本で初めてポケットナイフの量産をスタートしたのが始まりだ。その後、日本初となる紙断裁包丁の製造成功を機に工業用機械刃物メーカーへ転身。現在は、ペットボトルやタイヤなどの粉砕に用いられる粉砕刃や食品加工用など、多種多様な工業用機械刃物のメーカーとして事業を展開している。
特に、ここ15年は快進撃が続いている。2009年に6億円台だった売上高は2010年から右肩上がりで増加しており、2024年度には37億7955万円を記録。経常利益は6億8661万円(2024年度)に上るなど急成長を遂げた。好調の理由について代表取締役社長である福田克則氏は、「放任主義経営」を挙げる。
同社では放任主義経営によって自由闊達な風土が生まれ、1年間で300社以上の新規顧客の開拓に成功している。現在、年間1700社以上の顧客と取引し、約1万5000種類に上る製品を生産。その約30%を新規が占めている。さらに、かつて受注の約80%を代理店2社に依存していたが、現在はその割合が2%まで低下。直接営業が主流となっている。
直接営業の効果は新規顧客の開拓にとどまらず、刃物以外への進出にもつながった。特に、分業体制が当たり前の刃物業界において、切削から研磨、熱処理、ろう付けなど約40工程を全て社内で行う独自の一貫生産体制が幅広いニーズへの対応を可能にした。その結果、工作機械向け部品や半導体製造装置向け部品など新たな受注が広がっていった。
「本当のお客さまであるユーザーのご要望にお応えしたい。そう思っていても、代理店を通していると前に進まないことも多々ありました。一方、直接営業ではじかに顧客の声を聞くことができます。『ユーザーが本当は何を求めているのか』『何に困っているのか』といったニーズが鮮明になりました」(福田氏)
刃物メーカーというくくりも、代理店を通すという業界の常識も取っ払って、真摯に顧客のニーズに応えていく。その思考と姿勢が新たな顧客を創造し続ける。今でも主力製品は機械刃物だが、刃物以外の部品の売り上げも年々増加しており、今後も成長が見込まれている。

福田刃物工業 代表取締役社長 福田 克則氏
社員のやる気を引き出すのが社長の仕事
「どん底を経験したからこそ、生まれ変わることができました」(福田氏)。直接営業への挑戦をそう振り返るが、実は変化の芽はそれ以前から福田氏の中で育まれていた。
創業家に生まれた福田氏は、17歳の夏に単身で渡米。生徒の自主性を重んじる現地の高校・大学で7年間を過ごした後、NECに入社した。在籍していた半導体事業部はレベルの高い仕事であっても若手に任せる風土があった。5年勤務した後、1997年に福田刃物工業へ入社したが、「社員のモチベーションに大きな違いを感じた」(福田氏)という。
社内改革の必要性を感じた福田氏は、経営計画や目標を策定し、5S活動やISO9001の取得に勤しむなど社内の意識改革に取り組んだ。1日に何十回も工場を見て回り、経営者の集まりにも参加。片っ端から経営セミナーにも出席するなど、「『経営者がやるべき』と言われたことは全て実践した」(福田氏)ものの、一向に業績は上がらなかった。
「入社した1997年の売上高は8億3000万円でしたが、これは父の功績です。その後は、7億円から8億円を行ったり来たりで10年たっても10億円の壁を越えることはできませんでした」(福田氏)
そんな中、2003年に出席した講演会で出会ったのが、一生の師となる故・山田昭男氏だった。岐阜県で未来工業を創業した山田氏は、「残業、ノルマなし」「年間休日140日」「ホウレンソウの禁止」など型破りな経営で会社を成長に導き、一代で上場を果たした名経営者である。
「創業家に生まれたから後継者になれただけ。能力があるからではない」「社長は実務をやるな。社員をいかに感動させるか。それが社長の仕事だ」という山田氏の言葉を聞いた福田氏は「自分の勘違いに気付いた」という。後継者なのは自分の実力ではない。経営資源を生かして自走するチームをつくることが大切なのだ。
福田刃物工業の強さを語る上で欠かせない「放任主義」の芽が福田氏の中で徐々に育っていった。直接営業に切り替え、成長軌道に入った2013年に福田氏は代表取締役社長に就任。営業部への売り上げ目標の“押し付け”をやめ、エリアや担当を超えて自由に顧客を開拓できる体制を整えると、社員は生き生きし始めた。受注のスピードや生産性が格段に上がり、新規受注が急速に増えた。
現在、同社には社長が決める経営計画や売り上げ目標はない。コロナ禍を機に朝礼も廃止。福田氏は営業会議に出席せず、顧客の元に出向くこともない。営業戦略や売り上げ目標の設定は社員に任せており、問題が生じた場合も社員の判断で迅速に解決される。
個々のスケジュールを管理する行動予定表は社内から姿を消し、営業日誌も社員によって廃止された。管理しないと社員が怠けるのではと心配になるが、全てを任された社員は逆に自分の役割や必要な行動を考え、責任を持って判断するようになる。
福田氏が営業社員に伝えるのは「毎年ベストを更新する」というシンプルなミッションのみ。そのミッションの達成に向けて、社員は「最適な手段を自ら考えるようになる」(福田氏)。営業部から始まった放任主義は、製造部門や総務部門にも広がっており、社員が自ら考えて行動する自走する組織へと変化している。

世界三大刃物産地である岐阜県関市に本社を構える福田刃物工業

「食材がおいしくなる」と好評の超硬合金包丁「KISEKI:」。社内一貫生産体制、技術力に加え、社員に任せる風土があるからこそイノベーションが生まれている
放任主義を全社に広げ、社員が自走する組織へ
2023年に一般発売された超硬合金包丁「KISEKI:」は、そうした企業文化を証明する商品だ。同社初のBtoC向け商品であり、取締役で福田氏の実弟である福田恵介氏が発案し、2人のエンジニアと共に2年の歳月を投じて開発した。価格は1本3万4650円(税込)と決して安くないが「料理がおいしくなる包丁」として話題を呼び、注文が殺到。現在13カ月待ちの人気ぶりで、発売から2年間で受注額は10億円を超える異例のヒットを記録している。こうした状況を受け、同社はKISEKI:と受注増加中の工業用部品を生産する新工場の建設に着手。2028年春の稼働を予定しており、2029年12月期は売上高60億円を目指すという。
社員自ら高い目標を立て、そこを目指して主体的に行動する。急成長を遂げる理由は徹底した放任主義にある。それは数字からも分かる。福田氏が社長に就任して以降、経常利益率は常に10%超える高水準を維持しているのだ。
「社員自ら考えるので、とにかく決定が速い。社長への相談や報告も不要です。また、社長が会議に出席しないと短時間で終わります。私は話が長いですから(笑)。ほかにも社員同士の雑談が増えてチームワークも良くなりました。そうした変化が生産性の向上をもたらし、利益率の向上につながっています」(福田氏)
意識が高く、自走する社員の多い同社がこだわるのは“100%正社員”である。福田氏は「人にはお金以上の価値がある」と話す。
社員が自走する組織に変わり、新規開拓も年間300件を超えるなど顧客を創造する仕組みが回り始めている。2025年度は売上高44億円を見込むほか、その先もKISEKI:の増産を控えるなど明るい材料は多い。この先、どこまで突き進むのだろうか。福田氏に今後のビジョンを尋ねたところ、次のような答えが返ってきた。
「ビジョンはありません。ただ、社長として、いつも社員を喜ばせたい。経営者は社員のことだけ考えていれば良いと私は思います。まずは、現在130日の年間休日を1日でも多くする。そして、来年もベストを更新する。差別化するために新しいことに挑戦する。完璧ではなく前進することが大切です」
福田氏が考える良い会社とは、「業績が良い」「良い製品・サービスがある」「良い人材がいる」会社だ。「放任主義の実現度は、まだ60%ぐらい」だが、完璧な計画を立てるよりも、新しいことに挑戦して昨日よりも前進するのが福田流だ。その積み重ねが、今の福田刃物工業をつくっている。
福田刃物工業(株)
- 所在地 : 岐阜県関市小屋名353
- 創業 : 1896年
- 代表者 : 代表取締役社長 福田 克則
- 売上高 : 37億7955万円(2024年12月期)
- 社員数 : 160名