「デジタル」は今や企業が必ず実装すべき経営技術であり、どれだけ経営活動に活用できるかが競争優位と直結する。だが、その戦略を具体的に描けている企業はまだまだ少ないのが現状だ。そもそもなぜDX戦略が必要なのか、戦略を策定する際に押さえるべきポイントは何なのか、タナベコンサルティングのデジタルコンサルティング事業部の奥村格と武政大貴による新刊『DX戦略の成功メソッド 取り除くべき障壁は何か』(ダイヤモンド社)から一部抜粋・再編集して紹介する。
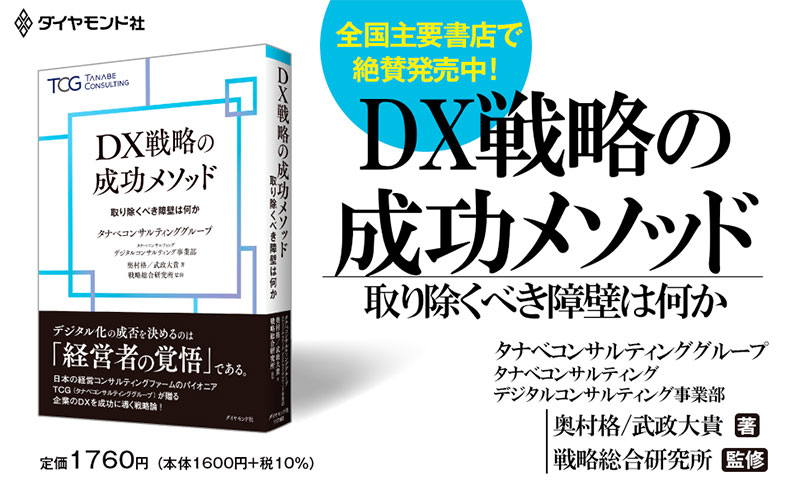
DX「戦略」が求められている
これまでDXといえば、従来は業務の効率化やウェブマーケティングなど、導入効果が分かりやすい「手段」への関心が強かった。だが現在は、そもそもの「目的」であるビジョン・戦略レベルから見直しを図る傾向が強くなっている。
こうした戦略回帰傾向は、これまで自社が推進してきたデジタル改革で思ったような成果が出ず、試行錯誤した上に行きついた経営課題であるといえる。つまり「戦略なきDXは成功しない」という企業の危機感の表れと見てとれる。
新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)が起きた2020年以降、約3年にもわたる行動制限(非対面・非接触)を機に、企業のデジタル化が進んだ。もはや「デジタル」は企業経営の前提になった感があり、経営判断そのものに大きく影響を及ぼす力を有している。
特に、デジタルを活用してビジネスモデルを変革するDXへの投資決断の遅れが、そのまま経営リスクにつながるといっても過言ではない。
DX投資とひと口にいっても、領域が広いゆえ一気に着手するのは不可能である。とはいえ、できるところから部分的に進めても全体像や目的が不明確だと収拾がつかなくなる。
例えば、設備投資費を抑えるため、更新期を迎えた古い業務システムの一部だけ更新し、どうにかごまかしながら使い続けているうちに深刻なトラブルが起きてしまい、全面更新した場合の投資額を大きく上回る損害額が出てしまったというケース。また、ウェブ広告を始めて自社の商品サイトの閲覧数は伸びているのに、問い合わせ件数がほとんど増えず、そもそも広告運用の目的は何だったのかという議論が社内に渦巻くというケースもある。
戦略は、投資の前提となるものだ。戦略なき投資は運頼みの“投機”に等しく、相当な確率で損を出す。DX投資においても同じであり、戦略が必要である。
DX戦略は“目指す姿”に近づくための羅針盤
DX戦略が必要な理由は大きく2つある。1つは、目指すべき姿に向かうための「羅針盤機能」。もう1つは、目指すべき姿に近づくために自社が何をすればよいかを示す「決断促進機能」である。
“目指すべき姿”とは、DXによって何を実現したいのか、目的地はどこなのかをまとめたものだ。これが「DXビジョン」である。ただ、DXで成果を上げるためには、これだけでは足りない。
目的地が定まっても「航路」を描かないと、そこにたどり着けないからだ。実現への具体的な道筋を示さないと、局所的なデジタルの導入を散発するにとどまってしまう。
結局どこに向かおうとしているのか、いつまでにどのくらいのデジタルレベルに到達すればよいのか、ライバル企業と比べてどの程度のデジタルアドバンテージを獲得すればよいのかが分からない。とりあえず出航したものの、大海原で風に身を任せて漂うことになってしまう。となれば、待っているのは「遭難」である。
したがって、経営者は、船長として明確なDXビジョンを掲げるとともに、その羅針盤として、取るべきアクションを具体化したDX戦略の策定・発信が求められるのである。また、目先の損得や情勢の変化などにとらわれず、現状とビジョンのギャップをつかみ、正しく決断していくことが重要である。
失敗例を挙げよう。老朽化した基幹システムのリプレースを迫られた、ある中堅メーカーの事例である。業務改善による生産性向上を中期ビジョンの1つに掲げていた同社は、基幹システムの置き換えと同時に業務システムも見直し、全社的な生産性向上を図ろうと考えた。社長は情報システム責任者に指示を出し、各システムを管掌している部門に今の課題をまとめてもらった。すると、さまざまな課題が次々と噴出し、やるべきことだけで山積みになってしまった。
社長は結局、リプレースの決断を先送りした。レガシーシステム(老朽システム)を使い続けた結果、同社は度重なる不具合の発生で保守運用コストが増大したほか、取引先の最新システムとの連携も図れず、会社全体の生産性が大きく低下した。
DX投資は時として、判断材料がそろわない状態で決めざるを得ない。とはいえ、自社の戦略や経営資源に見合った投資を実行しなければ、「帯に短し襷(たすき)に長し」で中途半端な投資に終わる。デジタル化を進める業務で一部アナログが残ったり、システム稼働率が低くなったりして、結局なんの変革も実感できなくなってしまう。すると、社長に対する猜疑心すら生まれかねない。
成功事例のつまみ食い的なDXになってはいけない。経営的視点からデジタルを見つめ、自社のアイデンティティーに即したDX戦略をつくることが重要なのである。
DXに取り組む前に押さえるべきポイント
得体の知れないものに投資するのは誰だって怖い。実際、何らかのシステムの導入を検討する際には、「このシステムを導入すれば300時間くらいは業務削減ができる」「今発生している人的なミスが70%は削減できる」という目安を知り、さらに類似するシステムやツール、サービスを最低でも2、3社ほど比較検討しているはずだ。
しかし、ことDXとなると、このプロセスをないがしろにしているケースも多い。デジタルリテラシーが低く、DXによる変革後の青写真が想像できないために陥りがちな状況である。「こういった仕組みをデジタル化すると、自社にとってはこんなメリットがある」という、導入後の効果を想定しておくことが必要だ。ひと口にDXといっても、どの経営領域で活用するのか、現状がどれだけDXを推進した状態にあるのか、によって得られる効果が大きく変わるからである。
まずは、領域ごとにDXで何ができるのか。効率化、省人化、利便性の向上といった直接的価値を把握しておく。「DXで何ができるのか」、すなわちDXの導入価値を知ることが、戦略構築前に押さえておくべきポイントだ。
DXの導入価値を知った上での次のステップは、その「先」に何を得られる(得たい)のかを明確化することである。例えば、ウェブ会議システムの導入を検討する企業の場合、「テレワークに利用できる」「社内に不在の社員も会議に参加できる」など用途だけを見ていると、「社員の通勤時間が減ってラクに仕事ができる」「会議日程の調整がしやすくなる」といった表面的なメリットしか享受できない。
企業によっては、「そんなことのためにお金は使えない」と投資自体をやめてしまうかもしれない。だが、本当に大切なことは、それらのメリットを活用して、何を得るかである。
一方で、デジタル化によって失われる機能をどのようにカバーするかという視点も必要である。例えば、ウェブ会議システムの導入により、社員同士の雑談の機会が減った。これを“無駄話が減って生産性が高まった”とプラス面に捉えることもできるが、“コミュニケーションの欠如による人間関係の希薄化”というマイナス面も大きい。
システム導入後、属人的なタスクや業務そのものが不要になり、自分の役割を見失った社員が寂しく会社を去った話も耳にする。人手不足を解消するためにデジタル化を進めた結果、社員が離れていくというのでは諸手を上げてデジタル化したと喜べない。
だが、このような人材にどう活躍してもらうかまで描いてデジタル化を推進している企業は少ない。導入価値と付加価値を想定するのと同時に、失われる機能をどのようにカバーしていくのかまで検討しておくことが、「実装後」のスムーズな運用につながる。
取り除くべき障壁は常に社内にある
例えば、顧客管理システムの導入を検討するとしよう。一般的なシステムで解決できる問題や現在の管理方法、課題感を正しく認識していないトップが、「よきに計らえ」とゴーサインを出す。だが、丸投げされたDX推進部門の責任者には顧客管理の実務理解が乏しい。責任者は何とかしようとして、一部の営業社員や業務部門とのやりとりをもとに、局所最適なシステムを導入することになる。
実態に即していないシステムを導入したことで、既存の営業支援システムや名刺管理ツールとの互換性がなく、従来のやり方に即した顧客管理も難しくなってしまう。運用を前提とした組織体制も想定していないため、実装後の推進力も働かない。典型的な失敗例である。
これが、デジタル化を進める上で実際によく直面する障壁の1つ、「トップのDXリテラシーの壁」である。経営者やデジタル推進に関する決裁権者のデジタルに対する理解度が著しく低い、あるいは知識に偏りがある場合に姿を現す障壁だ。
もう1つ、トップのDXリテラシーによって壁が出現しやすい状況がある。トップダウンの傾向が強く、トップが改革に大きく関わり過ぎるケースだ。トップがデジタル技術に精通していればよいが、付け焼き刃の知識でDXの本丸に居座るのも問題である。
解決しなくてはいけない課題が表に出てこなくなり、気付くとベンダーの言いなりになっていたり、DX推進部門以外の部署が面従腹背になっていたりする。マーケティング畑出身のトップがデジタル化を強引に進めた結果、営業部門の協力が得られなくなり、営業部門とマーケティング部門の対立を生んだというのはよく聞く話である。
DXを推進する上で忘れてはならないのは、こうした「壁」を突破することである。歴史と経験によって築かれた分厚い壁は、DX戦略を立案する前に対策を講じておかなければ突破できない。
障壁突破の鍵は「経営者の覚悟」
DX推進を阻む壁を突破する上で必要なことは、「経営者の覚悟」である。なぜなら、この壁を乗り越えるためには、①経営者自身の変革、②戦略投資の決断、③断行、④人的資本マネジメント、⑤組織風土改革などが求められ、いずれも経営者自身がなすべきことだからである。
DXには、ビジョンの実現に向けた継続的な投資が必要となる。経営者自身がDXとそれに伴う市場変化の可能性を最も理解しておかなければ、投資の意思決定ができず、DXビジョンは必ず形骸化する。それどころかDXに対し健全な危機感を持っている若手メンバーと、それを理解できない経営者の間でギャップが生まれ、有望人材の離脱にまでつながるリスクが考えられる。
DXに関する理解がないということは、数年後のビジネスに対する理解がないということでもある。もし、「デジタルに詳しくない」という理由でDXに距離を置いている経営者がいるとすれば、社内で最初に変わらなければいけないのは経営者自身といえるだろう。
経営者の覚悟がないDXは成功しないと断言してもよい。DXとは、トップ自らが本気で取り組むべき改革なのである。



