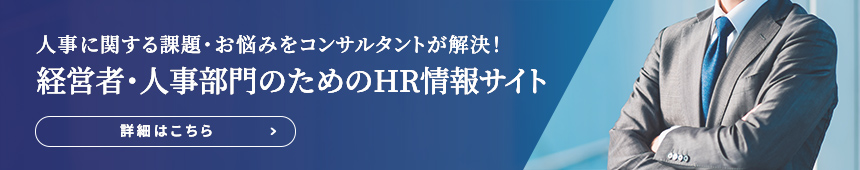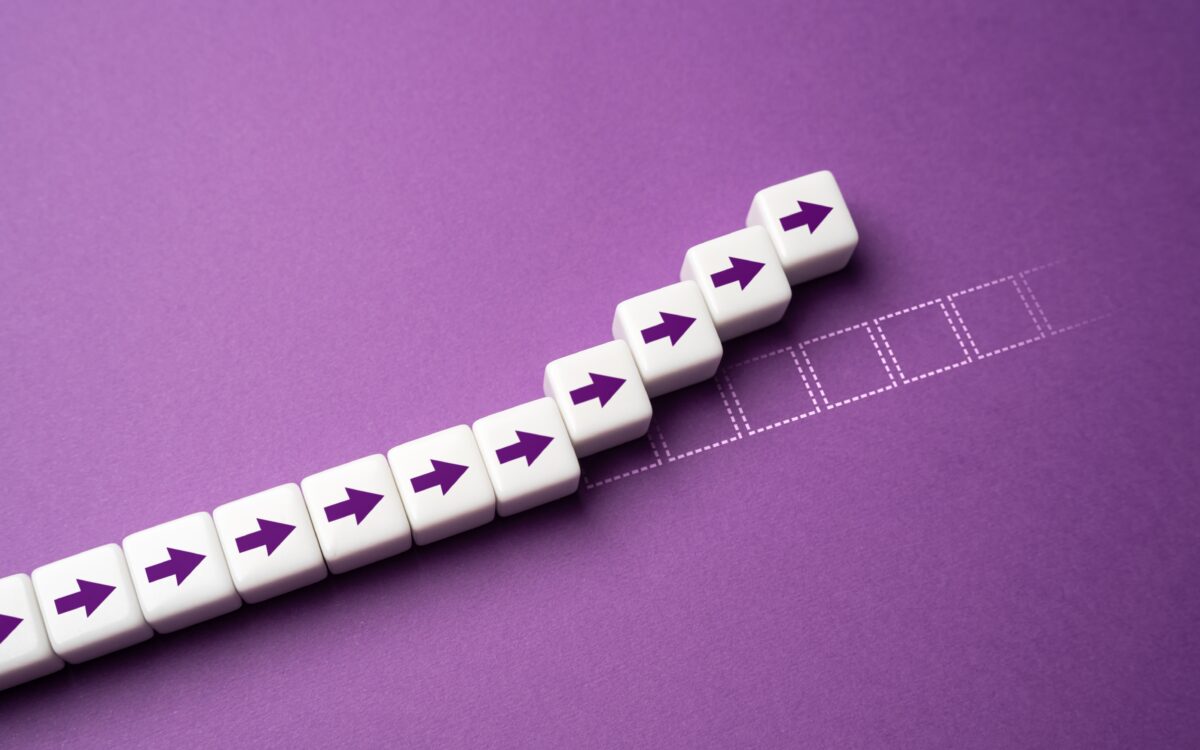若手のうちから経営知識を身に付ける
同社のプレマネジメント研修は、2024年7月から2025年2月まで全7回の集合研修で、ほぼ毎月1回のペースで進行する。プロフェッショナル・業績責任・付加価値創造・補佐責任・部下育成の「マネジメントの五大機能」を1つずつ、各回のテーマに設定。座学の基本講義とグループワークに加え、計数演習や経営数字の読み方も学ぶ。20~30歳代半ば、係長・主任クラスの12名が参加しているが、従来の選抜研修と異なるのが、受講は強制ではなく「任意」ということだ。
「対象年齢で人事評価が高い順に絞り込み、表彰制度の受賞歴なども踏まえて上司に相談して、『この人なら』と選定します。ただ、最終的に手を挙げて受講するかは、本人の判断に任せています。やる気や意欲が伴わないと、研修をやる意味も成長の伸びしろもありませんし、将来の経営を担っていく人材にはなれません」
意欲をどう測るかは難しいが、「任意」という選択肢を与えることで見極める、と川口氏。また、新たな研修はその狙いや対象の選定基準などへの不安や疑問が生じやすいが、その難しさも乗り越えた。
「社内通達文書に、『若手社員のうちから経営に関する知識を与えることで意識づけをし、成長を促し、本人の意欲も喚起する狙いを持って開催したい』と公表しました。また、人事部からも直接、業務に対する評価と会社が期待することを含めて『総合的にあなたがふさわしいと判断した』と伝えました。
多くの対象者が『受講します』とほぼ即答で連絡をくれました。期待を感じ取り、モチベーションにつなげてくれたようで、人事担当としてうれしかったですね。研修では全員が真面目で活発に議論していますし、坂入もときどき顔を出しています」
研修を間近で見守る川口氏は、受講者の変化も感じ取っている。開始当初は、休憩中の受講者同士のコミュニケーションは少なかったが、数回目から徐々に活発化したという。
「個人的には、そこがすごく重要だと思っています。彼・彼女らが育って部長や課長になったとき、他部署との連携は部課長同士のコミュニケーションで成り立ちます。その関係性がぎくしゃくしていたら、業務は円滑に進まず、ビジョンや経営計画の達成もできません。コミュニケーションがより一層、積極的になる芽が次々と出始めています」(川口氏)
マネジメント能力を養い「人が育つ」組織風土を醸成
プレマネジメント研修は、若手社員のうちからマネジメント能力や経営感覚を養うだけでなく、新たな若手ハイポテンシャル人材発掘の機会としても活用されている。
「プレマネジメント研修の受講者は、ゆくゆくは管理職候補となり、オイレススクールを受講する可能性が高くなります。ただ、プレマネジメント研修の受講が幹部候補の必須条件ということではなく、むしろこの機会に成長してくれることに期待しています。
当社は実力主義で、これまでマネジメント能力以上に業務遂行能力が重視され、昇進や昇格、登用が決まってきました。しかし、これからは『人を育てる』というマネジメントの要素が不可欠だと経営層も考えています。組織で見るマネジメントに重きを置き、人は育つ、という考え方から『人を育てられる人を育てる』という視点に変わり始めています。
当社のマネジメント像として何を求めるかを言語化し、明確なロジックを描き、経営幹部が育つ教育研修を組み立て、定着させたいと思っています」(川口氏)
初開催のプレマネジメント研修に参加した12名は、職場や業務内容が異なっており、研修に何を求めるかには個人差もある。必要な経営知識を身に付けながら、毎月、各回のテーマにひも付いた内容のリポートを提出する。
また、研修でインプットした知識は、日常業務の中ですぐにアウトプットできるため、必然的に一人一人の主体性が磨かれ、職場改善をはじめ「今、自分がいる場所から会社を変えていく」ことにもつながっている。
2025年2月の最終回には、社長や役員、上司に対する成果発表会がある。自職場の重点テーマとアクションプランの個別発表だ。長期ビジョン「OILES 2030 VISION」や中期経営計画の達成に向け、自分と職場、いまの会社に足りないものは何かを考え、どう実践し全社的に実装していくか。それぞれに取り組む姿は、長期ビジョンが目指す「サステナブルな社会の実現を、摩擦・摩耗・振動の技術+Xで貢献する」の、「+X」をいかに生み出すか、という取り組みそのものでもある。
「長期ビジョンや中期経営計画を達成するために、事業部の社員は事業の計画や提案を、バックオフィスの社員は事業をサポートし、+Xを生み出す人材をサポートするための提案を行うでしょう。実現可能性が高く、具体的な進め方までまとめる発表になるのでは、と楽しみにしています」(川口氏)
また、今後は価値創造と企業価値の源泉に育った人材を、他社に奪われないことも重要になる。
「当社の1人当たりの研修時間は長く、人材に対する投資はかなり多いと思います。人材流動性が高まっていく中、社員にオイレス工業で働き続けることを選んでもらうには、給与や賞与などの処遇はもちろんですが、それ以外にも『あなたをこう評価し、こんな期待をしている』と明確に伝えることも、これまで以上に大事にしていきたいと考えています」(川口氏)
社員に定着してもらい、持続的に活躍してもらうこと、会社が期待する思いを伝えること、そして社員の思いを生かすことは、あらゆる企業に共通するテーマだ。人的資本経営が求められる今、中堅・中小企業も含め多くの企業にとって、同社のような「将来を見据えた人材育成の仕組み化」が求められていると言えよう。

オイレス工業 企画管理本部 人事部 佐藤 正伸氏(左)、企画管理本部 人事部 企画課 川口 大志氏(右)
オイレス工業 (株)
- 所在地 : 神奈川県藤沢市桐原町8(本店・藤沢本社)
- 設立 : 1952年
- 代表者 : 代表取締役社長 坂入 良和
- 売上高 : 687億6500万円(連結、2024年3月期)
- 従業員数 : 2577名(連結、2024年3月現在)