企業価値を向上し、競争力を高める経営資源として「デザイン」を活用する――。戦略決定や商品・サービス開発、ブランディング、顧客・社会ニーズのマーケティングに役立つ「デザイン思考」を取り入れる経営手法とは。

クリエーティブ業界で存在感を高める揚羽。近年は「映文連アワード2019」(映像文化製作者連盟主催)の「経済産業大臣賞」、「日本BtoB広告賞」(日本BtoB広告協会主催)の2019年「企業カタログ(会社案内・営業案内)部・金賞」、2018年「ウェブサイト(リクルートサイト)部・銀賞」を相次いで受賞

クライアントと議論を重ねる揚羽の社員。「ユーザー視点のデザイン思考でご要望をいただくクライアントほど、成果を出しやすいですね。社内事情と言うか、内向き志向で上長が喜ぶことを重視することに意識が向いてしまうと、なかなか大きな成果は出せません」(忽滑谷氏)
デザイナーの存在よりも大事なのは「デザイン思考」の共有
経営が、より良く変わるmagic wand(魔法のつえ)――。サブスクリプションにテレワーク、オープンイノベーション、そしてデザイン経営にもそんな期待が高まる。だが、本当に魔法は起きるのか。その疑問に一つの解を示す指南役となるのが揚羽だ。
一貫したコンセプトのもと、採用活動全体のブランド構築を進め、クライアントの採用成功に寄与するリクルーティング事業、理念の定義付けから始まり、各ステークホルダーに向けたコンセプトの策定、クリエーティブツールの設計・作成を担うインナーブランディング事業、データに立脚した仮説構築から施策の立案・実行、効果検証までのPDCAを途切れなく実践し、MROI (マーケティング投資回収率)を重視した戦略を実現するマーケティング事業。同社の三つの事業領域は全て、クライアント企業がステークホルダーの最適なインターフェース(接点)を構築するのを、デザインが生み出す価値で支援するビジネスである。そのアプローチは、自社の企業価値向上にも発揮されている。
デザイン経営の必要条件は、経営チームにデザイン責任者がいること、事業戦略構築の最上流からデザインが関与することだ。同社でその重責を担うのが、制作部門と全社の制作物・広報をマネジメントする取締役制作担当の忽滑谷勉氏。CDO(Chief Design Officer:デザイン統括責任者)となる立場だ。
「デザイン経営を標榜しているわけではないのです。ただクリエーティブな人材がボードメンバーに多く、経営の意思決定にデザイナーの視点を入れるのは、創業時から当たり前の姿でした」(忽滑谷氏)
デザイナーや制作ディレクターを特別な存在と考えず、全社員がユーザー視点で考え、課題解決に導く。同社にはこうした「デザイン思考」が企業文化として定着している。クリエーティブ業界には、下請け・孫請けの階層的なビジネス構造がある中、大手企業と直接取引を展開し、成長を遂げてきたのもその成果だ。ロジカルなコミュニケーション力や寄り添って議論を尽くす姿勢、そして想像を超える価値づくりが顧客に高く評価され、それが選ばれる理由になっている。
「ビジネスが分かるクリエーターであれ」「クリエーティブが分かるセールスであれ」。クリエーターと営業スタッフが双方向で知見を高め合い、継ぎ目なく連携する姿は、29項目の行動指針を揺るがぬ羅針盤としている。「未来の一歩を創りだす」を筆頭にビジネスとクリエーティブの感性を併せ持つ「ハイブリッド人材を目指す!」もその一つで、人事評価にも適用。行動指針に対してどんな行動を起こしたかを半期に1回、評価面談で確認する。
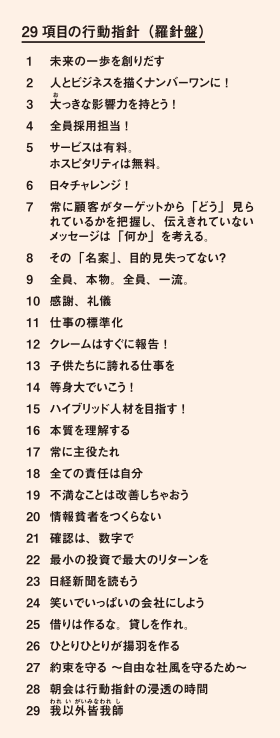
創業直後から掲げる29項目の行動指針。その一つである「常に顧客がターゲットから『どう』見られているかを把握し、伝えきれていないメッセージは『何か』を考える」は、デザイン思考そのものである
ブランド構築とイノベーションの実現へ
デザイン思考を全社的に共有・活用するイントラネット「アゲペディア」も独自の仕組みだ。ワークフローや過去の企画書などのナレッジを、失敗事例も含めて集約。クリエーティブ&ビジネスの情報が網羅されている。
「新卒・中途入社の社員は、悩んだり迷ったりしたらすぐに過去のノウハウを確認することができます。そのため、営業が制作進行を担い、制作が経営の最上流の要件定義から手掛けることも可能になります。
コミュニケーションをオープンにして、シェアする。まさにデザイン経営的な発想から生まれた仕組みですし、特にデジタルツールを積極的に活用しています。デザイナーに全てを背負わせてしまうのは違いますし、それよりも大事なのはデザイナー以外もデザイン思考を持つこと。職域で切り分ける必要はありません」(忽滑谷氏)
ブランド価値の構築とイノベーションの実現を通して、企業価値の向上に寄与するデザイン経営。CDO機能の確立を求める声が社員から主体的に上がる同社でも、「実はその実践は簡単ではない」と忽滑谷氏は語る。成果物や広報のチェックを繰り返す中で、「当社らしさをもっと意識して作ってもらいたい」と感じることも少なくないからだ。
「ブランディングは、その企業が持つ『らしさ』を、いかに明文化するかが大事です。また、イノベーションの創出も、進んだ技術があるから起こせるわけではなく、新しい何かとの組み合わせが必要になります。
デザインとは、言葉の意味だけ考えると物事の形状をつくること。でも実際には、らしさや強み、つまり指針となる在りかを知らないとカタチをつくれませんし、イノベーティブな方向性を考えることもできない。一つの方法論なのです」(忽滑谷氏)
顕在・潜在的な自社ならではの資産に気付き、可視化する。また、それを生かす可能性も描き出していく。簡単ではないが、企業価値を高めるアプローチとしてデザインは確かな経営手法となる。同社も、新たな社内施策に挑むときは、動きやすいようにミニマム(最小限)なチームを編成し、必ずデザイナーが参画している。その方が、らしさや強みを可視化させ、プロトタイプ(原型)を作るスピード感が向上し、内容も面白くなるからだ。例えば、ロゴマークのリニューアルも「わが社らしさとは?」から考えることで、変えるべきではないことは何か、変えるならどこをどう変えるかが見えてくる。インハウス(自社内)デザイナーが存在するメリットも、そこにある。
一方で、KPI(重要業績評価指標)などの目指す指標の設定や、成果を定量化しにくい難しさもある。
「やはり、どれだけ業績につながったかが判断基準になります。ただ、どんな時間軸で見るか、全社的なグロス(広告主への請求額)と一人一人のどちらの生産性を見るかで違ってきます。むしろ、最大のリスクはプロセス。どの組織にも、変化に適応できずに拒否反応を示す保守的な人がいますから」(忽滑谷氏)
デザイン経営の手法よりも人がリスクになるということだ。だが、克服すればエンゲージメント(愛着心・思い入れ)の醸成につなげることができる。
「クリエイティブ業界では、デザイン経営の推進は『中小企業にとってチャンスだよ』と言われていますし、チャレンジしない手はないと私も思います」(忽滑谷氏)



