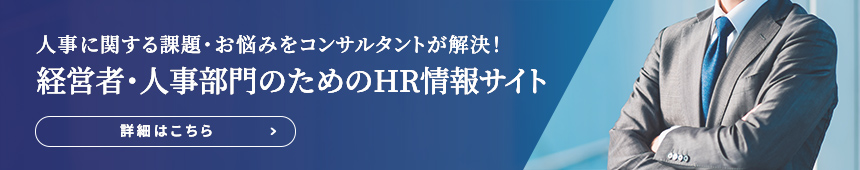ウェルビーイングの基礎学習体系
現代社会において、個人の幸福や健康、持続可能な生活を追求する「ウェルビーイング」が注目されている。人と人、人と組織の関係性が複雑化する現代において、「持続的な幸せ」や「イキイキと働きたい」といった、個人と社会の双方が「良い状態」を築くことの重要性が増しているためである。
本稿では、このウェルビーイングと基礎学習という考え方をいかに組織へと落とし込み、実践していくかを解説する。
ウェルビーイングの基礎学習体系とは、「個人や組織がより良い生活や働き方を実現するための知識とスキルを体系的に習得するための枠組み」を指す。
基礎学習体系では、まずウェルビーイングの定義と基本的な理論・モデルを学ぶことから始め、次の3つの要素を順に基礎学習体系へと取り入れながら学習サイクルを回す。
❶ 自己認識
自らがウェルビーイングな状態がどのようなことかを認知する
❷ 心理的スキル
ポジティブ・ストレスマネジメント、レジリエンス※など、マインドを健康に保つための心理マネジメントスキルを磨く
❸ リレーションスキル
人・組織・社会とのつながりを円滑にするコミュニケーション力など、コミュニケーションを主軸としたリレーションの質を高める
また、環境や職場のウェルビーイングを促進するための組織的アプローチや施策立案の視点も重要だ。実践的なワークショップやケーススタディーを通じて、学んだ知識を日常生活や職場で応用できる機会をつくることで、個人の心理的な自己管理能力と組織全体のウェルビーイング向上の双方に寄与できる。
ウェルビーイングを取り入れたマネジメント学習
ウェルビーイングの実現には、社員一人一人の「自分事化」と、具体的な「行動実践」へとつなげることが不可欠である。そのために有効なワークショップの一例を紹介する。
ワークショップの最大の目的は、参加者が自ら「幸福である」と感じる状態や、ストレスの原因について深く理解し、適切な対処法を身に付けることである。
社員は自己管理能力を高め、職場でのパフォーマンス向上や精神的な安定を図ることができる。企業側にとっても、社員満足度やエンゲージメントの向上、組織全体の生産性向上につながる。
具体的なプログラムの例として、「Well-Being Dialogue Card(ウェルビーイング・ダイアログ・カード)」が挙げられる。ウェルビーイング・ダイアログとは、一般社団法人ウェルビーイングデザインが開発した自己認識を高めるための対話型ワークショップのことである。
同法人の代表理事で、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授でもある前野隆司氏は、「幸福な状態には『やってみよう(自己実現と成長)』『ありがとう(つながりと感謝)』『なんとかなる(前向きと楽観)』『ありのままに(独立と自分らしさ)』の4要素が関係する」と提唱している。
52枚のトランプ型のカードには、それぞれウェルビーイングの要素に関わる質問(人生をかけて成し遂げたいことは何か、最近いつ達成感を味わったか、夢中になれることは何かなど)が記載されている。
そのカードを引いて、書かれた質問に答えられるとウェルビーイングの状態であり、答えにくい場合はそれについて深く考える機会とする。トランプ型カードというなじみやすい手法であるとともに、複数人で行うことで、自己理解と他者理解の双方が促進される。ほかにも、心理的スキル・リレーションスキルを具体的に学ぶワークショップをセットで実装すると良い。
ウェルビーイング学習の効果を最大化するには、「心理的なハードルを下げる」ことが肝要となる。自己との対峙や自己開示が必要であるため、参加者が心理的な抵抗を感じることなく、ポジティブな気持ちで臨める環境を設計することが望ましい。
また、組織におけるウェルビーイングの達成は個人で完結するものではなく、マネジメント層やリーダーの関与が不可欠である。その上で最も重要なのが、マネジメントシステムのアップデートだ。従来のマネジメントは、効率性や成果の最大化に重点を置いてきた。
しかし、これからの時代においては、「個人のウェルビーイングを重視することが、結果的に組織のパフォーマンス向上やイノベーション促進につながる」という価値観への転換が求められる。
短期的な成果を追求するマネジメントから、長期的な視点でウェルビーイングを育むマネジメントへと、企業の在り方を変革しなければならない。そのためには、マネジメント層に対する学習も変化させる必要がある。具体的には、主に3つの役割認識を促していただきたい。
❶ 組織を生み出す “設計者”としての役割
けん引型から創造型への組織構築ができるイノベーション・マネジメント
❷ 自らも学ぶ “教師”としての役割
人を育てることに力を注ぎ、自らが率先して学習する共育・マネジメント
❸ 仲間に奉仕する “執事”としての役割
自らが導く社員に献身的にリスペクトを送るサーバント・マネジメント
ウェルビーイングの推進を個人の課題として終わらせず、組織的なマネジメントシステムへと展開することまでが、企業に課せられた責務である。
OKRにウェルビーイングを取り入れる
OKR(目標と主要な結果)は、組織・チーム・個人の目標設定・管理方法である。組織や個人の目標(Objectives)と、その達成度を測る主要な結果(Key Results)を設定するフレームワークであり、明確な目標設定と定期的なレビューを通じて組織の方向性を一致させる。
現在では、MBO(目標管理制度)の代替として活用するケースが多いが、ウェルビーイングとの親和性は高い。OKRにウェルビーイングを取り入れるメリットは大きく次の3つである。
❶ 持続可能な高パフォーマンスの実現
社員の健康と幸福を考慮した目標設定により、過度なプレッシャーやバーンアウト(燃え尽き症候群)を防止し、長期、かつ持続的なパフォーマンスを実現する
❷「はたらく」に関するモチベーション向上
社員の幸福度や働きやすさを重視する文化が醸成されることで、組織の競争力が高まり長期的な成長につながる
❸ OKRを通した自己認識・自己開示機会の創出
OKRの進捗確認や振り返りを通して、自他とのコミュニケーション機会が増え、心理的安全性が高まる。OKRを単なる目標達成ツールとしてだけ活用するのではなく、自己学習と組織学習の両側面に展開し、長期的な組織効果を追求することがウェルビーイングを実現する上で重要である
ダイバーシティーという考え方の普及により、多様な価値観への受容度は高まった。今後は新たにウェルビーイングを取り入れることで、誰もがイキイキと働ける職場と社会になることを期待している。
※ 困難や逆境を乗り越え復元する力

HRBP ゼネラルパートナー
ホテル運営会社で事業戦略の策定、収益改革、人材育成、業務改善などの実務全般を経験後、タナベコンサルティング入社。人事制度の構築をはじめ、教育体系の立案や現場から幹部層を対象とした各種研修の企画など、各企業の実情を踏まえた戦略人事コンサルティングを得意とする。「人の成長なくして組織の成長なし」が信条。