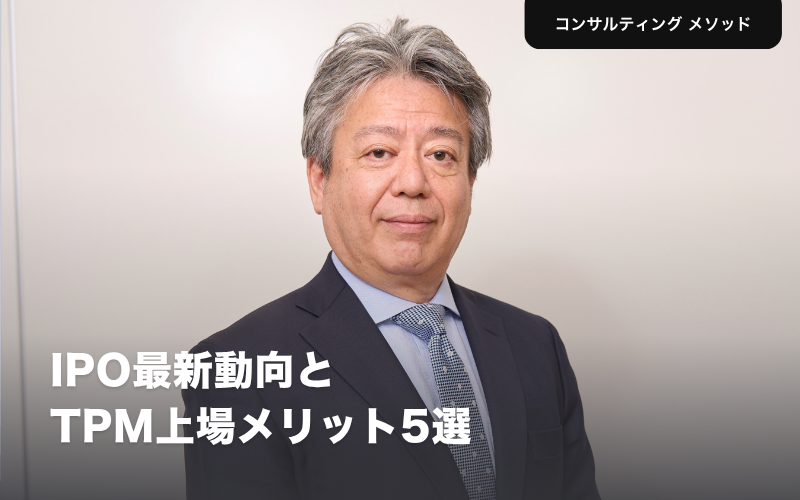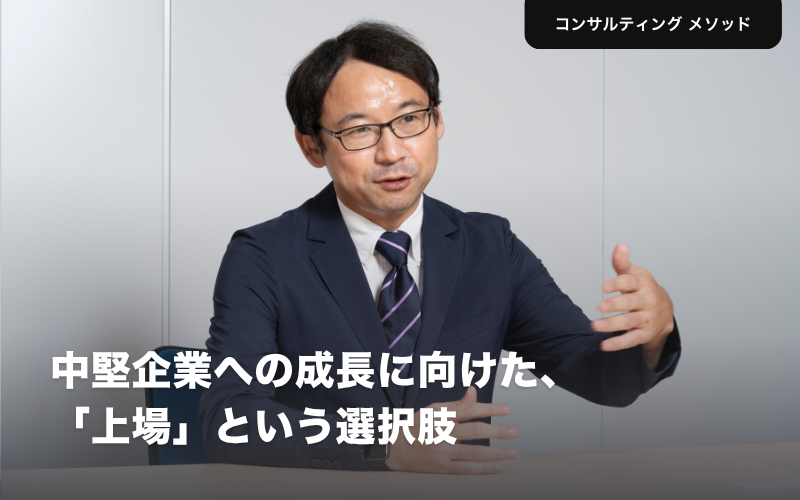取締役会による企業価値向上
コーポレート・ガバナンスは、企業の健全な経営を支える重要な仕組みであり、その中核をなすのが取締役会の機能である。
特に昨今の企業環境は、グローバル競争の激化やESG投資の台頭、企業不祥事の頻発など、取締役会に対してさらなる高度な役割と責任を求めている。取締役会には、企業戦略の妥当性やリスク管理体制の評価、経営陣の監督という多面的な役割があり、企業価値の最大化に直接的に影響を及ぼす。
この取締役会が実効性を持つためには、特に社外取締役の存在が重要である。社外取締役は企業内部の利害関係から距離を置き、独立した視点で経営を監督し、時には厳しい意見を述べることが期待されている。ある意味、「ダメな経営層の“首を取る”」ことが社外取締役の役割といっても過言ではない。
また、外部からの知見や多様な視点を提供することで、組織内での視野狭窄を防ぎ、経営の質を向上させる役割も果たす。このような透明で客観的な監督機能が働くことによって、企業は市場からの信頼を得やすくなり、中長期的な企業価値の向上に寄与するのである。
ただ、単純に社外取締役の数を増やせば良いというわけではない。東証1部の上場企業(金融を除く)を社外取締役比率別に4グループへ分け、2016年6月から2021年5月の5年間の株価推移を調べたデータ(広木隆「社外取締役の設置は株高の必要条件か」『日経マネー』2021年8月号、日経BP)によると、社外取締役の比率が高い企業の株価パフォーマンスはTOPIX(東証株価指数)を上回る。
これは、投資家が社外取締役の存在を透明性向上の要因として評価している可能性を示唆している。
特に興味深いのは、TOPIXを明確に上回ったのは、社外取締役比率が最も高い(過半数の)第1グループのみであり、比率が約3分の1の第2グループはTOPIX並みのパフォーマンス、それ以下の比率のグループはTOPIXを下回る結果となったことである。
この結果から、市場へアピールするためには、社外取締役比率を過半数にするなどの思い切った改革が求められ、「3分の1以上」という単なる数合わせでは評価されにくいと考えられる。
さらに、単に比率を高めるだけでは不十分であり、実際に機能する体制が求められる。
社外取締役の機能不全・価値発揮事例
小林製薬の紅麹サプリメントによる健康被害は、社外取締役の役割とその限界を浮き彫りにした事例である。第三者(事実検証委員会)による調査報告において、社外取締役がリスク管理体制の不備や意思決定プロセスの問題を見過ごしていたことを指摘した。
特に、創業家の影響力が強く、取締役会の独立性が確保されていなかったこと、社外取締役に必要な情報が提供されず、事態の把握が遅れたこと、そして、食品衛生管理の専門知識を持つ取締役の不在が大きな問題点であった。これらの要因が重なり、適切な対応が取られなかったと考えられる。
その中で、ある社外取締役は11年間もの長期にわたって同社の社外取締役を務めており、経営トップとの関係は非常に強かったものと推察され、その独立性には疑義がある。被害発生時、社外取締役に情報が共有されず、または被害を認識しない以上、取締役会は機能しようがない状況であったことは汲むべき点ではあるものの、積極的に情報収集を行わなかった事実において、この社外取締役にも落ち度があったと言わざるを得ない。
対照的に、味の素では社外取締役が積極的に関与し、経営の透明性と客観性を確保する仕組みが構築されている。
例えば、指名委員会等設置会社(取締役会の監督機能強化を目的に指名・報酬・監査委員会を設置し、経営の監督と業務執行を分離する株式会社)として、社外取締役の過半数を確保し、監督機能を強化している点が評価される。取締役会の前には各議案の論点を明確化すべく、社外取締役連絡会を開催するなどコミュニケーションを密に行っている。
また、「オフサイト取締役意見交換会」を開催し、社外で2日間にわたって企業価値向上の方法に関する意見交換を実施。取締役間の心理的安全性を向上させることで、取締役会の議論活性化を目指している。
さらに、ソニーの事例も興味深い。ソニーでは、取締役会における社外取締役の役割が変革の一環として活用され、企業の成長を後押ししている。特に、社内取締役の構成にも工夫を加え、異業種出身の経営者や海外経験を持つ人材を積極的に登用することで、事業の多角化やグローバル市場への対応力を高めている。
ソニーのようなコングロマリット経営(異なる複数の事業分野にまたがって企業グループを形成し、経営を行うこと)を行っている企業では、社外取締役のみに依存するのではなく、社内の経営陣とのバランスを重視しながらコーポレート・ガバナンスの実効性を確保している点が特徴である。
コーポレート・ガバナンス強化に向けたポイント
社外取締役の役割における課題は、①情報提供の不足、②独立性の欠如、③専門性の不足の3つに整理できる。
情報提供の不足については、社外取締役が経営の詳細を把握するための情報が十分に提供されていないケースが多い。この結果、社外取締役が適切な判断を下すことが難しくなり、実効性が損なわれる。
独立性の欠如について、特に創業家の影響が強い企業では、社外取締役が独立した立場を維持することが困難になり、経営陣に対する十分な監視ができない可能性がある。
専門性の不足については、企業の業態に即した専門知識を持つ社外取締役の登用が不十分である場合、特定のリスクに対する理解が浅くなり、ガバナンスの機能不全を招く恐れがある。特に、タレント社外取締役に対しては疑義を呈すものである。
いかに社外取締役を機能させてコーポレート・ガバナンスを強化するか。また、企業価値にプラスの影響を与えるかは、企業の取り組み次第である。改善案として、次の4点を挙げる。
❶ 情報提供体制の整備・強化
社外取締役が必要な情報を能動的に取得できる仕組みを構築し、定量的な指標を設けてモニタリング・マネジメントしていく
❷ 独立性の確保
指名委員会などを活用し、社外取締役の選任プロセスを透明化する。また、任期も設けて経営層との癒着を断ち切る
❸ 専門性の向上
企業のリスク特性に応じた専門知識を持つ社外取締役を選任する。著名人を採用する場合、自社のビジネスモデルとのシナジーを明確にした上で市場へメッセージを送る
❹ オフサイトミーティングの実施
社外取締役間で議論する場を設けることで心理的安全性を高め、活発な議論を促進する
適切に機能する社外取締役は、企業価値の向上に貢献する。しかし、形骸化した運用ではその効果は限定的となる。
提言した改善策を実施することで、より実効性の高いコーポレート・ガバナンスを整備していただきたい。

ホールディングス&グループ経営 ゼネラルパートナー
銀行にて、リテールからホールセールまでを経験。タナベコンサルティング入社後は管理会計を中心とした財務戦略や、ホールディングによる資本戦略策定などに従事。企業価値向上の観点による中期経営計画策定など、コーポレートファイナンス分野における上場企業向けのコンサルティング支援を得意とする。