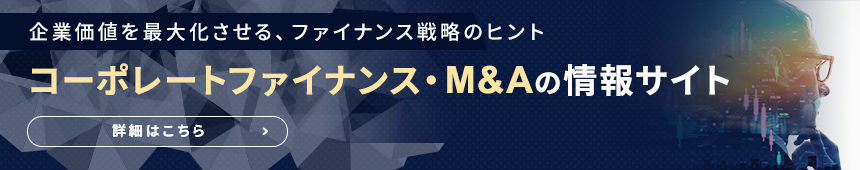M&Aにおけるリスク・目的・意図の明確化
M&Aは、企業の成長戦略において重要な手段であるが、その成功には慎重な準備と実行が求められる。特に、「DD(Due Diligence:買収監査)」と「PPA(Purchase Price Allocation:取得原価の配分)」は、M&Aのプロセスにおいて重要性が増しており、適切に実施することで買収対象企業のリスクを把握し、資産や負債の内訳を明確にできる。
DDは、企業の内部と外部の視点からリスクを特定し、M&Aの実行可否や条件の検討に役立つ。
PPAは取得企業が被取得企業の資産をどのように評価し、財務諸表に反映させるかを決定する重要なプロセスである。
これらの手続きを通じて、M&Aの目的や意図、リスクを明確にし、投資家に対して透明性を持たせることが求められるのだ。本稿では、M&AにおけるDDとPPAの目的や重要性について解説する。
DDによる買収リスクの特定
DDは、M&Aにおいて買収対象となる企業や事業の実態を把握し、その企業や事業が内包するさまざまなリスクを特定するための調査である。
DDの目的は、企業の内部と外部の視点に分けることができる。内部の目的としては、①M&A実行の可否に関する検討材料の提供、②価格、手法(ストラクチャー)、契約といった買収条件の検討材料の提供、③M&A実行後のPMI(統合プロセス)の検討材料の提供などが挙げられる。外部の目的としては、①外部利害関係者(株主、債権者など)への説明責任が挙げられる。
DDの種類は、事業(ビジネス)、会計・財務、税務、法務、労務、人事、環境、ITなど多岐にわたる。したがって、買い手企業には買収対象となる企業・事業の状況を踏まえて、実施するDDの種類を検討・選択することが求められる。
また、実施するDDの種類に応じて、専門家のアサイン要否を検討すべきだ。会計・財務DD、税務DD、法務DDは、DDで検出されたリスクが買収価格や買収条件に直結し、リスクの重要度が大きいケースも多いため、会計・財務DD、税務DDには会計士や税理士を、法務DDには弁護士を、DDの専門家としてアサインすることが一般的である。
事業(ビジネス)DDに関しては、対象会社の事業に対する知見が乏しい場合は、戦略コンサルティングファームをアサインして実施する場合もある。
そのほかのDDにおいても、リスクの重要度や社内リソースでの対応可否を検討の上、必要に応じて専門家のアサインを検討する。
DDを通じて企業や事業が内包するリスクを特定するために、買い手企業は買収対象となる企業のさまざまな情報を取得しなければならない。つまり、対象企業にはさまざまな資料(財務情報、契約書、社内規定など)を開示すること、インタビューや書面質問に回答することが求められる。この対応には、時間とリソースを投下しなければないため、対象会社の協力なくしてDDは成り立たない。
そのため、DD実施前の意向表明書や基本合意書で基本条件などを擦り合わせる段階で、実施するDDの内容、DD期間における情報開示への協力について、合意しておくことが望ましい。
DD実施のタイミングについては、基本条件などの合意後に買い手企業は対象会社に必要資料などの情報リクエストを行い、必要資料を受領してから1カ月~1カ月半程度期間をかけてDDを実施する。この期間は、対象会社から必要情報が適宜提示される場合の標準的な期間であり、資料開示や質問への回答に時間を要する場合は、DDの期間が長引くことや中断することもあり得る。
冒頭で述べたDDを実施する目的を果たすために、DD検出事項への対応方針を検討し、実行することが必要となる。DD検出事項のうち、M&Aの実行可否に関連する検出事項は次の順序で対応方針を検討する。
❶ 検出事項の重要性が乏しい場合
特段の対応を行わない(受け入れる)
❷ 検出事項に重要性があり、対応可能な場合
・定量化可能な場合:企業価値評価(バリュエーション)に反映し、買収価格の加減要素とすることを検討する
・定量化できない場合:買収手法(ストラクチャー)の変更や契約での対応の可否を検討する
❸ 検出事項に重要性があるものの、対応が困難な場合
M&Aを中止する
そのほか、M&Aの実行可否に直接関連はしないものの、M&A実行後のPMIの参考情報となる検出事項も存在する。
PPAの目的と重要性
PPAとは、M&Aにおいて取得企業が被取得企業を買収した際に支払った買収対価を、被取得企業に存在する資産・負債に配分し、財務諸表に計上する一連の作業(会計処理)を指す。
上場企業のように、公認会計士または監査法人の監査を受けることが求められる会社には、M&Aに際してPPAを行うことが求められている。
PPAを実施する目的は、M&Aにより取得した被取得企業の資産負債の内訳を投資家に明らかにすること(会計処理目的)だが、すでに財務諸表に計上されている資産や負債のほか、財務諸表に計上されていない無形資産も含まれている場合がある。
PPAには、取得企業が被取得企業の何に着目して買収したか(M&Aの目的や意図)を投資家に説明する役割も果たしており、特に無形資産の評価は重要となる。
PPAは、実施目的や実施時期の違いにより、次の2種類に分けられる。
❶Pre-PPA
Pre-PPA(プレPPA)は、M&A実施前にのれん(買収金額と対象企業の時価純資産の差額)や無形資産などの償却負担を踏まえた買収価額・事業計画(損益シミュレーション)の検討目的で実施される。
実施時期は契約締結前のDDフェーズで実施されるが、必ずしも実施する必要はない。評価に用いる資料もDDフェーズで入手可能な資料が基礎となることから、後述するPost-PPA(ポストPPA)と比べると、限定的となるのが一般的である。
❷Post-PPA
Post-PPAは、会計処理目的で実施されるPPAである。実施時期は、企業結合会計基準により、企業結合日を基準日として1年以内に行うことが求められている。
評価に用いる資料は、M&A実施後であることから、入手可能な資料は広く入手して評価をすることが求められ、最終的には監査法人の監査を経て確定する。
前述の通り、PPAにはM&Aの目的や意図を投資家に説明する役割があるため、取得企業が被取得企業の何の価値に魅力を感じて買収したか、被取得企業の強みの有無、収益やキャッシュ・フローなどの価値の源泉は何かを意識することに加えて、取得企業や被取得企業といったM&A当事者へのインタビューを行い、情報収集することが望ましい。
また、PPAは会計処理目的で行うことから、評価結果に対して監査法人の監査を経て数値が確定する。
評価に当たっては、将来予測といった見積もり数値や一定の仮定を用いた算定が行われる場面が多々あり、監査法人からも妥当性や根拠について説明を求められるため、採用する見積数値の前提や根拠を確認・検討の上、評価を実施すること。また、後々に監査法人から指摘を受けて大きな手戻りが生じないように、重要な評価の前提については必要に応じて監査法人とのディスカッションを実施することが有効である。

海外フィナンシャルアドバイザリー部 ヴァイスプレジデント
監査法人にて会計監査を経験後、グローウィン・パートナーズ入社。国内外の財務デューデリジェンス業務、バリュエーション業務に従事。トランザクションサービスを中心に、国内・海外M&Aや事業承継など多数の案件に関与し、現在は海外フィナンシャルアドバイザリー部にてクロスボーダーM&A案件を中心に担当。