自社教育の考え方・役割を再定義する
昨今の経営環境の悪化により、企業における人材育成の成果(効果)が測りにくくなっている。これは多くの経営者および人事・教育担当者が抱える悩みであり、「人材投資の費用対効果」という問題が顕在化した。
しかしながら、「自社の教育・研修が経営目標を達成するためにどの程度貢献したか」についてデータを基に正しく検証・分析したり、DX化を行い投資効果を立証している企業は限られている。中には「費用対効果(ROI:Return on Investment)」の測定は不可能と諦める人事・教育担当者も少なくない。確かに「人材育成の成果は測りにくい」という議論は、幾つかの点で正しい。
まず、多くの企業で用いられるペーパーテストなどの効果測定手法は、現場に必要な知識・スキルの一部を測定しているに過ぎない。また、現場で活躍する社員が保有するコンピテンシースキル(問題解決力やコミュニケーション力、応用力など)は測りづらい。
次に、どの時点で「成果(効果)があった」と見なすのかという問題がある。例えば、新入社員に教えたことは、5年・10年後にようやく成果となって表れるかもしれない。その意味で、企業の人材育成は中長期で考えるべき要素を多く含んでいる。
一方、近年の企業教育の現場を見ると、東京証券取引所が管理する、企業経営を管理監督する仕組みである「コーポレートガバナンス・コード」の改訂や、「ISO30414」(社内外への人事・組織に関する情報開示のガイドライン)の新設をはじめ、「直近の目に見える成果・施策を重視する」傾向が強まっている。
当然、企業は各種制度の変更などの対応を求められるが、今こそ自社の教育に対する考え方・在り方を再定義するタイミングでもあると言える。
人材育成の成果を見える化する3ステップ
人材育成の成果は、経営視点と社員満足視点の両軸で捉えることが重要である。成果測定は可能な限り業績とひも付く指標で測り、かつ、それらと連動して個人の成長を適切に評価する仕組みを整備することが必須要件であると言っても過言ではない。これらの実現に向けたポイントは、次の3点である。
❶人材育成の目的(Why:なぜ)を再定義
人材教育による成果の見える化が進まない企業の共通点として、人材育成の軸(目的)が不明瞭であることが挙げられる。このような企業は、業績が悪化すれば「営業力強化研修」、安定すれば「マナー研修」という安易な発想で研修を実施するケースが多く、業績悪化が教育の中止・延期に直結する傾向にある。これらの研修を否定するわけではないが、場当たり的な研修を行っている限り研修効果は期待できない。
このような近視眼的な研修からいかに脱却するかが、人材教育の成果の見える化に向けたファーストステップである。最初に「ゴール」を定め、現状とのギャップを確認し、バックキャストで全体像を設計していくことが重要だ。
ここで留意すべきポイントは、Why(なぜ)を基点として自社の人材育成の在り方を再定義した上で、What(何を)、How(どうやって)の方法論に落とし込むことである。その目的は、企業の経営目標や事業戦略と連動した教育制度の構築であり、ここが中長期的なKPI(重要業績評価指標)設計の土台となる。
❷現場での成果発揮と連動した効果測定の仕組みの整備
人材育成の現場でよくある課題に「研修と現場実務の非連動」が挙げられる。「研修で学んだことが現場で生かされず、身に付いているのかどうかが分からない」というケースである。
研修の目的や内容が充実していても、現場で生かされなければ意味がない。成果の見える化において重要なポイントの2つ目は、研修(インプット)→現場実践(アウトプット)→効果測定→研修(インプット)という継続的な学習サイクルの構築である。
正しいゴール(あるべき姿)と現場での効果測定(現状)を組み合わせた研修計画は、成果の見える化のみならず個人のモチベーション向上にも寄与する。また、効果測定で明確になった課題を上司・先輩と共有することで、課題に応じた適切なアドバイスや指導を生み、成長の加速化も実現する。
❸目的達成の難易度に応じたKPI設計
3つ目の課題として、「人材育成におけるKPI設計」が挙げられる。効果測定において必要不可決なKPI設計に難儀している企業は多いのではないだろうか。指標づくりの参考として、米国の経済学者ジェームス・D・カークパトリック氏が提唱した研修効果の測定方法、「新・4段階評価法」を紹介したい。(【図表】)
【図表】カークパトリックの「新・4段階評価法」
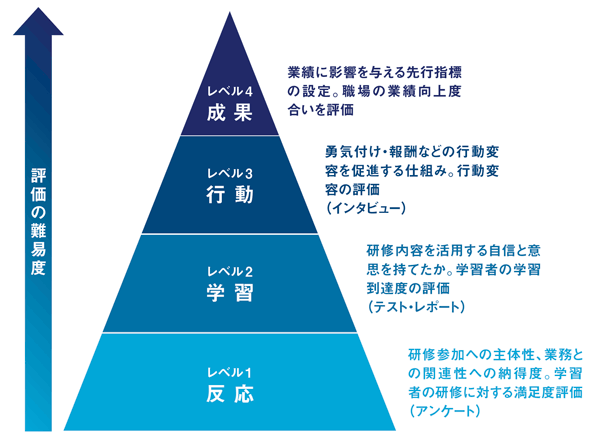
出所 : Kirkpatrick Partners公式サイトよりタナベ経営作成
本モデルは研修の効果測定手法として非常にメジャーである。「旧・4段階評価法」が研修自体(内容や講師など)を評価するのに対し、2016年に発表された新・4段階評価法は、成果を出すために必要な要素として、「行動・学習・反応」の評価を重視している。特に、「何を研修成果とするのか」「何がその成果を見る先行指標なのか」を研修前に決めることがポイントであり、前述したバックキャストでの研修設計との親和性が高いモデルの1つである。
最後に、教育成果の見える化に取り組む優良事例を紹介したい。音響エンジニアリング業を営むA社は、「若手社員の技術力の向上」と「計画的な人材育成」をテーマに社内アカデミー(企業内大学)を開校。教育成果の見える化を重点ポイントに、学びの善循環サイクルを構築している。特筆すべきは次の3点の連動である。
❶自社の業務遂行に必要なスキルマップづくり(在るべき姿の見える化)
❷スキルマップと連動したカリキュラム・研修づくり(学習進捗の見える化)
❸個別の進捗・課題を見える化するシステム構築(個人・組織能力の見える化)
同社では、学習進捗とスキルの習得状況を常に可視化し、半期ごとに上司・先輩と社員本人が振り返りながら、次の重点学習計画を立案している。
自社に適した人材育成手法を知るためにも、まずは自社の教育に対する考え方・在り方を再定義し、社員の成長を適切に評価する仕組みを整え、人材育成の成果の見える化を実現していただきたい。



