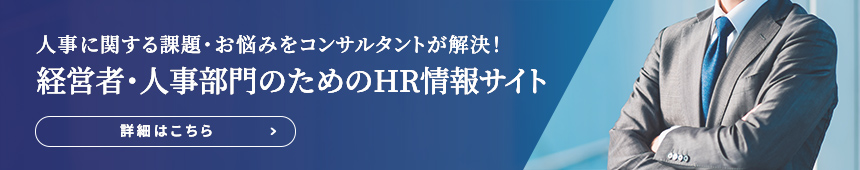毎年テーマを深化させ、社内コミュニケーションの温度を上げるナカリの経営者人材育成に迫る。

あらゆる種類のコメを扱うオールライスメーカー®
タナベコンサルティング・日下部(以降、日下部) まずは、ナカリの事業内容を教えていただけますか。
ナカリ・中村氏(以降、中村) 1923年創業の当社は「国内産米のオールライスメーカー®」として、あらゆる種類の米穀を加工・精米・販売できる一貫生産体制を整えています。とりわけ特定米穀(くず米)は日本一の取扱量を誇り、圧倒的な競争力を得ています。
特定米穀とは、主食用米として使われない、粒の小さいコメのことです。コメの収穫量全体から見ると5%程度のニッチな領域ですが、米菓・みそ・みりん・日本酒・焼酎・ビールなど多岐にわたって使用されていますので、皆さんも、おそらく間接的に当社の加工米を召し上がっていることでしょう。
日下部 ナカリは特定米穀の取扱量だけではなく、米穀の自社所有在庫量、異物除去装置の保有台数、比重選別機の保有台数、異物除去の精度、トレーサビリティーシステムの精度といった、コメに関する多様な分野においても日本一を実現されています。今日は、その背景にある人材育成に迫ります。
中村 ありがとうございます。初めにご紹介したいことは、人材育成の根本として40年前から続けている「朝礼」です。
長年参加している「管理者養成学校」という合宿プログラムに倣い、体操・発声練習・経営理念の唱和などを行っています。
一生懸命さを朝一番に表現する。列を整えて声を合わせ、心の整理をする。「経営理念」を体現する大切な時間と捉えています。
ジュニアボード研修直後に「組織活性部」を発足
日下部 朝礼をベースに、経営者人材を育成する仕組みとして2009年から取り組まれてきたのが「ジュニアボード研修」ですね。経営者人材の育成に向けて動き始めたのはいつごろからですか。
中村 2001年、ある経営団体の経営塾に参加して、経営理念と経営計画書を作成した時からです。当時36歳だった私は、同族経営の4代目後継者として、いつ経営に参画するか、どのように指導力を発揮していくべきかなどを思案していました。
この時に、学びを通して自社の足跡を振り返り、今後どうしたいのかというテーマを掘り下げ、経営理念に基づいた経営計画書を策定することの大切さを知りました。「中利商店」という創業以来の屋号を「ナカリ株式会社」に刷新したのも、同年です。
その後、タナベコンサルティングから「人間の健康診断と同じように、会社の健康状態をチェックしてみては」と提案いただき、2006年に経営診断を受けました。一言集約された診断の結果は「トップダウンで、社員を上から抑え付けている“文鎮型経営※”」。当時社長だった父親は、顔をこわばらせて憤慨していました。
日下部 文鎮型経営の原因は、どのような点にあったと考えますか。
中村 オーナー経営であることに加え、1カ月単位で売り上げに2倍、3倍の振れ幅がある米穀卸売業界特有の「値動きの激しさ」も少なからず影響していると思います。時々刻々の経営判断がとても大きな責任を伴うため、経営者が旗を振ってトップダウンで指示せざるを得ない業界でもあるからです。
私にとっても、診断結果は大変な衝撃でした。その後、組織体制と人事制度に関するコンサルティングを受け、文鎮型経営から脱却するためには、将来を担う経営者人材の育成が喫緊の課題だという考えに至ったのです。
早速、頭の柔らかい若手人材8名を選出し、2009年から2010年にかけて「第1期ジュニアボード研修」を実施しました。メンバーは経済環境分析、自社の経営資源・強み分析、ライバル分析から見た競争優位戦略など、全12回、1年間のカリキュラムを通して、少しずつ経営意識を持つようになっていきました。
現場の反発を乗り越え、改善活動を地道に継続
日下部 経営者人材の成長過程について4つのフェーズに分けて考察していきます。
2010年から2015年の第1フェーズは「手探り期」です。まず、ジュニアボード研修に参加したメンバーが中期ビジョンとアクションプランを策定しました。基本戦略のテーマは、「団結〜一人一人の意識改革で、未来(あす)のナカリグループを創る〜」です。目標管理の甘さや指導体制の不備により生じている各社員の温度差を解消し、個々の役割を明確にしていこうという意見で一致しました。
そして、研修を終えた4日後に「ナカリグループ中期ビジョン発表会」を開催し、20日後にはアクションプランを推進する「組織活性部」を発足。このスピード感には目を見張るものがありました。
中村 ジュニアボードメンバーが策定したアクションプランは、経営陣とは異なる客観的な視点からの分析に基づくものであり、非常に貴重だと感じました。
日下部 しかし、組織活性部の若手メンバーが一生懸命に働きかけても、現場にはなかなか浸透せず、手探りが続きましたね。
中村 私自身は、彼らが毎月定例会議を開いて地道に奮闘する姿を見ていたので、「新しい挑戦を続けているというだけでも大きな成果だ」と感じていました。
日下部 残念ながら、変化を嫌って離職した方もいらっしゃいましたが、どのように乗り越えていかれたのでしょうか。
中村 課題を解決するために行動を起こせば、必ずプラスとマイナス、両方の反応があるものです。とはいえ、60名中9名の社員が離職した影響は大きく、心境としてはどん底の状態でした。しかし、「ここまで来たら、やるしかない」と開き直ることにより、できることは徹底してやろうという気持ちになりましたね。
伝え方を統一して報告を徹底。それが「共走」の起点に
日下部 2016年から2020年の第2フェーズでは、改善活動の成果が少しずつ表れてきました。組織活性部のリーダーが、タナベコンサルティングの「幹部候補生スクール」に参加したことも、推進活動のきっかけの1つになったと伺っています。
中村 参加したリーダーは、幹部候補生スクールについて「他社のマネジメント層の方々と切磋琢磨できるので、良い刺激をもらえるし、広い視野で課題を捉え直せる」と報告してくれました。
日下部 第2フェーズからは、組織活性部が毎年テーマを掲げるようになりましたね。「報告の徹底」(2015年)、「5W1Hで報告精度UP」(2016年)など、一見すると非常に基本的なテーマですが、これらの成果はいかがでしたか。
中村 この時期の活動が、社員間の温度差を解消し、共有、共感、さらには納得、共創、共走へと発展していく起点になったと思います。毎年発表する経営計画書に組織活性部の活動紹介ページを設け、アクションプランの実行を通して、伝えることの大切さを意識化していきました。
日下部 2017年から2018年には「『なぜ・なんのために』で意味づけ」というテーマを掲げ、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を策定しました。
中村 バラバラだった社員の心が「共感」でつながっていった。その証がMVVです。組織活性部の活動も、「多能工化して各現場が助け合うことによって、休みやすい環境をつくろう」など、つながりを意識する動きが顕在化してきました。
日下部 第3フェーズ(2021〜2023年)には方向性が固まり、取り組みの成果が大きく花開きました。2023年7月の「創業100周年記念式典」に向けてさまざまなプロジェクトが始動し、社員の会社への思いを明文化した「いい会社をつくろう!!」をはじめ、大きな成果物も生み出されました。そして、2021年2月には「第2期ジュニアボード研修」も実施されました。
中村 後継者である私の息子も含めて、やる気のある若手を選出しました。第2期のメンバーは、この研修の集大成として、コミュニケーションの温度をさらに高めていこうというメッセージを「そうだよね」という素敵な言葉で表現してくれました。いま社内のいたるところに一言集約したパネルを掲示し、浸透を図っています。
失敗を恐れず挑戦の手数を増やしていきたい
日下部 第4フェーズを迎えた今、次の100年に対する思いをお聞かせいただけますか。
中村 会社は人生で最も多くの時間を費やす場所です。会社の活動が楽しくなければ、人生は楽しくない。そう言っても過言ではないでしょう。社員の皆さん、そして仕入れ先、販売先などステークホルダーの皆さまとともに、経営理念に基づいて幸せを実現していきたいと思っています。
そのためには、世の中の動きを敏感に察知しなければなりません。アップデートなくして、会社の発展はないからです。挑戦の手数は、多ければ多いほど良いでしょう。思い付いたらすぐにやってみる。やりながら上方修正していく。失敗したらすぐ止めて次に生かせば良い。そのような姿勢を大切にしたいのです。
最近、組織活性部のメンバーから「社長、こうしましょう」という提案が増えてきました。「どうしましょう」ではなく「こうしましょう」であれば、すでに挑戦のスタートを切っているわけです。この雰囲気を大切に、これからもナカリをアップデートし続けていきたいと思っています。
※ 経営者を組織のトップに置き、他の社員はほぼ同じ立場に置く組織形態による経営。横長の組織図の上に経営者だけが突出している形が文鎮に似ていることからそう呼ばれる

ナカリ 代表取締役社長 中村 信一郎(なかむら しんいちろう)氏
1964年宮城県中新田町生まれ。1986年東北学院大学経済学部卒業。1988年中利商店入社(2001年ナカリへ社名変更)。2011年ナカリ代表取締役就任。2013年タカラ米穀代表取締役、2016年ボン・リー宮城代表取締役、大崎倫理法人会相談役、全国米穀工業協同組合理事、2020年ナカリエステート代表取締役。
ナカリ(株)
- 所在地 : 宮城県加美郡加美町羽場字山鳥川原9-28-4
- 創業 : 1923年
- 代表者 : 代表取締役社長 中村 信一郎
- 売上高 : 150億円(グループ計、2024年7月期)
- 従業員数 : 150名(グループ計、2024年7月現在)

エグゼクティブパートナー
地域を思い、理念を重んじる「志」の高い経営者とともにビジョン構築、ビジネスモデル改革、チームビルディングに取り組み、多くの実績を上げている。また、中堅・中小企業の事業承継期の次世代経営体制・チームづくり、体系的な人材育成による自立型組織の構築コンサルティングにも高い評価を得ている。