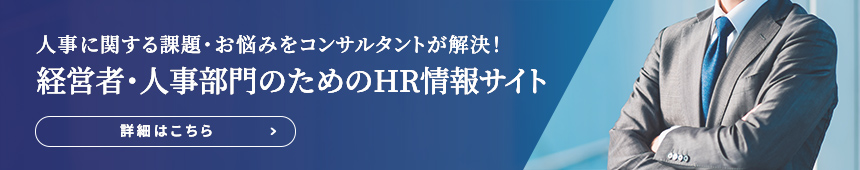社員の思いを込めた新たな経営理念
タナベコンサルティング・森松(以降、森松) 新潟クボタはトラクターやコンバイン、田植え機などの農業機械の販売・整備・メンテナンスを事業の中核に据え、新潟県内で高いシェアを誇ります。
近年では技術革新に力を入れ、自動化やIoT技術を活用したスマート農業を推進し、効率的な農業生産を支援。地域の農家と深い信頼関係を築いてコメの集荷・販売を手掛けるとともに海外販売に取り組み、2013年にはモンゴルに合弁会社を設立しています。
吉田丈夫氏は2024年1月に代表取締役社長に就任されました。
新潟クボタ・吉田氏(以降、吉田) 私は大学卒業後にディー・エヌ・エー(以降、DeNA)とクボタを経て、2016年に新潟クボタへ入社。営業所の所長、全営業所を束ねる直販部の部長、営業本部長、コーポレート本部長を経て4代目の社長となりました。
森松 2024年は創立60周年の節目でしたね。
社長に就任されてすぐに、新たな経営理念を発表されました。
吉田 事業承継の1年前からタナベコンサルティングの協力を得て、経営理念の刷新に取り組みました。それまでの経営理念は抽象的だったので、もっと事業の在り方や社員の働き方に近づけたかったのです。
まず、当社に在籍する約400名の全社員が、各5名ほどの班になって最寄りの営業所やサービスセンターに集まり、会社の存在意義や大事にしたい価値観などをざっくばらんに話し合いました。その結果を事業部長や部長クラスで討議し、「人間立社」という経営理念に結実したのです。
さらに、経営理念に基づいた「進むべき道」と「価値観」も策定しました。事業承継のタイミングにおける最も大きな仕事だったと考えています。
経営者に必要なのは悩み続ける力
森松 経営者として重要だと感じるスキルは何ですか。
吉田 「中長期的な視点」、より泥臭い表現だと「悩み続けられる力」でしょうか。
中長期的な視点というと、「未来を分かった上で、そこから逆算して戦略的な手を打つ」といった洗練されたイメージがあります。しかし、父や他社の経営者の話を聞くと、実際は「未来が見通せない状況で、必死でもがきながら窮地を脱するための判断を続ける中から道が開ける」ようです。
「本当はこうしたい」という悩みやもがきによって導き出された判断が、中長期的な判断の一貫性につながると考えます。
森松 ご自身の考え方や働き方に影響を与えた人物は誰でしょうか。
吉田 1人目はDeNA創業者、南場智子会長です。同社には「新入社員が社長の鞄持ちをできる」制度があり、私も当時社長だった南場氏に終日ついて回った経験があります。また、南場氏と同じフロアで1年間働くこともできました。とてつもないハードワークが連続する毎日で、社長業のすさまじさを痛感させられました。
もう1人は父の吉田至夫です。22年間、会社をけん引してきた中には、「これはすごい」と感じ入る側面と、「これは変えなければ」と思う側面の両面があり、私に大きな影響を与えています。
森松 経営者の役割を果たす上で難しいと感じることは何ですか。
吉田 社長2年目を迎えた現段階で難しいと感じることは2点あります。まず、部下のやることへの関与の度合いです。「部下への権限委譲」と「経営者としての要望」のバランスをどう取るのか、現場との“間合い”の取り方が難しいと感じます。
もう1つは、私の言葉が現場へ正確に伝わらないこと。私の下に4名の本部長、その下には10名近くの事業部長がいますが、「基本的にはAだが、状況に応じBに変更しても良い」といった指示を出すと、伝言ゲームのようになってしまい、現場に届くころにはAだけが強調されたり、Bだけが強調されたりして想定外の事態が生じ、面食らうことが度々あります。
森松 そのような課題も含めて、経営者人材を育成するための最も大きな要素は何だとお考えですか。
吉田 経営者人材とは、「自分で意思決定を行い、結果に責任を取れる人材」。自分で意思決定を行って成功や失敗を経験しないと、人として成長しないし深みも出ません。経営者人材の育成においては、対象者を実際に意思決定ができるポジション・立場に据え、実践経験を積んでもらうことが大きなポイントになると思います。
経営理念の浸透に努め組織文化の転換へ
森松 組織文化が経営者人材に与える影響をどのようにお考えですか。
吉田 組織文化には「これまで」と「これから」の2つがあると考えます。“製品の差”以上に“販売力の差”で形成されたのが、これまでの組織文化です。「夜遅くまで何件も訪問すればおのずと機械は売れる」と社員にハッパを掛け、県内では6割近くまでシェアを伸ばしました。自己判断する要素を減らし、ひたすら訪問し大量に販売することを奨励していたのです。
ところが、統計では農家はこの5年で2〜3割減少し、残った農家は放棄された農地を集約するところが多いので、一生産者当たりの事業規模は右肩上がりで拡大。すると、困り事のバリエーションが多様化し、新しい農業方法の紹介や農機以外の提案なども必須になってきました。
それに伴って「営業所ごとにお客さまの課題解決に結び付いた提案を考える」という方針で形成されるのが、これからの組織文化です。良いところは残しながら変えるべきところは大転換し、自分で判断して成功と失敗を繰り返しながら次のステージへ向かう、“良いとこ取り”を実現する策を探索している状態です。
森松 新潟クボタでは、販売の粗利益よりもサービスの粗利益が大きくなりましたね。
吉田 機械販売後のメンテナンスなどのサービスの収益が次第に上がってきました。販売会社なので営業職が花形という組織文化があり、他職とは大きな処遇の差がありましたが、「誰が利益を生み出しているのか」という観点ではサービス職の給与が高くなって当たり前です。
しかし、今でも営業職の処遇がはるかに良いままであり、ある程度は見直すべきなのですが、一朝一夕に進められることでもないため、慎重に検討しています。
森松 組織の価値観を変えるのは非常にハードです。経営者候補と組織の価値観やビジョンを共有するために取り組んでいることは何ですか。
吉田 社長就任時に新たな経営理念・進むべき道・価値観を発表しましたが、全社に浸透させる仕掛けはこれからです。
まずは、年1回開催している社員大会で全社員に経営方針書を配布し、私から経営理念の具体化について話しています。それに加えて、上期と下期に実施する査定評価で「価値観の5項目を達成できたか」という項目を設け、経営理念を行動に結び付けられるようにしています。一歩一歩、浸透させるしかありません。
幹部候補生スクールと早期抜てきで経営者人材を育む
森松 経営者候補育成のために実施している教育プログラムや実践的な機会の提供について教えてください。
吉田 タナベコンサルティングの「幹部候補生スクール」に毎年2〜4名派遣しています。課題ごとに自社の経営者と対話する機会が設けられているので、私の思いをじっくりと伝えたり、現場の声を深く聞いたりする好機になっています。
もう1つは先代が始めた「早めの抜てき」。年功序列の考えを捨て、見どころのある人材は思い切って昇格させる組織文化を育んできました。現在、営業所の所長は40歳代前半、部長は40歳代半ばが中心です。
私が営業本部長になってからは、プレッシャーをかけず「好きにやらせる」方針に転換。そのような変わり目以降に育った人材が増えています。
森松 若手を抜てきすると、結構失敗するものです。吉田社長も失敗から多くのことを学ばれてきたと思いますが、それを次代のリーダーにどのように伝えていこうと考えていますか。
吉田 「どこでしくじったかを明確につかんで、再発防止策を立てよう」という方針で相談に乗っています。それによって「失敗を隠さず、次に生かす」という思考が身に付くからです。
例えば、私は直販部長になったころから人事に携わるようになりましたが、思い切って新しい施策を実施すると、その施策を良く思わなかった社員たちが退職してしまったという苦い経験があります。事前に悩みを本人や上司から聞き出す仕組みを構築できたら、彼らがどのような状況に置かれているかを客観的に把握でき、再発防止につながります。
森松 最近は組織を一部改変されましたね。
吉田 長年、営業本部と管理本部の2本部制でしたが、メンテナンス事業が収益の柱になったことから、サービス本部を新設しました。さらに、2025年1月には営業本部を農業機械の販売を中心とした第一営業本部と、コメや建築、車両などの事業を展開する第二営業本部に分離しました。
第一営業本部は従来通りクボタとの連携が重視されますが、第二営業本部は新潟クボタが独自に動ける領域なので、やりようによっては収益が伸ばせると期待しています。第一営業本部は「深掘り」、第二営業本部は「探索」の位置付けです。
森松 第一営業本部・第二営業本部・サービス本部・管理本部で構成される4本部制になりましたが、それは経営者人材の育成につながりますか。
吉田 明確につながっています。4本部が競いながら経験を積む環境の中で、経営者候補や役員を育成していきます。本部長4名のうち2名は40歳代半ばの人材を抜てきしました。
森松 経営環境が厳しさを増す中、次代を切り開くリーダーに求められる資質は何だとお考えですか。
吉田 現在の組織や社風は、過去「当たり前」だったことに適応する形でつくられています。そのため、今起きている事象をしっかりと見つめて論理的に考えれば、もはや時流に適合しないものが多いと気付くはず。過去の当たり前に縛られず、事象を論理的に捉えて最適解を追求するスキルやマインドが大切だと考えます。

新潟クボタ 代表取締役社長 吉田 丈夫(よしだ たけお)氏
早稲田大法学部を2008年に卒業。その後、ディー・エヌ・エー(DeNA)、クボタを経て2016年に新潟クボタ入社。常務、専務などを経て2024年1月代表取締役社長に就任。
(株)新潟クボタ
- 所在地 : 新潟県新潟市中央区鳥屋野331
- 設立 : 1964年
- 代表者 : 代表取締役社長 吉田 丈夫
- 従業員数 : 418名(2024年4月現在)

エグゼクティブパートナー
外資系製薬会社にてマーケティング分析および臨床試験によるプロトコール(治療指針)制作担当を経て、タナベコンサルティングに入社。企業の成長発展のためのビジョン構築・中期経営計画の策定・新規事業・新商品開発を得意とする。また、社内風土改革や社員教育も数多く手掛け、親身なコンサルティングで多くのファンを持つ。