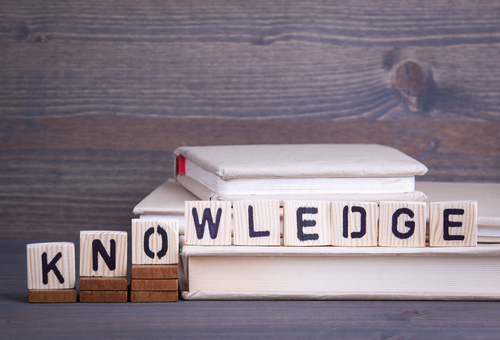なりーの野菜屋さん・ファーストオン「がりがり粗挽きピパーツ」
削りたての石垣島産のこしょう「ピパーツ」を味わえる。八重山そばはもちろん、鳥の水炊きや塩焼きそばにも
汗をかく人が価値を生む
「共創」という概念がビジネスの現場で注目され始めてから、そろそろ10年になろうとしています。
立場の違う事業者や組織が手を携え、時には消費者をも巻き込む形で事業プロジェクトを進め、新たな価値を社会に生み出す。それが共創の意味であると、私は理解しています。
ただ、言葉にするのは簡単ですが、これがまた難しい。利害関係が絡み合う中で、立ち位置の違う者同士がそんなにうまく事を運べるのか。また、別の角度から考えますと、既存の協業(力のある企業が主体となり、そこに業務を請け負う企業が参画するなど)と何が異なるのか。
もう何年か前の話ですが、そうした私の疑問に対して、明快と思える答えを提示してくれた人がいました。日本を代表するメガバンクで共創事業を担当し、ベンチャー企業とのプロジェクトを進めている男性でした。
「それはシンプルな話です。共創の場合には『汗をかいている人が偉い』んです。企業の規模ですとか、肩書きですとか、そうしたものは共創の現場では全く関係なくなりますし、関係なくあるべきともいえます」
とても納得できました。私なりの言葉でさらに咀嚼しますと、一緒に事を運ぶ相手から何を得るかではなくて、何をもたらすかを考え、行動に移す姿勢こそが、共創が成功するかの鍵を握る。そう表現しても良さそうです。
で、今回の話です。2024年の晩秋、沖縄県の石垣島を訪れました。仕事を終え、いよいよ帰京となる直前、島の人から「こんなものがあるんですよ」と教わった新商品に、私はとても引かれました。
挽きたてを味わう
商品名は「がりがり粗挽きピパーツ」といいます。ピパーツというのは石垣島を含む八重山地方に根付く「島こしょう」です。それは一般的な黒こしょうとは別物で、正式名称はヒハツモドキと言うそう。辛さだけでなくて、柑橘というべきかシナモンのようなというべきか、甘みも感じさせるスパイスです。
島こしょう自体は、もうご存じの方は少なくないかもしれませんね。石垣島で八重山そばのお店に入ると、卓上にまず確実に島こしょうを微粉末状にした小瓶が置かれていますから。これを八重山そばに振りかけると、味が引き立ちます。
では、この商品はというと、中身はかなり粗い粒のままの島こしょうです。で、容器は透明な樹脂製のペッパーミル(こしょう挽き)。つまりは、使うたびにミルを回して挽きたてを味わえるという話です。
値段は1540円(税込み)とかなり立派なものです。それでも私は躊躇なく購入しました。島の香りを家にそのまま持ち帰れて、しかも長く使えそうだからです。実際、これが面白かった。何も八重山そばにだけ合うというものではない。鳥の水炊きにも良かったし、塩焼きそばに振りかけても抜群です。
微粉末状の島こしょうは、島のお土産物屋さんなどでこれまでも買えましたが、ペッパーミルと組み合わせることで、新たな価値提案を成せているところが、私の評価した理由でした。
実は相当思い切った商品
なぜまたこんな発想を物にできたのか。興味を抱いて、帰京後に商品開発の当事者に連絡を取ってみたのですが、ここからの話がまた面白かったのでした。
この商品、石垣島で食品加工業を営む「なりーの野菜屋さん」と、同じく島内にある企業の「ファーストオン」の共同開発だそうです。私が話を聞いたのは、ファーストオンの代表である黒島保氏。企画立案からプロモーションまでに携わる立場だそうです。
まず、粗挽きの島こしょうをペッパーミル容器に収めた商品は過去にもあったのかと尋ねると、過去には存在しなかったらしい。発売は2023年の秋といい、すでにリピート購入が多く、一般消費者だけでなく、島外のフレンチや中国料理といった料理人からの定期購入、さらには酒造会社からの注文も舞い込んでいるそう。「使うたびに挽く」という、石垣島の島こしょうとしてはまさに新しかった提案が功を奏したというわけですね。
「もちろん、そうした提案が成功したという側面はあります」と黒島氏は話します。安全に保存が利くように、乾燥までの工程を100回近く見直したとも言いますから、開発は思いの外大変だったようですが、その苦労が報われたとも言えるでしょう。
ただ、話を聞き進めると、この商品を開発した背景にあるのは、もう少し複雑な要因があったとも言います。それは10年前にさかのぼるもののようです。石垣市は地元の特産品である島こしょうの普及促進に10年前から取り組んできました。でも、なかなかうまく事が運ばない。それはそうかもしれないと私も思います。特産品の販売増強というのは、どの地域も頭を悩ませる課題であり、単純なプロモーション施策では効果が得られにくいのが常とも言えます。
石垣市はここで思い切った策に出ます。島で暮らす人々にピパーツの苗を無償で提供して栽培してもらおうとしたのでした。ここが第一の共創ですね。一般島民をまさに巻き込む形をとった。
しかしながら、ピパーツの栽培が広まっても、出口がきちんと存在しないとその施策は成果を挙げられません。
まさに踏み込んだ姿勢で
この局面で黒島氏が動いたそうです。島民が育てたピパーツの実を買い取ると宣言しました。買取価格は1kg当たり1500円(税込み)とも伝えます。そうすれば、島の人たちもがぜん、やる気を出してくれますね。
しかしながら、ここで重要となってくる話があります。島の人が持ち寄ってくれるピパーツの実を黒島氏が全量買い取るとするならば、それをちゃんとさばき、さらにはそもそもの狙いである特産品・島こしょうの存在を光らせるための商品開発が必須となります。「買い取りますよ」と宣言したからには、もう後がない。
独自性をたたえ、プロの料理人をも振り向かせた、がりがり粗挽きピパーツが完成するまでには、そうした必死の取り組みがあったということです。私自身、商品を手にした時点では、そこまでの背景があったとは知りませんでしたが、こうした経緯を聞いて納得しました。そこに必然性があり、また、懸命な思いで作り上げた商品には、相応の訴求力がおのずと伴ってくるという話であると思います。
これこそ、まさに文字通りの共創事例ですね。汗をかいた人が答えを導けたのですから。
石垣市はこの冬、島内の全ての小学校にピパーツの苗を無償提供することを決めたそうです。児童が育てたピパーツの実を黒島氏たちが買い取れば、部活動などの費用を小学校は得ることができます。また新しい共創が始まりそうです。

製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門領域とする一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画する。
日本経済新聞社やANAとの協業のほか、経済産業省や特許庁などの委員を歴任。サイバー大学IT総合学部教授(商品企画論)、秋田大学客員教授。