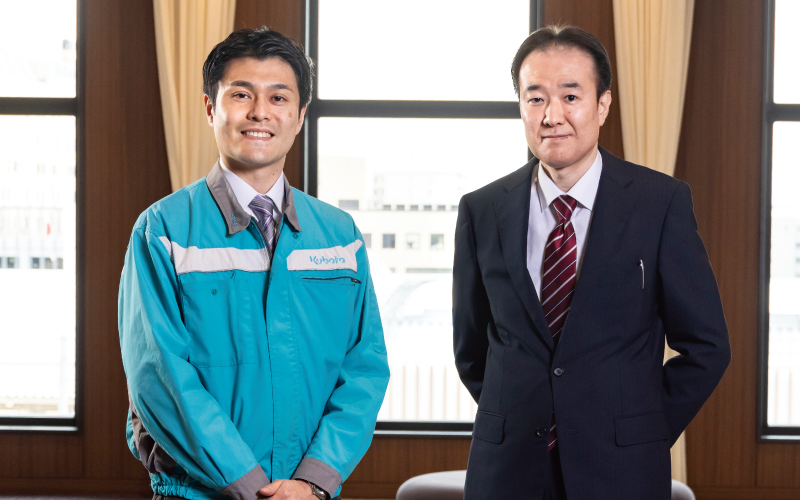ウェブからの問い合わせは24年間で累計1万件を超える。京都の中小企業が共同で立ち上げたプラットフォームは、新たな顧客の創造と未来事業の探索の場となっている。

風車事業を手掛けるパンタレイと開発した「ポータブル風力発電機」の試作機。開発したい製品イメージの立案から、工程・仕様の整理、機構設計、部品・組立図の設計、試作機の組み立てまでトータルでサポート
インターネットを活用した顧客創造の仕組みを構築
京都府の中小企業が集まり設立された京都試作ネットは、「顧客の思いを素早く形に変える」をコンセプトに掲げ、2001年に試作に特化したECサイトを開設。企業が抱える課題に向き合い、開発試作を通して多くのソリューションを提供してきた。これまでに寄せられた問い合わせは累計1万件以上。大手企業から官庁関係、スタートアップまで幅広い層に顧客が広がっている。
大手通販サイトAmazonが国内で書籍販売をスタートさせたのは2000年11月。ECモールのオープンは2001年に入ってからだった。BtoCの大手企業がECサイトを開設し始めたばかりの黎明期に、BtoBの中小企業が集まりECサイトを開設したのが試作ネットである、ということだ。これについて、京都試作ネット5代目の現代表理事を務める佐々木智一氏は次のように語る。
「2001年にウェブサイトを立ち上げて集客を始めたこと。これは、京都試作ネットにとって最初のチャレンジであり、最大のチャレンジだったと今も思います。一般消費者でさえ、ECサイトで商品を購入することに抵抗があった時代に、モノを売るためではなく、顧客からの問い合わせを獲得するECサイトを立ち上げました。特に、BtoBの会社に絞るとパイオニア的な存在だったと自負しています。京都試作ネットだからこそできたチャレンジだったと思いますし、そうしたチャレンジを常に大事にしています」
佐々木氏は、金属表面処理薬品の開発を得意とする佐々木化学薬品の代表取締役でもある。当初、機械金属関連の中小企業10社からスタートした京都試作ネットは、現在38社が参加。当初の中心だった金属系企業に加えて、今では装置・電気系やマイコン制御・ソフト、樹脂、ゴム、熱電素子、UI(ユーザーインターフェース)といった幅広い分野の企業がメンバーに名を連ねる。
事業についても、部品の加工試作だけでなく、全体のシステムや機構の開発試作、さらにスタートアップ企業のアイデアを形にする「協創試作」へと拡大しており、ものづくりから社会課題の解決に向けた価値創造の支援へと活躍の場が広がっている。
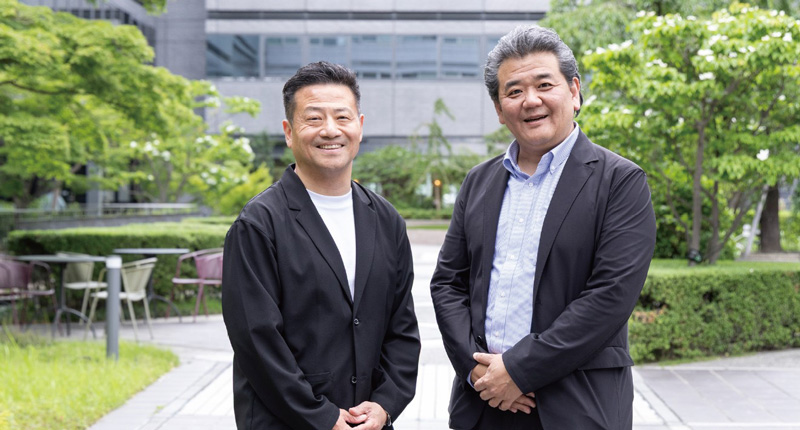
京都試作ネット 現代表理事 佐々木化学薬品 代表取締役社長 佐々木 智一氏(左)、京都試作ネット 現常任理事 菅原精機 代表取締役社長 菅原 尚也氏(右)
顧客創造を目指すなら「ボール球に飛びつけ」
社会の変化を敏感に読み取り、新しいフィールドに果敢にチャレンジする。京都試作ネットが24年間、顧客を創造し続ける理由について、菅原精機の代表取締役社長である菅原尚也氏は次のように語る。
「京都試作ネットには、『ボール球に飛びつけ』という言葉があります。ストライクゾーンとは既存事業のこと。ボール球とは既存事業から少し外れている案件を指します。ボール球に手を出すからこそ、各社の技術や対応力が上がりますし、京都試作ネットの目的でもある未来事業の探索につながります。未知のニーズこそ、私たちにとって最も有益な情報なのです」
当然、ボール球のほとんどはメンバー企業にとって経験したことのない案件であり、すぐに売り上げや利益につながるわけではない。しかし、そうした依頼に対応することで、顧客が何をつくろうとしているのか、求める品質や技術、さらには次にどういった分野に進出しようとしているのかが見えてくる。
それが未来事業の探索につながり、メンバー各社が今後どのような事業を強化すべきかを考えるヒントになる。多様な技術・ノウハウを持つ企業が集まる京都試作ネットだからこそ、幅広い案件が寄せられ、多くの情報が集まってくるのだ。
そうした文化が醸成された背景には、設立当初から抱える環境変化に対する強い危機感がある。
京都試作ネットの原点は、1993年に京都機械金属中小企業青年連合会の有志によって始まったピーター・F・ドラッカーの勉強会にさかのぼる。ちょうど日本の大手製造業が人件費の安い中国や東南アジアに生産拠点を移転していた時期であり、国内の産業空洞化が叫ばれていた。
それまで中小製造業が担ってきた大量生産の下請け仕事が急速に喪失していく中、新たなマーケットとして着目したのが国内に残された開発機能だった。それぞれの強みを持ち寄って、一品ものや少量生産の試作に特化したソリューションネットワークとして活動がスタート。価格競争力ではなく、スピード重視の「2時間レスポンス」(問い合わせに対して2時間以内に連絡、見積もりを返すルール)を掲げて新規顧客の開拓に励んだ。
それが見事に当たり、ECの浸透や展示会を通して知名度が上がると大手企業の開発部門からの依頼がくるようになり、2015年ごろには年間1000件を超える案件が寄せられるようになった。ドラッカーが企業の第一目的として挙げる「顧客の創造」につながる仕組みが完成したのだ。
予期せぬ顧客との出会いがイノベーションを生む
大手企業の図面から一品ものの試作を手掛ける事業モデルを確立する一方、京都試作ネットは、10年ほど前から事業領域の拡大を図ってきた。特に、近年は社会課題の解決に向けたテーマや、ハードウエア系スタートアップ企業に対する支援が増加。試作の枠を大きく超え、事業構想パートナーとして存在感を高めている。
「スタートアップ企業は素晴らしいアイデアを持っている一方、そのアイデアを形にするノウハウが十分とは言えません。一方、私たちはものづくりに精通した集団ですから、試作だけでなく、量産化に耐え得る品質や生産体制を構築するアドバイスや支援が可能です」(佐々木氏)
スタートアップ企業の成長段階には、必ず「死の谷」(製品開発から事業化への移行段階で発生する、事業を失敗に導く可能性の高い段階)が存在する。
ハードウエア系スタートアップの場合、その多くは資金調達用試作から量産化に移る段階に訪れる。
資金調達用に数個の試作品をつくるのと、量産化では難度が格段に違うからだ。その点、京都試作ネットのメンバー企業には大手製造業の下請けを経験し、大量生産に必要な部品調達や品質管理、工程管理などにたけたところが多い。そうしたノウハウを活用して量産化試作を支援する機会が増えている。
さらに、支援するスタートアップ企業が資金調達する際も、京都試作ネットが一役買った例もある。
「私たちが支援するスタートアップ企業への投資を検討するベンチャーキャピタル(以降、VC)2社に対して、工場見学の受け入れも含めて技術面や量産化についてご説明したところ、2社から投資を受けることができました」(佐々木氏)
京都試作ネットと協業することは、スタートアップ企業にとって量産化試作に加え、VC対応にも大きなメリットが生まれる。またVC側からすれば、京都試作ネットと協業することによってスタートアップ企業に対する評価や投資がしやすくなる。こうしたメリットが認知されていけば、京都試作ネットにとって「顧客の創造につながる新たなモデルになる」と佐々木氏は期待する。
世の中にない製品を生み出すスタートアップ企業の案件は、間違いなく「ボール球」だ。そして、VC対応も中小製造業にとって経験したことがないボール球。だが、あえてそこに手を出すことで新たな展開が見えてくる。その境界に、京都試作ネットは立っている。
一番大事なことは「社長自ら汗をかくこと」
2024年1月、京都試作ネットは米・ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES2024」に初出展した。展示されたのは、有志メンバーが共同開発した「廃熱発電システム」のコンセプトモデル(機能試作)だ。

京都試作ネットが「CES2024」に出展した「廃熱発電システム」。京都試作ネットに所属する各企業が持つ技術を分かりやすく表す製品を通して、来場者に日本の技術力をPRした
「廃熱発電システムは、工場の廃熱を電気に変えて再利用する装置です。ただ、装置の販売が目的ではありません。私たちが持つ技術を分かりやすく示すアドバルーン的な製品を通して、各企業が持つ技術やコンセプトを見える形に変えたのです。このコンセプトモデルを通して、今後は顧客の技術やノウハウを分かりやすい形に見える化する提案をしていきたいと考えています」(佐々木氏)
これまで京都試作ネットは、寄せられるニーズを試作という形に変えてきた。開発者の期待を超える試作品をどこよりも早く提供する。これが事業の定義だったが、今回のコンセプトモデルはシーズ起点の開発であり、その定義からは外れている。
「これまでの文化とは異なりますが、あえて挑戦しました。なぜなら、時代が変わっているからです」と佐々木氏は言う。設立以来、図面からの試作が事業の中心だったが、同様のサービスを提供するAIプラットフォームの登場によってマーケットが大きく変わろうとしている。その変化の波を乗り切るには、「経営者自らが汗をかく」ことだと佐々木氏は指摘する。
「私が代表理事を引き継いでから、京都試作ネットの問い合わせ窓口を設立当初と同じ社長対応に戻しました。ボール球に挑戦する決断ができるのは社長だけ。今は38名の社長が5グループに分かれ、日替わりで問い合わせに対応しています」(佐々木氏)
社長自ら未知の領域や予期せぬ顧客と接点を持つこと。1社ではできないチャレンジ(実験)ができること。そこに京都試作ネットが進化を続ける秘密があり、大事にしている約束だ。
失われた30年の間に低下した国内製造業の競争力を再び取り戻せるか――。「日本の製造業が進化した1つのモデルを京都試作ネットが示せるよう、これからも挑戦を続けていきます」(佐々木氏)
(一社) 京都試作ネット
- 所在地 : 京都府京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク2号館2F
- 創設 : 2001年
- 代表者 : 現代表理事(5代目、任期2021年7月~2026年6月)
佐々木 智一(佐々木化学薬品 代表取締役社長)