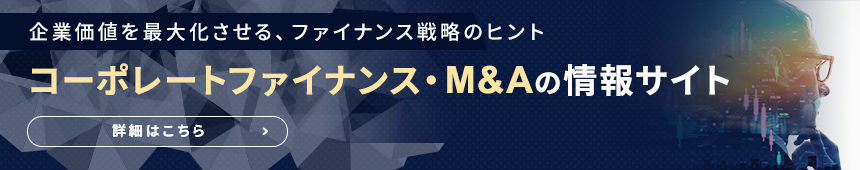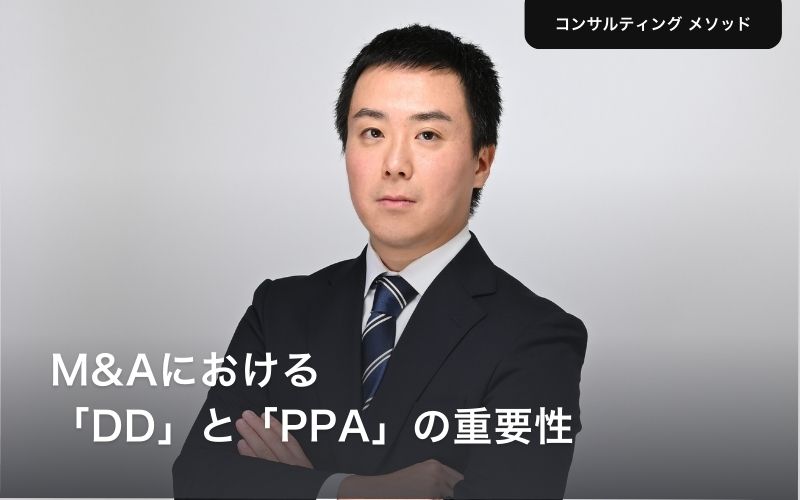PMIの流れ
TCG(タナベコンサルティンググループ)では、M&Aの交渉だけでなく、戦略構築などの検討段階から買収後の統合プロセスまで一貫して支援する「PMI(経営統合)コンサルティング」を提供している。
「M&A成功の鍵はPMI」と言われるように、M&Aによるシナジーを生み出せるかどうかは、PMIの質に依存している。今回は、PMIの進め方と成功ポイントについて解説する。
買収後に企業文化を擦り合わせる統合作業をPMI(Post Merger Integration)という。PMIを進める上で最も重要なのは、自社の現状を認識することである。TCGでは、この現状認識を行うためにチェックリストを整備し、クライアントの状況を分析することから始める。
PMIコンサルティングの流れは、PMIプロジェクト体制の確立、PMIの実行、モニタリングの3フェーズから構成される(【図表】)。支援期間は約10カ月を想定している。
【図表】タナベコンサルティンググループのPMIコンサルティング

出所 :タナベコンサルティング戦略総合研究所作成
フェーズⅠ:PMIプロジェクト体制の確立(所要期間1カ月)
まずは、PMI推進チームを組成する。PMIは単独で進めるのではなく、各関係部門を含めたチームで進める。具体的には、事務局・意思決定機関を設置後、プロジェクトメンバーを選定する。
次に、現状認識としてM&A検討時に実施したDD(デューデリジェンス:買収監査)で指摘された項目を分析する。事業分析では、SWOT分析※1などを行い、企業の内部環境(強み・弱み)、外部環境(機会・脅威)を整理し、業界内のポジショニングを把握する。組織分析では、人事処遇制度、意思決定構造(会議システム)などの分析を行う。収益財務分析では、会計ルール・日常業務内容を分析する。
現状認識を踏まえ、買収スキームを基にした統合方針(ビジョン)の策定を行う。具体的には、統合ビジョンの策定後に、統合手順、統合スケジュールの策定、重点項目の絞り込みなどが挙げられる。
PMIの準備は、M&Aの最終契約締結後から始まる。つまり、M&Aのクロージング(成約)までにPMIプロジェクト体制(フェーズⅠ)を確立することが重要である。
フェーズⅡ:PMIの実行(所要期間3カ月)
PMIの実行段階では、長期的に実施していく内容(経営のPMI)と、短期的に実施していく内容(業務のPMI)に分けて行う。
経営のPMIは、中長期ビジョンの構築が重要である。中長期ビジョンを設定し、定性・定量のビジョンを明確にした上で、セグメント・エリア・商品別に既存事業の強化策を検討するなどの事業戦略を設計する。
また、全社・事業別の販売計画の策定や、新規事業についても併せて検討する必要がある。収益・財務戦略の設計においては、全社・事業別の収益構造を設計し、中期財務計画を策定する。
次に、資金調達方法を含む投資計画を策定し、中期KGI(重要目標達成指標)・KPI(重要業績評価指標)を設定する。組織・人材戦略の設計では、組織・マネジメント体制の設計が重要である。併せて、売り手企業を経営する経営者の育成プランの設計や、人事・賃金制度の統合プロセスの設計にも注力していただきたい。
業務のPMIは、業務の引き継ぎを重視する。売り手企業との信頼関係を構築し、クロージング後には従業員への公表、面談を実施する。また、社内のキーパーソンと面談し、クライアントに向けてメッセージを発信することも重要である。
次に、コーポレート部門の統合や経理処理、決裁プロセスを中心とした統合作業を実施する。管理会計ルール(経営会議資料)や、文書管理体制の統一も行う。さらに、KPIの設計と管理方法を支援し、決算手続きについてもサポートする。
統合に関わる内容については、公開するメンバーを限定した上で、適宜、進捗報告を行うことが重要である。特に、組織や人材に関わる部分は時間がかかるため、慎重に進めていただきたい。
フェーズⅢ:モニタリング(所要期間6カ月)
PMIの全体像が固まり次第、テスト運用を開始する。具体的には、中長期計画で設定した項目の実施と、日常業務が支障なく行われているかをチェックする。
まずは、事業アクションプランを設計、実施する。年度別KPI達成に向けた事業戦略の具体策を考え、プロダクト・サービス別にプロモーションミックス※2を設計し、シナジーを生み出すための対策を実施する。
次に、収益・財務戦略アクションプランを設定する。併せて、業務PMIの進捗確認やブラッシュアップを行う。また、業績進捗確認後には経営会議に参加し、PMIノウハウの文書化を支援する。
最後に、組織人材アクションプランを実施する。人的資源(HR)領域の制度充実に向けた具体策(人事制度・賃金制度の見直し、労務関連規定の整備など)の検討などである。
継続的なモニタリング報告により、統合状況の進捗とシナジー効果が図れているかを確認する。
自社独自の型を持つ
PMIを成功させた企業に共通しているのは、「自社独自のPMIの型を持っていること」である。独自のPMIの型を定め、エクゼキューション(M&Aにおける一連の事務手続き)の最中からその型に合わせて譲渡企業側の現状認識を行い、PMIに入るときの論点や課題を見極めることで、シナジーの創出が難しいと判断すれば、M&Aの取引自体を中止する判断が可能となる。
また、M&A実施後の対象企業でのオペレーション体制の構築も重要である。譲渡企業の内情をよく知るためには、譲渡企業に常駐する人材が必要である。経営者人材であり、かつ現場レベルで業務を把握できる担当者を早期に送り込むことが重要である。
M&Aは、譲渡を完了して終わりではない。重要なのは、M&A実行前に検討したM&A戦略に従ってシナジー効果を生み出すことができるかである。最適なPMIを実施することで、M&Aの効果を最大限に引き出していただきたい。
※1 自社の社内リソースと自社を取り巻く外部要因を照らし合わせて分析し、今後挑戦できる市場領域や解決すべき事業課題を見つける手法
※2 企業が製品やサービスを市場に効果的に伝えるために使用する、さまざまなプロモーション手段や戦略の組み合わせ

金融業界にて法人・個人営業を経験し、税理士事務所にてM&Aを担当後、タナベコンサルティング入社。後継者不在企業において、M&Aニーズのヒアリングから、書類作成、ソーシング活動まで事業承継M&Aに従事している。顧客に寄り添い、顧客の要望を丁寧にヒアリングしていくコンサルティングスタイルに定評がある。