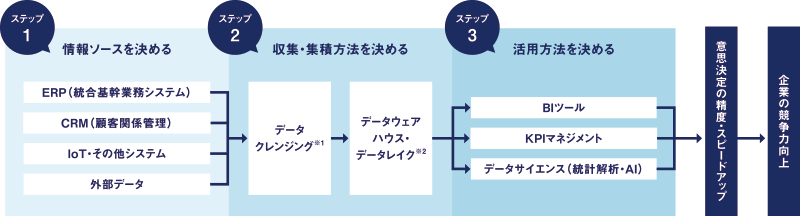企業経営における意思決定の精度とスピードを上げるためには、BI(ビジネス・インテリジェンス)ツールが必須の打ち手となる。BIツールとは、企業が持つさまざまなデータを分析・可視化し、経営判断や業務に役立てるソフトウエアである。
昨今のビジネスシーンでは、BIツールは経営判断を行う経営層だけでなく、さまざまな部門で活用されている。例えば、経営企画部門では財務・予実分析、営業部門では売上分析、マーケティング部門では顧客・販売時期・エリア分析、人事部門ではタレントマネジメントなどである。
日本において、BIツールは1990年代から普及を始めた。2000年前後のERP(統合基幹業務システム)登場をきっかけに、複数のシステムからのデータ取得が容易になり、BIツールの有効性に対する理解は広まった。
だが、データ収集・活用に悩む企業にとって、BIツールは有効な手段として理解されたものの、「データサイエンティスト」「データアナリスト」と呼ばれる専門スキルを持った人材が必要と考えられていたため、コスト・人材不足の観点からBIツールを導入する企業は増えなかった。
2015年ごろには、セールスフォースの「Tableau(タブロー)」、マイクロソフトの「Power BI」をはじめとする、エクセルを基礎とした「セルフサービスBI」(専門知識を持たないユーザーでも分析やレポート作成ができるBIツール)が登場。個人でもBIツールを簡単に利用できる環境が整ったが、デジタルリテラシー不足で広がりを見せなかった。
デジタル化への転換を早めたコロナ禍の現代においても、BIツールを導入している企業は少ない。導入が進まない理由として、企業のDXが進んでいないことが挙げられる。慢性的にデジタル人材が不足しており、DXと言っても目先の業務効率改善が中心で、データの利活用まで進んでいない企業がほとんどである。
企業でBIツールの導入を進めるに当たり、まずはBIツールの種類を理解いただきたい。BIツールには大きく、「エンタープライズBI」と、前述したセルフサービスBIの2種類がある。
エンタープライズBIは、データ活用時代の先駆けとして2000年ごろから普及した従来型のBIツールである。専門スキルを持った人材を主担当に置き、ガバナンスや運用体制の整備で収集データの信頼性や整合性を高めるメリットはあるものの、データの知識がない社員にはほとんど利用できないというデメリットがある。
セルフサービスBIは、専門スキルを持たない人材でも簡単に操作できることを目指して開発されたBIツールである。誰でも扱える半面、ユーザー自身がデータソースを自由に操作できるため、データの信頼性や整合性が低くなる可能性がある。それぞれのメリットを生かし、ハイブリッドで活用することが重要だ。
BIツール導入の本質は、「自社の競争力を高めること」にある。既存のデータを使って継続的に日常業務を確認するといった取り組みにとどまるのではなく、「データドリブンな組織」への変革を目指していただきたい。
データドリブンとは、収集・分析したデータを基に、経営における意思決定や課題解決の施策立案を行う全体的なプロセスを指す。データドリブンな組織をつくるためのBIツール導入に当たり、ポイントを2つ紹介する。
❶データドリブン型プラットフォームの構築
まず、自社で保有するデータと併せて、統計情報など外部のオープンデータも含めた情報ソースを決める。次に、データの収集・集積方法を決める。最後に、人にしかできない「知見・分析判断軸」と、AIが行う「機械学習による分析判断軸」を掛け合わせ、経営判断の精度とスピードを上げる。(【図表】)
【図表】データドリブン型プラットフォーム構築のステップ
❷必要スキルの会得
セルフサービスBIを使うことで簡単なデータ分析はできるが、本格的に活用するにはある程度のスキルが求められる。主なスキルとして、①抱えている業務課題や潜在課題を基に要件定義を行う「業務スキル」、②不要・欠損データの精査やマスターデータを管理する「データ管理スキル」、③複数のシステムからデータを取り込みデータベースを設計・開発する「データハンドリングスキル」、④必要な分析項目を視認・操作性を考慮しながらUI(ユーザーインターフェース)に落とし込む「画面デザインスキル」、⑤モニタリングすべきKPI(重要業績評価指標)の設定、実績値の測定と目標値の設定やPDCAを運用する「KPIマネジメントスキル」、⑥自社課題を基に仮説を立て、統計解析やAI(機械学習、深層学習など)を駆使して将来予測・分類・最適化を行う「データサイエンススキル」の6つがある。
組織でBIツールによるデータ分析・活用を浸透させるに当たって、現場で頻発する問題事例を紹介する。データ分析担当者が、「A層への訪問回数を10%増やせば受注が30%増える」という分析結果を現場マネジャーに見せた際、「当たり前の分析結果だ」「すでに取り組んでいる」と反論されることがよくある。
このような場合、現場では「一部のハイパフォーマーしか課題を認識していない」「課題を数字で把握できていない」ということが多い。関わるメンバーに分析データを共有し、ハイパフォーマー以外にもデータ活用によるメリットを理解してもらい、全員が「できる」「している」状態にすることが重要である。
また、新しい分析結果ばかり追うことは、ビジネスにおいて非効率だ。普段意識しない“当たり前”な分析結果を再度見直し、現場の行動変化を起こすことを優先すべきである。
BIツールを使って自社でイノベーションを起こすことはできるだろう。だが、BIツールを自社の経営課題の解決につなげるためには、前述した組織づくりとスキルが求められる。自社が足踏みしている間にも、競合他社はデータドリブンな組織づくりを進めているかもしれない。
自社でBIツールをすぐ導入できない場合は、デジタルパートナーを活用するKPO(ナレッジ・プロセス・アウトソーシング:情報分析などの知的業務の外注)という手段もある。
自社に適したBIツールやKPOを知るためにも、まずは自社の課題を把握し、BIツールの導入で意思決定の精度とスピードを上げ、企業競争力を高めていただきたい。