経営戦略を軸に人材ポートフォリオを再定義する。ポストコロナ時代の人事制度とは:川島 克也
「生産性」という視点で分析し直し、改革・改善を進めることが必要
コロナショックは、企業の雇用や人事に対して大きなインパクトを与えており、実際、2020年4月7日の緊急事態宣言発出後には「テレワーク」などのニューノーマル(新常態)な働き方が広まっている。
日本生産性本部の調査データ※1によると、「コロナ禍収束後もテレワークを行いたいか」との質問への回答は、「そう思う」が27.9%、「どちらかといえばそう思う」が47.7%で、前向きな回答が75.6%に上った。
内閣府の調査※2でも、東京23区では調査対象者のうち55.5%がテレワークを経験、このうち約9割が継続したいと回答している。これは、テレワークによって、これまで当たり前だった満員電車での通勤がなくなったり、少なくなったりして、快適な生活を体験したことが大きな要因になっているといわれている。
しかしながら、5月25日に緊急事態宣言が全国的に解除された後は、テレワークが継続されていないのが実情である。日立製作所や富士通など一部の大手企業では、在宅勤務を恒常的な仕組みとして導入しようと取り組んでいるが、まだまだ少数派だ。
第2波がピークに達した7~8月においても、日本では従業員がオフィスへ復帰する姿が目立った。これは、テレワークが運用できるインフラが十分に整っていない企業や、そもそもテレワークに向かない業種の企業が多いこと、また、職務の定義の曖昧さや、評価制度などの人事制度が未整備な状況、テレワークに対して否定的な組織風土といった日本的な雇用環境が背景にあると思われる。その結果、テレワークを継続したいという従業員のニーズに応えきれていない「ミスマッチ」な状況が生じている。
さらに、日本企業の時間当たり労働生産性は、米国の6割強の水準にとどまり、OECD(経済協力開発機構)加盟36カ国中21位。主要先進7カ国の中では最下位の状況が続いている。(【図表1】)
【図表1】OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性(2018年/36カ国比較)
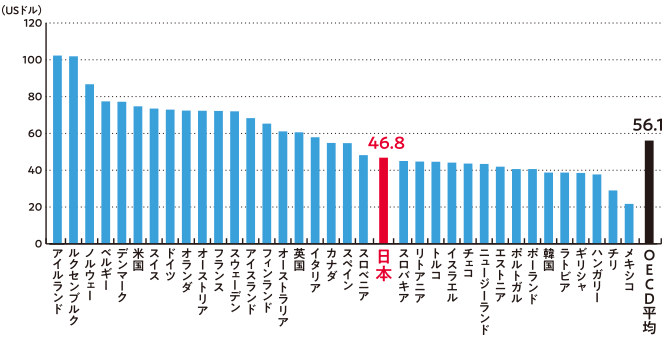
単位:購買力平価換算USドル
出所:日本生産性本部「労働生産性の国際比較2019」
前述の通り、日本企業は労働集約的でテレワークに向かない業種も多く、中小企業の割合が多い産業構造であることや、「サービス無料」の風土が醸成されていることなども、生産性が上がりづらい要因である。
しかしながら、必ず出社して、狭い職場空間の中で仕事をしなければならないのか。全ての商談・打ち合わせを顧客企業へ訪問して行わなければならないのか。こうした現状を「生産性」という視点から厳しく見つめ直し、改革・改善を進めることが必要である。
ここで、電力関連製品を製造している中堅メーカーA社の事例を紹介したい。A社では、コロナ禍に対応してテレワークを推進したが、モノづくりの業態であるため、工場の従業員はシフト勤務までで、テレワークを完全に導入できたのは管理職と営業職だけだった。
A社社長に「テレワーク導入によって、業務や生産性に影響は出ていますか?」と質問すると、次のような回答があった。
「不思議なもので、営業担当者が顧客企業へ訪問しなくてもまったく業績に影響がないんですよ。また、管理職が目の前にいなくても、大きなトラブルもなく仕事が回っているようだし、逆に、管理職からの突発的な指示もなくなって、仕事に集中できているようなんですよね。今回のテレワーク導入が、営業の仕事を見直し、管理職の本来の役割とは何かを考えるきっかけになりました」
今回テレワークやシフトワークを導入した企業の方々には、共感する部分も多い話なのではないだろうか。
そうした中、A社は「所管組織の方針・目標の実現に向けて、生産性の最大化を図る」という管理職本来の役割、「顧客ニーズと自社製品のマッチングを図り業績を上げる」という営業職本来の役割から鑑み、主体業務(=本来の役割・付加価値を上げるための業務)に集中できる業務改善を通した生産性向上に取り組んでいる。
※1…日本生産性本部「第2回 働く人の意識に関する調査」(2020年7月21日)
※2…内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」(2020年6月21日)
日本では今後35年間で、約30%の労働力が失われていく
コロナショックは、短期的にテレワーク導入などの「働き方の変化」を迫っているが、そもそも企業経営においては、長期的な環境変化・トレンドへの対応が必要である。
周知の通り、日本の人口は減少傾向にある。現在の日本の人口は約1億2596万人であるが、2030年には約1億1912万人、2055年には約9744万人となる見込みである。また、生産年齢人口(15~64歳人口)は現在約7481万人だが、2055年には約5027万人となることから、今後35年間で約30%の労働力が失われていくことになる(【図表2】)。このことからも、産業構造を変えていかなければ日本経済は縮小傾向に陥っていくことが避けられない。むろん、企業においても「労働力の確保」と「人時生産性向上」は重要課題である。
【図表2】将来の人口予測(2055年)
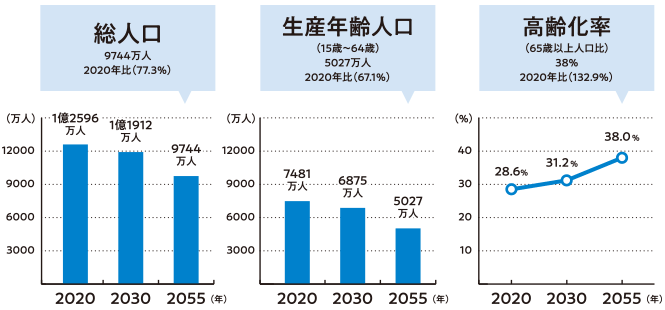
出所:2020年は総務省統計局「人口推計(2020年3月確定値、2020年8月概算値)」(2020年8月20日公表)、他は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」数値を基にタナベ経営が作成
こうした状況下、企業においては、人的生産性指標に基づいた改革への取り組みが必要になる。人的生産性の代表的な指標は「労働分配率」である。労働分配率とは、企業活動において産出された付加価値・限界利益をどれだけ人件費に配分しているのかという指標である。(【図表3】)
【図表3】労働分配率
(限界利益に占める人件費の割合)
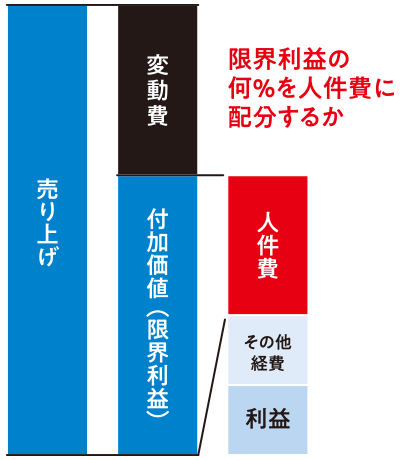
現在の日本企業全体の労働分配率は平均60%程度といわれているが、重要なのは、自社にとって適正な「労働分配率」が設定され、常にその適正労働分配率に収まるようにコントロールができているかである。
平均60%といっても、実際には業種・業態によって基準となる労働分配率は変わるので、適正労働分配率は会社ごとに設定することになる。業界平均、競合比較、自社の収益構造、今後の中期経営計画などを踏まえて、適正労働分配率を設定していただきたい。
従来、「人件費コントロール」を画一的に行っていた企業が多かったと思われる。例えば、業績が悪ければ社員の賞与を一律10%カットする、反対に業績が良ければ一律10%アップするということだが、これでは、業績に対する貢献度が反映できず、貢献度の高い社員のモチベーションを上げることはできない。
現在は働き方改革が進み、多様な人材の活用、多様な働き方・貢献の仕方がスタンダードになっている。従来の画一的な発想を改め、自社の競争力の源泉となるコア業務とコア人材を明確にし、ここへ重点的に資源配分ができる人事へと転換する。こうした人件費コントロールこそ、今後の企業の競争力・生産性向上に必要なポイントになる。



