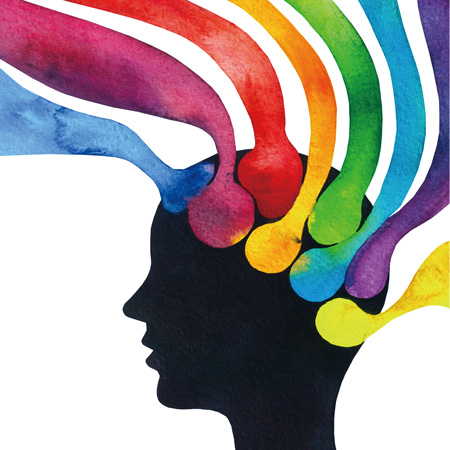
技術革新を味方に付けよ
AIに仕事を奪われる?堂々と奪ってしまえばいいのだ。
時代はその繰り返しであり、技術革新とともに経済は発展してきた。高度経済成長期に普及が進んだコンバインは、稲作にかかる稲刈りと脱穀の労働時間を19分の1に短縮させた※。まさに爆発的な生産性改革だ。裏を返せば、19人分の仕事を1人でできるようになり、18人分の仕事を技術革新が奪ったとも言える。
私のクライアントであるこんにゃくメーカーA社の例を挙げよう。日本で初めて板こんにゃくを自動で加工・切断する機器を製造した企業でもあるA社は、高い生産技術力でユニークな形のこんにゃくを製造し、その商品力の高さが同社の成長を引き上げていった。しかし、板こんにゃく加工自動化の裏側には次のような物語があった。
こんにゃく製造業は従来、労働集約型で、板こんにゃくは液状化されたものを木枠を使って固め、必要な形状に人の手でカットする流れが一般的であった。A社の製造工程も同様だったが、A社の経営者(創業者)の妻も工場で働き、夏は暑く、冬は寒い環境下で作業をしていた。まだ乳児である子どもを背負って。
A社の経営者はその姿を見て、「どうにか楽にしてあげたい」と思い、板こんにゃく製造自動機を開発した。従来よりも生産性を大幅に向上させたことは言うまでもない。
自動化や技術革新の裏側には、このような物語がいくつもある。決して、「雇用を奪おう」という気持ちで開発はしていないはずだ。
しかも、労働力不足の日本においては、さまざまな産業でAI化・自動化が進めば、働き方改革にも大きく寄与するだろう。
※クボタのホームページ「クボタプレス」(2017年8月31日号)より引用
先端技術でビジネスモデルを変える三つの着眼
さて、今回は先端技術を軸にしたビジネスモデルについて考えていただきたい。企業が先端技術を取り入れたビジネスモデルを組む目的として、次の三つが考えられる。それぞれ、説明していこう。
1.技術そのものを創り出す
まず、一番シンプルであるが一番難易度の高い、技術を創造する取り組みだ。特集1で紹介したキャディやMUJIN、IBUKI(O2グループ)がそれに当たる。キャディは、自動見積もり技術を創り出し、製造業の「調達」というプロセスにイノベーションを起こしている。MUJINはモーションプランニングAIを創り出し、ロボットメーカーではできなかった、ロボット市場における複数の「不」を解決することで急成長を遂げている。
また、山形県の老舗金型メーカーであるIBUKIはIoT・AIを活用し、射出成形の技術やノウハウをシステム化。2014年に製造業コンサルティングファーム、O2のグループ企業となって以降、ハード・ソフト・サービスを一体化させて新たな価値を創出している。
ただ、これらの企業は市場の「不」と向き合い、解決するための技術を創り出すという非常に難易度の高いことに取り組んでいる。他社が簡単にまねできることではなく、その道のりも険しいが、技術力のある企業はぜひ取り組んでいただきたい。
2.技術が巻き起こす市場の変化の周辺事業を狙う
中堅・中小企業が狙うべき市場はここだ。過去を振り返っても、市場拡大を引き起こすコアの部分よりも、その周辺事業を押さえた企業は大きく成長している。1800年代、ゴールドラッシュで金の採掘者が殺到した際に一番儲けた企業が、実は発掘作業に適した強く破れにくいジーンズを製造したリーバイ・ストラウス(リーバイス)だった話は有名だ。
また、ウェブ市場が拡大するとともに、アマゾンを代表とするEC(電子商取引)企業が増えたが、アマゾンの利益の源泉はEC事業より、それを支えるクラウド事業であることも有名である。
もう一つ、身近な例を挙げてみたい。スマートフォン(以降、スマホ)に関する技術が発展する中、周辺事業としてその変化を感じているのが「バッグ市場」だろう。最近、ビジネスパーソンがリュックサックを背負う姿が当たり前になってきた。ユーザー(消費者)の価値観が変わっているのももちろんだが、それよりも携帯電話がスマホに変わり、スマホを見る時間が格段に増えたことが要因と思われる。
私もそうだが、電車の発着時間の検索や新幹線の席の手配、ニュースアプリでの情報閲覧など、外出時にスマホを手に持っていることは非常に多い。バッグ片手に操作をしていると両手がふさがり、とっさの事態に対応できない。雨が降った日などは最悪だ。つまり、スマホという技術革新がライフスタイルや価値観などを大きく変え、変化が起きたことで、その周辺でまた新たな変化が起きているのだ。
まさに、「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざの通りである。技術が巻き起こす市場変化の周辺事業を考えていただきたい。
3.技術を取り入れてビジネスモデルを変える
AI、3Dプリンター、ドローン、IoT、VR/AR/MR、画像処理技術、協働ロボット、RPAなど、さまざまな技術が日進月歩で進んでいる。これらの先端技術は、「これまでできなかった」を否定し、「できる」道をつくり出していることが多い。
例えばAIだ。インターネットで物を購入する際に、「こちらもどうですか?」と自動で勧められた経験は誰しもあるのではないだろうか。「これとこれを買った人はこの商品を買うことが多い」といった個人情報を基に、AIが百人百様のレコメンドをしているのである。顧客それぞれへの最適な提案を人間が行うのは難しい。その意味でまさに、AIは「これまでできなかった」ことを実現しているのである。
また、MR(Mixed Reality:複合現実)をご存じだろうか。VRやARに近いが、仮想空間と現実空間をミックスし、仮想空間上のものについて、デバイスを使う複数の人から確認できるなど、現在ビジネス上に盛んに取り入れられている技術だ。
MRの中ではマイクロソフトの「HoloLens(ホロレンズ)」が有名であるが、このHoloLensがさまざまな業界の「できなかった」を「できる」に変え、ビジネスモデルそのものを変えている。ここでは建設業界の事例を紹介したい。
建設業は大幅な生産性向上が難しい業種である。扱うものが毎回違い、人にしかできない仕事が多いことが要因だ。こうした状況の中、ある地方の中堅建設会社B社は、HoloLensを取り入れて建設業そのものの仕事の進め方を変えようとしている。
建築物の仕様確認は、顧客とのギャップが起きることが多く、クレームや手直しの要因となることが多い。一方、B社はHoloLensで3Dデータを用いて本物さながらの状態をつくり、クライアントと確認をするなどの取り組みを行い、顧客価値を引き上げている。
繰り返しになるが、「できなかった」過去は捨ててほしい。「できる」手段は先端技術を軸にいくつもあり、意外と簡単に手に入る。自社のビジネスモデルの「どこ」に「どの技術」を導入すると、顧客価値を引き上げられるのか検討していただきたい。

問題解決の思考フローを変える「技術解決思考」とは
「先端技術はあくまでも手段でしょ?」と言われることがある。
確かにその通りではあるが、今後その考えでビジネスを進めていくのは危険だ。成長しているさまざまな先端技術企業の共通点は、「新たな技術を用いて、どの問題を解決するか」を常に考えていることである。
一般的に、日本のビジネスパーソンには「問題解決思考」が備わっており、「課題抽出⇒原因特定⇒対策考案」という流れで確実に問題解決できる素晴らしい能力を持っている。しかし、これからの環境下では、「対策手段⇒抱えている問題の選定⇒解決」といった思考フローが必要と思われる(ここではあえて「技術解決思考」と呼ぶ)。
思考の流れを変えるにはまず、「先端技術・デジタル技術がどのようなものか」「どこでどのように使われているか」を知る必要がある。技術の基礎知識と応用知識をもとに、「自社の課題解決にどう使えるか」「顧客満足度を高めるにはどこで使えるか」を考えることが成功への近道である。
技術解決思考では、一つの対策で複数の問題を解決できるといった特長がある。例えばユニクロは、RF-ID技術※を用いて複数の課題解決を実現し、小売業界にイノベーションを起こしている。具体的にはRF-IDチップを商品タグに埋め込むことで、①店舗の棚卸し作業時間の圧倒的短縮、②工場内在庫管理業務の自動化、③店舗のセルフレジ化という3点の課題解決を実現した。ボウリングの1番ピンを倒すがごとく、1投で複数の課題解決を実現しているのである。
「業界にイノベーションを起こす必要がある」「10年後を考えると今のビジネスモデルでは通用しない」と感じているのであれば、まずは最新の先端技術を学ぶべきではないだろうか。誰も答えを教えてはくれないが、不確実な未来で変化を待つのではなく、自ら考え、変化を起こす側に回っていただきたい。
タナベ経営では、尖端技術研究会という「新たな技術を研究する会」を開催している。そこでは、特定の技術に固執せず、今後の市場環境を変えるであろう技術を研究するため、企業視察・講演会という形で2カ月に一度、さまざまな企業を訪問している。また、その一環として、2018年、2019年にはシリコンバレーにも赴いた。今後は中国の深圳や、2021年に米国ラスベガスで行われるCES(世界最大級の電子機器見本市)への視察もカリキュラムに入れ、現地・現物で「最先端」を学ぶことを軸に取り組んでいる。ぜひご参加いただければ幸いである。
※ID情報を埋め込んだRFタグを使い、電磁界や電波などを用いた近距離の無線通信によって情報をやり取りする技術


