【図表】建設業就業者数の推移
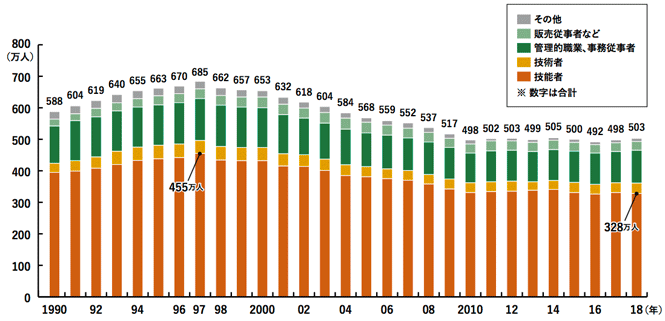
出典:総務省「労働力調査」(暦年平均)を基に国土交通省で算出
資料:国土交通省「公共工事の施工時期等の平準化に向けた取組について」(2019年7月19日)
深刻さを増す建設業の人材不足
2008年のリーマン・ショックを境に、建設業を取り巻く環境が変わった。10年余りが経過した現在、業界は本質的な課題に苦しんでいる。端的に言えば「人材不足」だ。
帝国データバンクの調査(「『人手不足倒産』の動向調査」、2019年4月)によると、2018年度に発生した人手不足倒産件数は169件(前年度比48.2%増)、このうち「建設業」が全体の3割超、最多の55件(同77.4%増)を占めた。
リーマン・ショック以前まで、浮き沈みはあるものの建設の需要と供給が一致し、専門工事会社は直接雇用ができていた。だが、リーマン以降は民間工事を中心に需要が減り、価格競争が激化。それに伴い、施工管理者や職人の賃金が下がり始め、「頑張っても報われない」という悲惨な状況に陥った。
国土交通省の資料(【図表】)によると、建設業の技能労働者数は1997年をピークに減り続け、2011~14年でいったん持ち直したものの、以降は緩やかな減少傾向となっている。1997年(455万人)から2018年(328万人)の21年間で、127万人の技能労働者が業界を去った計算になる。
東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた建設需要で労務費や資材費が上がり、働き方改革も相まって人材の待遇面に改善ムードが漂っている。だが、異業種へ転職して経験を積んだ人材は、そう簡単に戻ってこない。
では、この課題を解決するためには、どうすればよいのか。答えを出すのは業界団体ではない。企業自身である。キーワードは、「採用」と「育成」だ。
採用予定枠の人数を確保できなくても、新卒者を毎年採用できている会社はまだいい。問題は、採用せず、育てもせず、そのツケが10年後に回ってくる会社である。国交省の推計によると、60歳以上の建設技能者数は2015年で81.1万人と全体の約25%を占めており、10年後(2025年)にはその大半が引退するとみられている。一方、将来の建設業を支える29歳以下の建設技能者数は36.6万人(約10%)。人材不足は今後いっそう深刻になるということだ。
しかも、建設業は育成に時間がかかる。10年後を見据え、今このときから経営資源を投下していく必要がある。まずは、採用・育成戦略を本格的に見直さなければならない。採用しても早期に辞めてしまうことが多ければ、会社も人材も、互いに不幸である。
解決策は戦略的な採用と育成
(1)採用
一昔前は、建築もしくは土木の学科を修了していないと、技術者になれなかった。総合職採用であっても、あらかじめ技術系と事務系に分かれていた。「技術者になりたい」という熱意だけでは、どうにもならない現実があった。
しかし、今は違う。“地図に残る仕事”を夢見ている学生にとっては良い時代だ。建築・土木の知識ではなく、熱意重視で採用を進める企業も多くなってきたからだ。
実際、建設会社A社では、土木を学科で学んでいない入社2年目の社員が、条件付きではあるが現場代理人(工事の元請けの代表者)を務めている。入社2年目で現場に責任を持てるというのは幸せなことだ。責任は大きいが、技術者としての成長スピードが速まる。その分、早く仕事の醍だい醐ごみ味を味わうこともできる。
建設業にとって人材の育成は経営そのものだ。A社の社長は「人を採用し、育て、定着させ、そして活躍させることのできる会社が生き残る」という信念を持ち、実践しているのである。
まずは門戸を広く開き、熱意のある人材を採用することが、課題解決の第1ボタンと言えるだろう。
(2)育成
建設業の人材育成は難しい。構造上の課題を整理すると、
――という3点に集約できる。こうした課題に加え、「技は盗むもの」といった職人気質も加わり、人材育成はさらに難しくなる。
建設業B社の社長は、「施主や協力会社から学ぶというサイクルが崩壊し、誰からも学べない上、失敗も許されない。若い人たちがかわいそうだ」と嘆いていた。昨今、職人時代の育成システムは、もはや機能していないということである。
では、どうするか。まずは、社内で人材育成の重要性を認識するところから始めなければならない。せっかく門戸を広げて採用しても、多くが時を待たずに辞めてしまっては意味がない。
次に、「夢」や「仕事を通した成長」の舞台を用意する必要がある。私が若手社員の育成に必要不可欠だと考えるのは次の5要素だ。
①自社の“あるべき人材像”を描く
②あるべき人材像と現状のギャップを把握する
③業務を棚卸しし、若手に必要なスキルを整頓する
④教える側に“教え方”を教育する
⑤スキルの進捗状況など、運用のルールを作って実践する
人材育成は経営戦略と同じく、あるべき姿を設定し、その理想と現実のギャップを埋めていく活動だ。場当たり的な教育では意味がない。「採用→育成→定着→活躍」の善循環サイクルを回し、自社が理想とする人材を多く育てていただきたい。近い将来、必ず自社の大きな資産になる。
また、技術面だけでなく、仕事で関わる人たちへの接し方についても、育成カリキュラムに加えた方がよい。講師になるのは、経営幹部(もしくは社長)である。“人間力のある技術屋”が早期に育成されるだろう。



