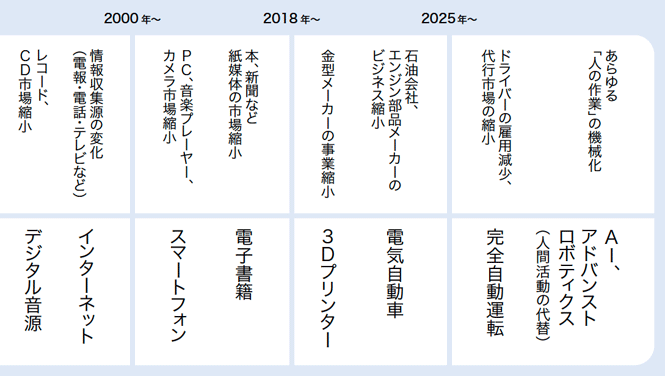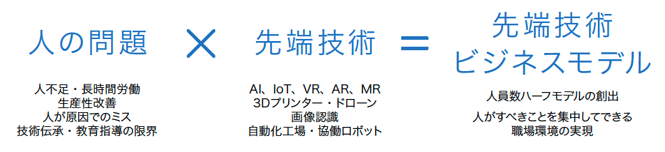先端技術の活用が人材不足の課題解決につながる ストラテジー&ドメインコンサルティング事業部
先端技術が巻き起こす創造的破壊イノベーション
先端技術はいつの時代も、創造的破壊イノベーションを起こしてきた。例えば、直近の例で言えばITが挙げられる。1990年以降のインターネットの進歩によって、EC(電子商取引)市場が拡大した。その半面、小売市場や卸売市場が縮小した。また、デジタル技術が発達してデジタルカメラが普及すると、銀塩カメラとフィルム市場が大幅に縮小した。そして、カメラ付き携帯電話が登場すると、デジタルカメラ市場が縮小してきた。
先端技術による創造的破壊は、これからも市場環境を大きく変化させていくだろう。すなわち、今後10年間に起こる技術革新は、これまでの常識が覆される変化を生み出すことになる。しかも、それはある日突然に訪れるのではなく、すでにいま起きていることが多い。
現に、量産対応可能な3Dプリンターが登場しており、複雑な形状の製品でも、金型を製作することなく大量生産できる時代となった。ある企業は、「金型で生産していた時は、仕様の発注を3カ月前までに行わねばならなかったが、3Dプリンターでの大量生産が可能となってからは、ギリギリまで設計の検討ができるようになった」とのことである。
先端技術を導入することで既存技術が置き換えられ、その結果、さまざまなメリットが生まれている。先端技術を導入する企業が増えるほど、導入に必要な費用の単価が下がり、普及スピードも加速する。初めのうちはスピードが緩やかでも、「クリティカルマス」(ある商品・サービスが一気に普及する分岐点=市場普及率16%)を突破すれば、爆発的に普及する。
技術の変遷を押さえることが成長戦略につながる
世界最大の産業である自動車産業がいま、100年に一度の変革期を迎えている。変革のポイントは「CASE」である。これはC(コネクテッド、つながる)、A(オートノマス、自動運転)、S(シェアリング、共有化)、E(エレクトリシティー、電動化)のそれぞれの頭文字を取った造語だ。
例えば、電気自動車の台頭により、内燃機関自動車の部品点数が4割減少するといわれている。従って、既存の延長線上の事業を続ける自動車部品メーカーでは、必然的に仕事を失う企業が出てくるだろう。
また、シェアリングの切り口で考えると、世界規模で急成長しているUber(ウーバー)が創造的破壊イノベーションを起こしている。Uberはスマートフォン(以降、スマホ)を用いた配車システムで、一般の人が自分の空き時間と自家用車を使って他人を運ぶ仕組みを構築。米国の都市部では、すでにイエローキャブ(タクシー)を見掛けることが少なくなるほど普及している。不足・不満・不安など、タクシーにまつわるさまざまな“不”を解決したからこそ、Uberのようなイノベーションが起きたわけだが、これはスマホをはじめとする技術なしには成し得なかっただろう。
とはいえ、こうした創造的破壊イノベーションの登場を、具体的に予測することは極めて難しい。人間は誰しも、未来を予言することはできない。だが、技術を中心にして市場が変化する以上、その変化はある程度、予想できる。今後10年、さまざまな技術革新が、これまでにないスピードで起こることが想定される。ほぼ確実に、市場の変化も伴うだろう。その変化は、既存のマーケットそのものを消滅させるかもしれない。
企業は「環境適応業」。環境に適応できない企業は淘汰される運命にある。この10年で起こり得る先端技術による大変革をよそ目に、成長戦略を組むことは難しい。従って、技術の変遷を押さえ、これまでに破壊された市場(事業)、今後縮小していくであろう市場(事業)を推測する必要がある。(【図表1】)
【図表1】破壊・縮小されていった(されていくであろう)市場・事業
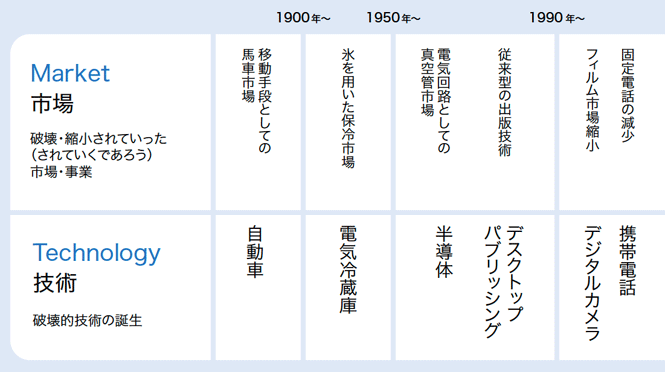
先端技術は人の仕事を奪うのか?
先端技術は“人の仕事を奪う”と誤解されがちである。確かに、「人にしかできない」と思われていた仕事が機械やシステムに置き換えられた事例は多い。例えば、米国の大手金融グループであるゴールドマン・サックスでは、2000年に600名在籍していたトレーダーが、現在2名だという。空いたポジションを埋めているのは、200人のコンピューターエンジニアによって運用されている「自動株取引プログラム」である。
また、ある製造企業は、品質管理における定型の品質チェック業務を全てセンサーによるデータ取得に置き換えた。毎日、複数人で行っていた仕事が無人で行えるようになったのである。
マヨネーズのトップメーカー・キユーピーも、近年は先端技術を用いて生産工場を進化させ続けている。その進化とは「品質検査工程のAIによる自動化」である。自然由来のものを原材料として使用する食品製造業では、調達する原材料の品質が製品の最終品質を左右することも多い。同社は従来、1日100万個以上流れるダイス型のポテトを一つ一つ、人の目で見分け、異物混入や不良品がないかを確認していた。
この品質確認の工程を、同社はAIが持つディープラーニング機能と画像認識機能によって自動化させた。2万個近い良品のダイスポテトの写真を10時間かけてAIに読み込ませ、品質チェック工程に取り入れたのである。結果、「良品ではないかもしれない」ダイスポテトは“異常”としてはじかれ、そのポテトを人の目でチェックするという工程に置き換えたところ、生産性は2倍になったという。
一見、人の仕事を奪ったように見えるが、裏を返せば、これまでの定型業務を機械やAIに任せることで、本当に人がすべき仕事に集中できる体制が整ったとも言える。すなわち、先端技術の本質は、“人のパフォーマンスを最大限に引き出すためのもの”なのである。
労働力不足を補うための先端技術
現在、国内企業が抱える長期的かつ深刻な課題は「労働力不足」である。2050年には生産年齢人口(15~64歳)が35%減少するといわれており、これまで100人でやっていた仕事を65人でこなさねばならない時代が必ず来る。従来、多くの企業では人の問題を人で補ってきたが、今後はそうもいかない。
私が今回、提言したいのは、「人の問題を技術で補う考え方へのシフト」である。ピンチをチャンスと考え、ライバルがまだ取り入れていない尖った先端技術を戦略的かつ積極的に取り入れる。労働力不足を技術でどのように補うか。これを前提としたビジネスモデルを描く必要がある。
日本のビジネスパーソンは得てして、発生している問題から出発し、その解決手段を考えるという手順を踏む。しかし、解決手段を考えてたどり着いた答えが“先端技術”ということでは、導入したところで遅すぎるのである。先端技術を単なる解決手段とは考えずに、「先端技術を前提としたビジネスモデルを描くこと」を検討してほしい。そうでなければ、激化しているグローバル競争を勝ち抜けないのだ。
「人員数ハーフモデル」を先端技術でデザインする
企業は、100人でやっていた仕事を50人でする「人員数ハーフモデル」をデザインすべきである。もちろん、これは“100人の社員を50人にリストラせよ”という意味ではない。50人分の仕事量を機械化やシステム化、AI化することによって、「人がすべき仕事に集中してできる環境づくり」に投資するということである。
これによって、現状の事業モデルや収益構造を大きく変化させ、競合に大きく差を付けられる高収益モデルを実現させることができるかもしれない。
AI、IoT、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)、3Dプリンター・スキャナー、ドローン、画像認識、協働ロボットなど、さまざまな先端技術の選択肢がある。どの技術も、基礎研究の段階はすでに卒業しており、応用研究の段階へと入っている。米国のベンチャー企業をはじめ、日本の老舗企業などにおいても、先端技術を商品・サービスに応用して、新たなビジネスモデルへと実用化する事業展開を推し進めている。どの技術を用いて、どのパートナーと組んでビジネスモデルを描くか。
人員数ハーフモデルを前提とした中で戦略を描いてほしい(【図表2】)。その先には、「働き方改革」や「1人当たり生産性の大幅改善」などが実現され、社員満足や社員の幸せを実現できるに違いない。