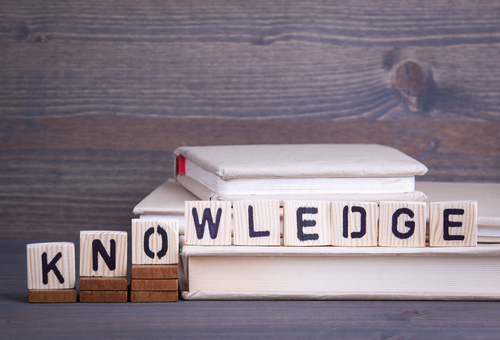Vol.118 なぜ新領域に挑むのか 北村 森

浅舞酒造
1917年創業。山々に囲まれた秋田県横手盆地は、四季を通じて朝夕の寒暖差がある米作りに適した土地。酒造りに使用する酒米の全量は横手盆地産
「飛び地」ではなく必然
今回はまず、大手企業の事例を少しお伝えしましょう。
岩谷産業といえばカセットコンロで知られる会社ですが、実はカセットコンロ事業の売上比率は数パーセント程度しかなく、主軸はガスの供給などを進めるBtoBの総合エネルギー事業です。
そんな同社ですが、2022年にマーケティング部を立ち上げて、BtoC領域での新商品開発に着手します。「自社の強みを生かす」をテーマに据えた新部署だと言いますが、2025年に話題の商品を世に送り出しています。
それは何かというと、コーヒー、豆の焙煎機なのです。商品名を「MY ROAST」といい、販売価格は5万5000円(税込み)です。
秋からの一般発売に先立ってクラウドファンディングを公開したところ、なんと4600万円を超える支援を獲得しています。これは異例と表現できるほどの大反響です。業務用ではなく一般消費者向けの焙煎機にもかかわらず、この支援額となった。
理由はいくつかあるでしょう。まず、本体が小さくて取り回しやすいこと。既存の焙煎機の約半額であること。また、焙煎機のトップブランドであるフジローヤルとの共同開発であり、コーヒー愛好家の心をつかんだこと。そして、カセットコンロを熱源とする(カセットコンロの上にしっかりと固定できる構造)であり、使うイメージを想起しやすく、また、身近に感じられる存在であることです。
開発担当者に聞いたら「岩谷産業が飛び地を攻めた」と、他社から驚きの声が上がっているそうです。「飛び地」というのは、企業がそれまでの得意領域を度外視して、突拍子もない分野に打って出る場面で用いられる表現ですね。岩谷産業がいきなりコーヒー豆の焙煎機を完成させるなんて、周囲から見ればまさに飛び地です。
しかし、担当者にすれば、飛び地という意識は全くなかったらしい。
小型の焙煎機を作ってカセットコンロと組み合わせる提案を成せば、それまで焙煎機の購入をためらっていた消費者が必ずや振り向くとの確信があったと言います。つまり、そこには必然性があり、あくまで「自社の強み(カセットコンロの存在)を生かす」ことが目的だったのです。
日本酒蔵がワインを醸造
さあ、ここからが今回の本題です。秋田県横手市の浅舞酒造という1917年創業の日本酒蔵が挑んでいる新規事業についてお話ししましょう。
「天の戸」という銘柄の日本酒で知られ、国内外で数々の賞を獲得している浅舞酒造ですが、同社が今進めているのがワイン造りです。同じ醸造酒とはいえ、コメ由来の日本酒とブドウから醸すワインでは、ちょっと趣が異なりますね。小さな日本酒蔵とはいえ、「天の戸」の人気は揺るがないものにも思えるだけに、どうしてワインなのか気になります。
普通に考えれば。日本酒市場の低迷の影響かと想像するところです。消費者の日本酒離れはよく指摘されるところですし、実際、クラフトビールやウイスキーの製造に乗り出す日本酒蔵は、近年、全国各地で増えています。どちらも人気のある領域ですから、そこに活路を見いだそうという話です。
てっきり浅舞酒造も同じような考えでワイン醸造に臨んでいるのかと思ったら、全く違いました。
代表取締役社長である柿﨑常樹氏に尋ねたら、ワイン造りを始めた理由はただ1つで、それは「自分たちの日本酒を売るため」なのだといいます。えっ、新規事業で売り上げを伸ばすためではないのですか。
日本酒を売るためのワイン醸造
どうしてワイン醸造が日本酒を売るためとなるのでしょうか。ちょっと不思議にも感じられる言葉です。
柿﨑氏に順に説明してもらいました。きっかけとなったのは、数年前、自らの日本酒が欧州でアワードを受賞したときのことだったそうです。柿﨑氏は欧州まで赴いたのですが、そこで現地の業界関係者から告げられた言葉を噛み締めた。それはいったいどんな言葉だったか。
「日本酒を欧州で展開したいのなら、ワインのことを学びなさい」という言葉でした。ワイン文化が根付いている欧州で、同じ醸造酒といっても人々のなじみが薄い日本酒を売りたいなら、まずはワインを知るのが早道というアドバイスだったわけです。
柿﨑氏はこの強い示唆を受け止め、帰国してすぐに行動を起こします。ワインに関係する文献や資料からワインを知れば十分か、あるいはワイナリーに出向いて教えを乞えば学びは完了するのか。柿﨑氏の判断はそのどちらでもありませんでした。
「だったら、畑を取得して、自分で土を耕し、ブドウを育て、ワインをつくろう」と柿﨑氏は決めたのです。つまり、欧州で日本酒を売るために、ワイン造りに着手した。ブドウ栽培を社員任せにしたり、ブドウを外部から調達したり、ワインを委託醸造したりしていては学びになりませんから、柿﨑氏自身が毎日のように畑を世話してワイン醸造までを手掛けています。
テロワールの意味
ワインを醸すに足るブドウが実るまでには数年を要します。最初の何年かは近隣の農家からブドウを仕入れて、なかば試験的に醸造を続けました。そして2025年秋、柿﨑氏の育てたブドウによるワインをいよいよ醸せる段階までたどり着いたそうです。
その過程で、柿﨑氏は学びを得ることができたのでしょうか。
「ブドウ畑で過ごし続けて、ようやく分かったことがあります」。柿﨑氏はそう言いました。何だったのでしょうか。「それはテロワールの意味でした」
ワインの世界では。原材料となるブドウが生育する環境や風土を指すテロワールが重視されます。どんな土壌で、どんな気象下で、といった説明を成すのがテロワールですが、「それを言葉にするだけでは不足していると理解できた」と言います。「見えないテロワールというのがあると知りました」とも。つまり、表現するなら、ブドウがそこで何を感じ取って育っているかに思いを寄せ、言語化して伝えるのがテロワールだと気付いたのです。
「日本酒の場合、こんなコメを使って、こんな水を用いて醸していますなどと説明することが多い。でも、それだけでは足りなかったのです」と柿﨑氏は実感を込めて話してくれました。
こうした経験を生かそうと、柿﨑氏はワイン造りを進めると同時に、今度は日本酒のためのコメを育てる田んぼを取得したそうです。「天の戸」のテロワールを語り、欧州でさらに訴求力を高めるための取り組みです。
浅舞酒造の新規事業であるワイン造りは、飛び地のように見えてそうではなかった。そこにはやはり必然性があり、かつ、主軸である日本酒に、さらに強みを持たせるためのものだとよく理解できました。

製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門領域とする一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画する。
日本経済新聞社やANAとの協業のほか、経済産業省や特許庁などの委員を歴任。サイバー大学IT総合学部教授(商品企画論)、秋田大学客員教授。