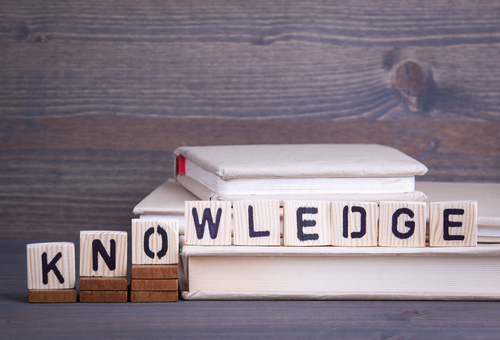わずかな差が結果を分ける
Y&Co.「ヤギチーズ」

黒部の大自然で育ったヤギの乳と、黒部川が注ぐ富山湾の海洋深層水で作られた塩を使った無添加のチーズ専門店
私はいつも「伝わっていない商品は存在していないのと一緒」と考えています。
なにも偉そうに申し上げるわけではなくて、私自身、地域産品のブランディングを手掛ける仕事に携わっていますから、そのように肝に銘じていると表現した方が良いかもしれません。
では、伝えるためにはどうすれば良いか。SNSで活躍するインフルエンサーの力を借りる? いや、少なくない企業がそう動いていますが、狙ったような成果を上げるのは容易ではありませんね。いわゆる企業案件の投稿に、ネットユーザーは食傷気味ですから。
展示会や見本市にブース出展するのはどうか? それなら、一定以上の効果があると思っています。バイヤーは“まだ見ぬもの”を懸命に探すために会場を訪れています。
ただ、良い結果を得るのには1つの前提があると考えます。それは、派手なブース装飾で目を引くなどではなく、ブースに立つ人の真剣度です。これは、出展企業の側が想像するよりも、来場者からすればはっきりと瞬時に見て取れるものです。声を出さず所在なげに立っているだけだったり、出展企業の社員同士が談笑し続けていたりすると、そのブースへの吸引力はたちまち下がります。
2025年に入ってから、いくつもの展示会を訪れましたが、「ブースに立つ人の気迫というのは間違いなく形に表れるなあ」と何度も実感しました。たとえ小さくて地味な作りのブースであっても、そのブースが光っている。そして、足を止めたくなる。そういうものだと思います。
2人の女性経営者
なぜこんな話を冒頭から切り出したかと言いますと、先日訪れた富山県が主催するワークショップのことを思い出したからです。
まさに「伝え切るとはどういうことか」をテーマに据えて、トークセッションに登壇しました。私が司会進行役で、富山で活躍する2人の女性経営者が一緒にステージに上がりました。
このトークセッションを通して私がしみじみ感じたことがあります。「伝え切る」ために成すべきことは、意外とシンプルな行動かもしれない。ただし、そのシンプルな行動に踏み出せるか否かが勝負どころとなる。つまり、先ほど述べた展示会の話と同じです。ただ立っているだけか、それとも、来場者に足を止めてもらえるように気を張るか。やろうと思えばすぐできるのですが、実際には「そこまでしなくても…」と油断してしまいがちです。そこが大きな分岐点となる。
トークセッションの話に戻しましょう。一緒に登壇した2人の女性経営者はこんな人でした。
まず、ヤギの乳を使うチーズで海外の受賞を重ね、日本航空の国際線ファーストクラスの機内食にも採用されているY&Co.(吉田興産)の取締役、吉田朋美氏です。小高い丘でヤギを100匹育て、絞った乳の状態を1匹単位でチェックしていますから、相当に丁寧なチーズを作っていると思います。そして実際においしい。
もう1人は、金属加工の老舗である能作の社長、能作千春氏。「KAGO」というヒット商品をご存じの読者も多くいらっしゃることでしょう。錫でできた板のような姿なのですが、何度でも自在にぐにゃりと曲げられるのが面白い。使い方は多彩です。フルーツ籠のようにも使えますし、私などはワイン籠のような形に曲げてワインボトルを収め、友人への贈り物にしています。
諦めずに手紙を送り続けた
さあ、この2社は、それぞれが作り上げた商品をどのように伝え切ったのでしょうか。伝え切れたからこそ、ヤギチーズは国際線ファーストクラスで採用されたほか、名だたる料理人が仕入れるまでになっています。また、能作は「KAGO」のヒット以降もオリジナル商品を次々に送り出すほどに成長しました
Y&Co.のヤギチーズから話を進めていきましょう。同社はもちろん最初から有名なわけではありませんでした。しかも、チーズを作り始めたのは2013年だと言いますから、チーズ工房としては完全に後発組の部類です。
そんな状況から、吉田氏は何を成したのか。「ここはというレストランのシェフたちに、手紙を毎年したためた」そうです。
なぜ手紙なのでしょうか。吉田氏は言います。「人も少ない会社ですし、お金も少ない。でも世界に打って出たい。ただし、チーズ作りがありますから、私はここから離れられません。ならば手紙だと考えました」。
チーズの持ち味、チーズづくりの環境などを丁寧につづった手紙を何通も送り、その結果はどうだったのか。
1年目、返事は1つもこない。2年目、やはりこない。でも吉田氏は諦めなかった。
3年目、返事をくれるシェフが現れ始めました。そして、チーズの生産現場を見にくるシェフが少しずつ増えていったと言います。そうしたシェフたちが吉田氏のチーズの存在を広める役割を果たす格好で、食のプロフェッショナルの間に高い評価が浸透していったのでした。
「とにかく曲げろ!」 が合言葉
能作「KAGO」

「錫100%」製品の製造・販売を手掛ける。企画から製造までの一貫生産体制から、セミオーダーや部分加工などにも対応している
能作氏の取り組みはどうだったか。創業100年を超える同社ですが、自社ブランド商品を手掛け始めたのは2002年になってからのことだそう。
「KAGO」を発売した2005年時点では、社名も、オリジナル商品も、まだ全国的に知られていない段階でした。今では認知度の高い「KAGO」も、すぐに売れたわけではなかった。
「ここで大きな判断を下した」と、能作氏は振り返ります。東京の老舗百貨店への出店を決めたのでした。「これが大きな転機になりました」
ただし、能作氏の話を聞き進めていくと、ただ単に東京の百貨店に店を出したことが成功を引き寄せたというわけでは全くない。大事なのはここからです。
能作のスタッフたちは、百貨店で「KAGO」の持ち味を懸命に伝えます。合言葉は「とにかく曲げろ!」
金属製なのに何度でもぐにゃりと曲げられて、使い手の創造力を刺激するこの商品は、その持ち味を口頭や文字で説明するより、見てもらった方が明らかに伝わるのだ、と考えたわけですね。
「たとえ商品サンプルをいくつか駄目にしても良い。この商品の面白みを、言葉ではなく目で実感してもらうほかない」という一念だったそうです。
その結果、「KAGO」の面白さは消費者に伝わり、能作ブランドの存在感は今や全国規模で広まりました。
すぐに反応が得られなくても手紙をしたため続ける、商品サンブルをいくつ駄目にしようが曲げ続ける…。2人の話はシンプルなものです。ただただ愚直にやるのかどうか、ここが重要なのですね。

製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門領域とする一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画する。
日本経済新聞社やANAとの協業のほか、経済産業省や特許庁などの委員を歴任。サイバー大学IT総合学部教授(商品企画論)、秋田大学客員教授。