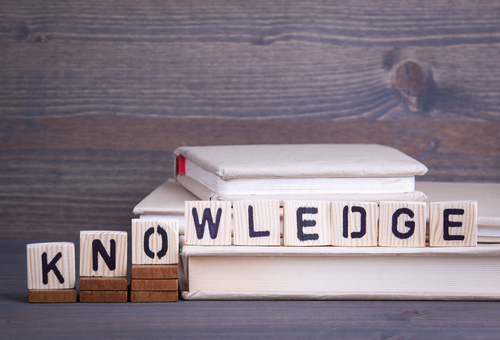サカセ化学工業「救急カート」「METAMO+」
病院向けカートやキャビネットのトップシェアを誇るサカセ化学工業。グッドデザイン賞受賞の「救急カート」(写真左)や、非常時にはプライベートブースに変形するラック「METAMO+(メタモプラス)」(写真右)などを販売している
「無理を覚悟」から始まる
規模が小さくてもキラリと光っている。そんな企業が全国各地にいくつもあります。
なぜ存在感を放っているのか。その理由はそれぞれでしょう。この連載で過去につづった事例で言いますと、例えば創業から100年を超える田中卒塔婆WORKS(Vol.102、2024年5月号掲載)は、長年の卒塔婆づくりで培ったノウハウを活用して、全く領域の異なる米びつ(コメを入れておくストッカー)を開発し、注目を集めています。この例などは、自らの会社に根付いていた技術や知見を生かした話と言えるでしょう。
もう1つ、ECBB(Vol.96、2023年11月号掲載)というベンチャー企業は、1999年の設立からウェブマーケティングを専門としてきましたが、2015年からは自ら商品作りにも乗り出しました。その取り組みの中で高機能なポーチを開発。これがクラウドファンディングで累計支援額3000万円を超える実績を獲得しました。
どうしてそんな異例の数字を積み上げられたのか。代表に尋ねたら、なんと「1000人以上の知人に、1件ずつ個別メッセージを送って支援を依頼した」とのこと。念のため言いますが、一斉メッセージではなく、1000件超の個別メッセージです。
この話を再びお伝えしたのには理由があります。田中卒塔婆WORKSのような老舗らしい長年のノウハウがない場合でも、商品や販売促進を通して会社を光らせる手立てはあるということを、ECBBの事例は示していると思うのです。その手立てとは「多少の無理は承知の上で実践に移す」という覚悟にあると私は感じます。
業界シェア70%の町工場
ここからが今回の話です。先日、私は福井県福井市を訪れました。それはサカセ化学工業の本社工場を見学するためです。
同社は病院向けのカートやキャビネットの分野で、国内シェアが約70%(同社調べ)だと言います。大手メーカーを相手に、70%というシェアを占めているのはどうしてなのか。
代表取締役社長の酒井哲夫氏に聞くと、彼が事業を継承する三十数年前までは大手企業の下請けで樹脂加工を施す事業が主力だったそうです。つまり、そう長くはない期間のうちに、ここまでのシェアを一気に勝ち得たという話でもある。
「まず、私が事業を承継した際、このまま下請け事業を主軸に据えたままで良いのかと考えました」と酒井氏は言います。導き出した結論は2つ。まず、自社ブランドの商品を開発して、事業をそちらにできる限りシフトすること。次に、可能な限り内製主義を貫くこと。考えようによっては決して効率的とは言えないかもしれませんが、長い目で見れば製造コストを抑える効果を得られるとの判断だったそうです。
本社工場を巡る中で、ちょっと面白い言葉を酒井氏から聞きました。「ここはまさに町工場の集合体のような姿なんです」。ああ、確かにそうかもしれません。樹脂加工の工場の隣には金属加工の工場が連なっていて、さらに奥に進むと木材加工の工場がある。これらが1つの場所に並んでいる格好です。つまり、この本社工場の中で、製品を構成する部品の開発製造から組み立てまで、全てを担うことができるわけです。
同社が自社ブランド商品の展開にかじを切ってから少したったころ、社員が全国各地の病院に足しげく通い詰める中で、あることに気付いたと言います。
気付きを放っておかない
それは「病院と一言でくくることはできない」という話でした。病院内にはさまざまな物の流れが存在します。カルテも、医療機器も、患者さんに提供する病院食もそうです。そうした物の流れは「実は病院ごとに大きく異なっていて、『こんな感じ』と簡単に言うことはできない」と酒井氏は語ります。同社は数々の病院から話を聞く作業を通して、そのことを知りました。
では、それがカートやキャビネットという同社の主力商品と、どのような関係があるのか。
「いわゆる既製の商品をそれぞれの病院にそのまま組み込むと、まず確実に病院の医師や看護師、職員にしてみると60〜70%程度の満足度しか得られないんです」(酒井氏)
決して100%の満足はもたらせないということですね。
だったらどうするか。ここで同社は「一品特注」というテーマを掲げます。それぞれの病院のものの流れをじっくりと聞き出して、どこに課題があるのかを検討して、病院ごとにカートやキャビネットの仕様を細かく変えて納品する、という決断を下します。
「それ、本当ですか。そんな面倒なことを?」という私の驚きに、「本当です。商品カタログは一応存在しますけれど、カタログの商品そのままを納品するケースは1%を切ります」と酒井氏は笑います。「効率化の真逆なんですよ」とも。
なぜこんな一品特注体制を実行できるのかというと、「それは、この会社が町工場の集合体だからにほかなりません」と酒井氏。本社工場で部品1つから製造しているため、「一品特注であっても短期間で完成させられるのは、極めて大きな強みです」。
つまりは、酒井氏が事業承継するタイミングで内製重視の体制を作ろうと、一見非効率とも思える判断をしたことが、一品特注を果たす上で原動力になったという話だったのでした。
今回、冒頭で「多少の無理は承知の上で」とつづったのは、このサカセ化学工業の取り組みがまさにそうだと私は感じたからでした。ECBBが勝負どころで1000件を超える個別メッセージを送ってクラウドファンディングの成功を期したのも、サカセ化学工業があえて一品特注という方針を打ち出して実行し続けているのも、話の種類は違うにしても、「時に無理を承知で動く」ことの意義を示している点が共通しています。
あらゆる業界で激しい競争が繰り広げられている現在、経営や商品開発、あるいは販売促進における効率化は大事です。そこを否定する気持ちはありません。ただし、ある局面においては効率化の真逆を選択するという意思決定が効いてくるケースがあるのだという話ですね。
次なる一手は
業界シェア70%の同社ですが、次の一手も打ち出しています。
例えば、普段はカートやラックとして使え、震災などの非常時にカートが介助チェアになったり、ラックが着替えや授乳に助かる簡易ブースに形を変えたり、という商品をすでに展開しています。
さらには、病院向けカートやキャビネット製造で積み重ねた知見を生かす形で、業界をまたがった新領域での協業プロジェクトも開始間近と聞きます。また果敢に攻めるのですね。

製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門領域とする一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画する。
日本経済新聞社やANAとの協業のほか、経済産業省や特許庁などの委員を歴任。サイバー大学IT総合学部教授(商品企画論)、秋田大学客員教授。