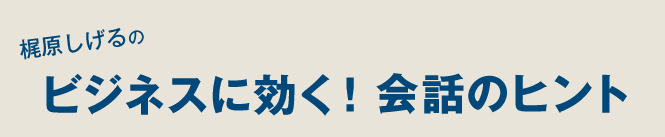
2018年8月号
全く不満を漏らさなかった彼女のひと言
梶原「25歳は人生の考えどころだよねえ」
若尾「それを越えると不思議なモノで、それなりに元気が出て、バンドとバイトをガツガツできちゃうんです。僕もそうでした。ところが……」
梶原「三十路の坂というか壁が立ちはだかる?」
若尾「引くならもうここしかないかなあ、越えるなら極めないとなあって、これも不思議なモノで心を揺らすものが出てくるころ……って、実はこれ、僕のことなんですが」
驚くことに軟派なイメージのミュージシャン・若尾青年は、中学校の同級生である女性との長きにわたる純愛を大切に育んでいたのです。
大学を卒業して就職もせず、ミュージシャンとはいえ、見方によってはフリーターのような暮らしをする彼に不満を漏らしたり、愚痴をこぼしたりすることもなく、マリア様のような彼女は彼の生き方をおおらかに見守りながら、笑顔で応援してくれていたそうです。
彼がたまらなく申し訳ない気持ちになったのは、30代が視野に入り始めたころ。「先の人生」についてなど口にしたことのなかった彼が、彼女にふと漏らしたのだそうです。
「もう、僕は、まともなサラリーマンにはなれないかもしれない。でもそろそろ、きちんとした仕事に就かないといけない気もする。ぜいたくを言えば、クリエーティブな、物づくりみたいな……」
ここに至っても、ミュージシャンとしての作品作りやプロモーションアイテム制作の世界から決別できずにいた彼。こんなことを言えば相手の女性は堪忍袋の緒が切れ、「なんて身勝手な!クリエーティブな仕事だなんて、いまさら言えた身分だと思ってるの!?」と、激怒されてもおかしくないと、私は思いました。
ところが彼女は、ニッコリ笑ってこう言ったのだそうです。
「ブドウを育ててワインを造るのって、クリエーティブな物づくりだと思わない?」
彼女の実家は、ブドウ栽培を江戸の昔から、そのブドウを使ったワイン醸造を昭和の初期から始めた、伝統あるワイナリーであることを彼はあらためて思い出しました。
彼は勇気を奮って彼女にプロポーズ。彼女は受け入れてくれました。今からちょうど10年前、2008年のことでした。とはいえ、仲間に別れを告げ、東京の家を引き払い、彼女の山梨の実家に向かう新宿発甲府行きのJR中央本線の特急「かいじ」号車中では、「墓場に帰るような気持ちだった」と罰当たりなことを言って当時を振り返るのです。音楽三昧、好き勝手をしていた都会での暮らしに、まだ未練は残っていたんですね。
勝沼ぶどう郷駅で降りて、彼女の実家に到着しました。ご両親は義理の息子が、家業を継いでくれることを大いに喜んでくれました。
ブドウ畑作りの知識ゼロ、ワイン醸造の知識ゼロからの三十路スタートでした。ちょっと前まで床に就くのが朝4時だった自分が、今では同じ朝4時に起き、畑へ出掛けます。夕方まで作業して、風呂に入って食事して、夜9時になると布団の中です。「東京時代は、ライブがそろそろ始まる時間だったなあ」


