業務の可視化でDXを実現し生産性を向上する:マネジメントDX
【図表1】企業におけるDX推進状況
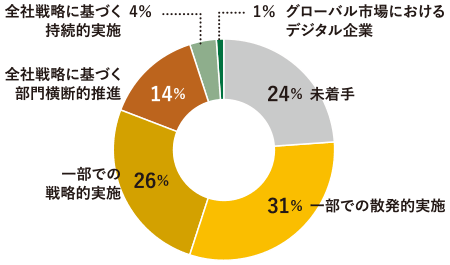
出所:情報処理推進機構(IPA)「DX推進指標自己診断結果分析レポート(2020年5月28日)」よりタナベ経営が作成
コロナ禍で痛感したDXの必要性
情報処理推進機構(IPA)がまとめた分析リポート(【図表1】)によると、国内企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進状況は、約半数(55%)の企業が「未着手」か「一部での散発的実施」だという。
また、IPAの「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査(2019年4月)」によると、調査企業が現在取り組んでいるDXの多くは「業務の効率化による生産性の向上」(78.3%)であることが分かった。
RPA(ソフトによる業務の自動化)ツールの導入による業務の効率化やリモートワークといった働き方の変化、商品・サービスの高度化が進む中、企業間の競争は激化しており、DXの活用でデジタル時代に勝ち残れる会社に進化する必要がある。だが、推進の半ばで頓挫する企業も散見される。
DXに失敗する企業には、「経営陣と現場におけるDXに対する認識の不一致」「推進初期段階で大きな成果を求める」「既存の業務フローを変えずにDXを推進」という三つの要因がある。
本稿では、特に多い「既存の業務フローを変えずにDXを推進」する場合の解決策を述べていく。
【図表2】DXレポートから見る「2025年の崖」
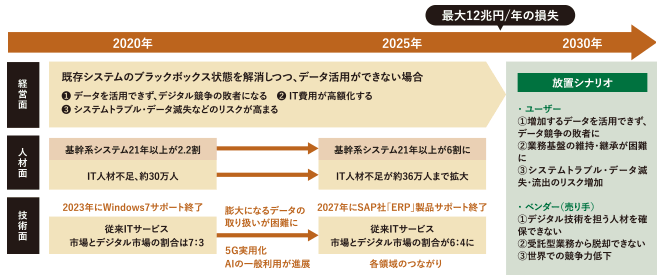
出所:経済産業省「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」(2018年9月)、「IT人材需給に関する調査」(2019年4月)などより筆者作成
DXを成功に導く業務の可視化と業務フロー改善
DXの実現に向け、既存業務の可視化とDX後に合わせた業務改善が必須となる。具体的な失敗ケースとして、契約書の発送業務のデジタル化を例に挙げる。
アナログ業務が残る会社では、事務担当者が契約書のデータをワードなどで作成し、データを紙に印刷して顧客へ発送する。仮にテレワークへ移行した場合、契約書の作成まではデジタルで対応できるが、社判や上司の印鑑といった書類への押印がないと送れないため、結局は事務所に出社して印刷・発送をしなければならない。このように、既存の業務フローを変えずにデジタル化だけを推進しても成功することは難しい。
まずは、既存業務の可視化から始めることが重要だ。各業務フローにおける意味を理解した上で、報連相に具体性を加える5W1H※で業務の可視化を実施する。この段階において、既存業務の所要時間を計測することを勧める。ポイントは大きく三つである。
(1)業務目的の可視化
業務フロー作業ごとに目的を把握する。作業目的の把握とともに作業の必要性を把握することで、次のステップで実施する業務のスリム化に役立てる。
(2)業務担当者と関係者の可視化
該当する業務の関係者および関係部署を洗い出す。社外との連携を伴う業務の場合は、企業別に分析することで業務がより明確になる。
(3)判断項目・基準の可視化
デジタルの場合と人間の場合で大きく異なるのが、判断できるか否かである。人間は無意識に判断を行っており、この判断項目・基準を明確にしなければ、業務をデジタルに代替させることができない。
次に、業務フローにおいて古くなった要素を思い切って捨てていく。「決まっていることだから」「そう教えられたから」などの古い慣習だけで進めてきた業務があれば、それを見直して改善する必要がある。
最後に、部分的な改善にとどまることなく、大胆に改善を実施していく。ゼロベースで検討する姿勢で臨まなくては、DXを諦める原因になりかねない。「紙ベースの資料だから」「取引先が対応してくれないかもしれない」「担当者がデジタルに精通していない」などの“できない理由”を並べ、変革を止めてしまってはならない。
ここまで、DXの実現に向けた業務改善について述べてきた。DXは全企業・全産業におけるテーマであり、経済産業省が発表した「DXレポート」では、DXが進まなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告している。(【図表2】)
コロナ禍が収束すれば、企業のDXの必要性がなくなるというわけではない。DXの実現は、難易度が高く成果が出るまでに時間を要する。だが、一つの経営課題として捉え、全社一丸となって取り組みを継続できれば、必ず成果は表れる。今一度、自社の業務を細かく可視化し、DXを導入することで生産性改革につなげていただきたい。
※5W1H(When、Where、Who、What、Why、How)にHow much(いくら)を加えた用語。How muchを加えて相手に伝達することにより、ビジネスシーンにおける報連相の具体性が高まる



