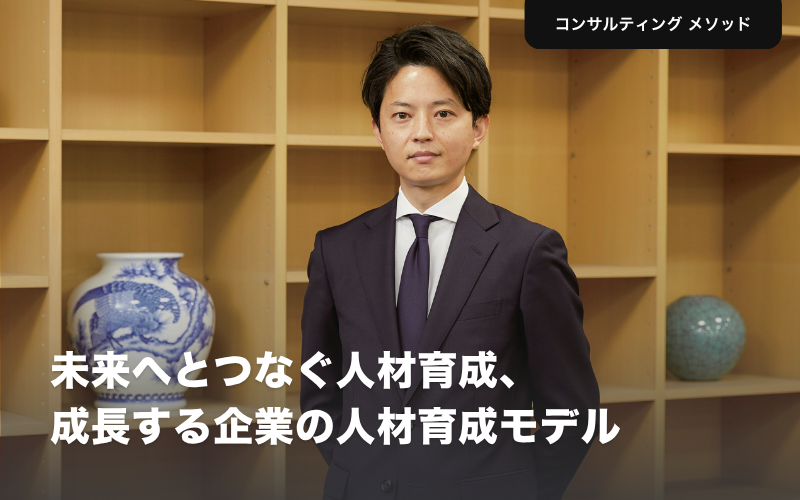時代のプロデューサー「蔦屋重三郎」
人材育成をテーマに、歴史に残る3人の人物を取り上げます。まず紹介するのは、2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」の主人公でもある、蔦屋重三郎です。日本のメディア産業の元祖とも言える人物であり、始まりは貸本屋業でした。
文字を読める顧客がたくさんいて商売が成り立ち、絶対に儲かることを重三郎はよく分かっていたのです。貸本屋から小売り・卸売り・版元・広告業へと次々と新規事業を成功させながらも、生涯にわたって本業の貸本屋を手放さなかったことがポイントです。
また、それまで趣味の領域であった作家や絵師に、日本で初めて報酬(ギャラ)を支払ったのも重三郎です。その原資となったのが広告収入であり、彼はこれによって才能あるクリエイターを支援し、良質なコンテンツを生み出すという新たなビジネスモデルを確立しました。
自身の店である耕書堂を経営しながら、人材育成の観点から見ると、重三郎はプロデューサーです。吉原という遊郭で生まれ、身分は町人で出自は不利でしたが、幕府の御家人(現代の国家官僚に相当する役職)で狂歌師の大田南畝、戯作家の朋誠堂喜三二といった公的な立場にある人々と連携し、彼らをプロデュースすることで社会的信用を築いていきました。
さらに、ある程度実績を残したら、町人出身の山東京伝をパートナーとし、作家業でギャラを払い、その知名度を生かして顧客を集める小物販売との2本柱で生計を成り立たせる支援を行いました。また、喜多川歌麿や東洲斎写楽、曲亭馬琴、十返舎一九など次世代の作家や絵師を育成し、その大成を後押ししました。
事業承継においても、血縁のない番頭に全財産を譲り、2代目を任せています。常に“金の匂い”がするビジネスにアンテナを立て、しっかりと当てて儲ける「今だけを考える商売人」で、「世の中を変えたい」という壮大なビジョンがあったわけではないですが、それが蔦屋重三郎でした。
カリスマを支えた「豊臣秀長」
2人目は、重三郎に続く2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主人公でもある、豊臣秀長です。農民から天下人になった兄の豊臣秀吉を支えた人物で、俗に言う“じゃないほう”ですが、だからこそ共感を得る部分があります。世の中の多くの人は、自分を“じゃないほう”と思って人生を過ごしているからです。
一代でのし上がったカリスマ経営者の秀吉は、右腕として自身を支えた弟の秀長に大きな権限を委譲し、100万石もの領地を与えました。「秀長が長生きしていれば、『関ヶ原の戦い』は起きずに豊臣政権は安泰であった」と後世に言われるほど、その存在は大きいものでした。しかし、秀長の死後、秀吉は実質的なワンマン経営に陥り、後継者選びに迷走することになります。
秀吉には自分の子どものように育てた子飼いの武将たちがいました。加藤清正や福島正則、石田三成などです。秀吉が武将として名を上げていく段階では、清正や正則が武官として活躍し、天下人となった後は、三成が文官として支えました。
後継者に対しても、幹部に対しても、一代のカリスマである秀吉は「トップダウンであり過ぎた」と言えます。右腕であった秀長とは対照的に、子飼いの武将たちを「指」のように扱い、大きな権限を委譲することはほとんどありませんでした。
そもそも、秀吉は商売人ではなく、本質的には政治家であり官僚です。ビジネスの原理を学ぶのであれば、政治家や公務員よりも、同じ商売人である渋沢栄一や岩崎弥太郎、近い時代では本田宗一郎や松下幸之助を参考にする方が良いでしょう。
未来を見つめるビジョナリー「津田梅子」
最後に取り上げるのは、津田塾大学の創設者であり、5000円札の肖像画にも描かれた津田梅子です。幕末に生まれ、6歳で米国へ留学し、「帰国後には日本語を忘れていた」という逸話を持つ人物です。
当時は英語教師をしたり、鹿鳴館でダンスマナーを教えたりするぐらいしか活躍の場がなかった梅子は、再留学を決めました。米・ブリンマー大学で教育学や生物学を学び、日本人女性として初めて高等教育を修了。文系・理系のハイブリッドである梅子は非常に総合力の高い女性でしたが、何よりも優れていたのは「常に未来を考えている」ことでした。
再留学中の27歳の時、現地の日本人に寄付を募り、日本女性のための奨学金制度を設立。帰国後の1900年には、36歳で女性の高等教育を目指す私塾「女子英学塾」(現津田塾大学)を開校しました。厳しい授業と面倒見の良いキャリア指導で後進を育てることに力を注ぎ、英語系出版社も設立。常に自分の強みである分野で勝負をかけて一点突破し、「支援者が展開を広げるまでが自らの役割」と自覚していたのです。50歳代で体調を崩し、60歳代でひっそりと生涯を閉じました。
津田梅子は、「未来を見つめる」ビジョナリーな「教育者」でした。しかし、そのアプローチはあくまで教育者としてのものであり、顧客・取引先・従業員といった多様なステークホルダーから常に評価される、利益追求を目的としたビジネスとは本質的に異なります。
紹介した3人の人物像から、人の育て方は職業によって異なることを知り、自社はどれかを見つめ直すきっかけになると幸いです。

1972年京都府生まれ。法政大学文学部史学科卒業後、東進ハイスクール日本史講師などを経て、現在はリクルートが運営するオンライン学習サービス「スタディサプリ」で日本史・歴史総合・倫理・政治経済・公共・地理など高校社会科5科目・中学社会科3科目の計8科目を担当する「日本一生徒数の多い社会科講師」。43歳で早稲田大学教育学部生涯教育学専修に再入学し、49歳で卒業。主な著書に『もっと学びたい!と大人になって思ったら』(2025年5月、筑摩書房)、『アイム総理 歴代101代64人の内閣総理大臣がおもしろいほどよくわかる本』(2024年3月、KADOKAWA)など、監修書含め83冊・累計160万部を超える。