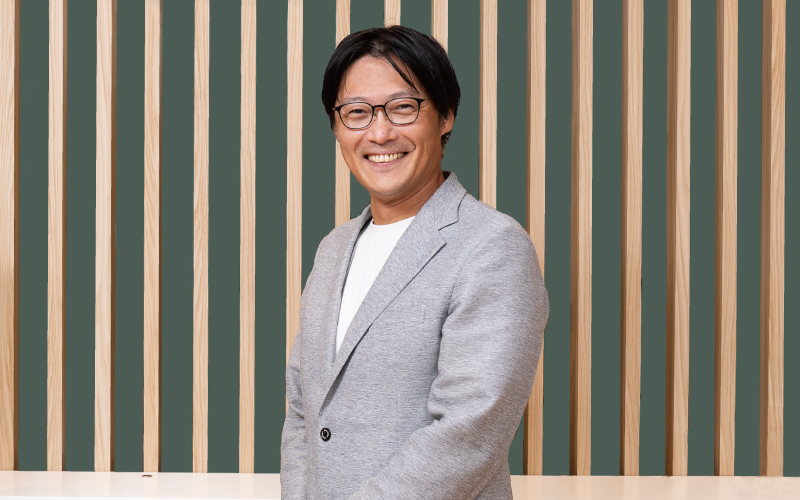統計学が解き明かした人的資本の真価
「はたらく人が抱えるストレスに伴う経済的損失は、男性で生涯平均約6000万円になる」。九州大学大学院工学研究院都市システム工学講座の教授・馬奈木俊介氏は、ピースマインドとの共同研究※1でこの衝撃的な数字を導き出した。ピースマインドが企業向けに提供するストレスチェック「職場とココロのいきいき調査®」の3年間延べ約100万件のデータを基に、馬奈木氏が分析・試算した結果である。
ストレスチェックデータを分析した結果、不安や抑うつ感は特定の個人に偏らず、幅広い層に分布していることが明らかとなった。また、九州大学都市研究センターの調査※2によると、ストレスが低い人ほど年収が高いという相関が確認されている。
これらの調査結果に基づくと、ストレスとの相関から導かれる男性1人当たりの年間平均損失額は約100万円。ストレス状況が変わらず、25歳の平均的な男性が40年間働いたと仮定すると、生涯平均で6000万円程度の損失となる計算だ。この「見えにくい損失」が、企業全体に深刻な生産性低下をもたらしている。
「年間100万円を投じて従業員のストレス軽減システムを構築できれば、1人当たり6000万円の経済効果が期待できる。これほど明確なリターンを示せる投資は他にありません。従業員のウェルビーイング向上は、設備投資や新規事業と異なり、確実に、しかも長期的にリターンが見込めます」と馬奈木氏は言う。経営者が「コスト」と捉えがちなウェルビーイングが、実は最も確実性の高い「投資」であることを、データが物語っている。
馬奈木氏が行った国際比較研究によると、北欧諸国では働く時間の増加とともに幸福度が向上し、8時間でピークを迎える。一方、日本は働き始めから右肩下がりで幸福度が低下し続けるという。
なぜ、このような差が生まれるのか。その要因は、日本企業の意思決定プロセスにある。「日本企業では『検討した結果、やりません』で終わるケースが非常に多い。やらない理由はいくらでも見つかりますが、そこから1歩でも前進できるかどうかが、企業の成長を大きく左右します」と馬奈木氏は指摘する。
具体的には、次のような構造的な課題が、日本企業の生産性を慢性的に低下させていると馬奈木氏は考えている。
❶ 多層的な承認プロセス
承認を得るために複数の段階を踏む必要があり、意思決定が遅れることで現場の機動力が低下する。
❷ 成果の見えにくさ
良い提案が通らず、努力が成果に結び付かない実感が、学習意欲やモチベーションの低下を招く。
❸ 組織の硬直性
特に大企業では前例踏襲が根強く、現場の声が上層部に届きにくい。
「統計的に見ると、日本人の7割は他の先進国並みのウェルビーイングを保っています。問題は残り3割、特に非正規雇用の人々のウェルビーイングが著しく低いことです。
この層が全体平均を押し下げているので、企業としてはここに重点的に投資することで、大きな改善効果が期待できます」(馬奈木氏)
ウェルビーイング実装には継続的な定量測定が必要
ウェルビーイングを可視化するには、数値で捉えられる指標を定期的に測定することが重要だ。例えば年1回、従業員の幸福度、職場満足度、同僚との人間関係、目標への共感度などを測定する。
「初期投資を抑えたい場合は、歩数計アプリのデータから始めることをお勧めします。社内移動パターンと満足度の相関が見えてくるはずです。実際、適度に移動している従業員の方がストレスが低い傾向があることが分かっています」(馬奈木氏)
先進的な手法として、衛星画像を活用した分析もある。住環境と職場環境のデータを比較することで、緑地の多い環境に住みながら働く人の幸福度が高いことなどが明らかになっている。こうした空間的な要素も、従業員のウェルビーイング向上に寄与する重要な要素として注目されている。
企業が初めてウェルビーイング経営の実装を試みる際のポイントは、次の3つである。
❶ 小さく始めて段階的に拡大
全社員のデータを一度に取ろうとせず、まず部署を絞って実施する。回答率も5割で良いから答えてもらう、嫌な人は答えなくて良いという姿勢でハードルを下げ、やり切ることが重要。具体的には、特定部署で1年間試行し、そのノウハウを他部署に展開していくアプローチが効果的である。
❷ ゴール共有でストレス軽減
馬奈木氏の研究によると、統計的に、会社のゴールを共有している組織は、そうでない組織に比べて従業員のストレス値が低いことが、データから明らかになっているという。ゴールの共有は、経営の王道として経営者にも受け入れられやすく、結果的に従業員のストレス軽減効果も期待できる、一石二鳥の施策である。
❸ 継続性の担保
ウェルビーイング施策を1年で終わらせてしまう企業が多い。継続するには、制度として定着させることが重要だ。年次評価項目への組み込みや、役員報酬との連動、外部専門機関との長期契約などの仕組み化が効果的である。
企業での実装事例として、馬奈木氏が人的資本の経年測定を実施している地方銀行大手のふくおかフィナンシャルグループ(FFG)の取り組みを挙げる。FFGは社内で数値測定をするだけでなく、サステナブルスケールという子会社を設立し、企業のSDGsやESGの取り組みを可視化するサービス「Sustainable Scale Index」を展開している。
「性別、年代別の人的資本変化を定量化することで、どの層にどのような投資を行うべきかが明確になります。例えば、30歳代女性の人的資本が他の年代より低い傾向が見えれば、その層への研修投資を重点的に行う。配置転換でも、データに基づいてより適切な判断ができるようになりました」(馬奈木氏)
具体的には、管理職が経験則で判断していた「この人は営業向き」「管理職候補」といった人事配置が、客観的なデータに基づく判断に変わった。その結果、FFGは従業員満足度の向上と業績向上の両立を実現している。「経験と勘」による人事から、「データドリブン人事」への転換を図ったことが奏功しているのだ。FFGのこうした仕組みは、地方銀行業界で先進的な取り組みとして注目されている。
人的資本経営を成功に導く3原則
人的資本経営にテクノロジーを活用する企業が増えている一方で、課題も見えてきている。可視化のためのソフトウエア開発が完了すると、それがどう使われて、何の改善に役立つのか、利益が上がるのか、といったことを検証せずに終わってしまうケースが多いと馬奈木氏は指摘する。開発完了が目的となってしまい、実際の活用状況や効果測定が後回しになりがちだ。
しかし、テクノロジー活用の環境は着実に改善している。「導入コストは年々下がっています。5年前に1000万円規模だったシステムが、今なら300万円程度で導入可能です。中小企業でも十分に手の届く水準になっています」(馬奈木氏)
重要なのは、導入したシステムを継続的に活用し、その効果を定期的に検証することだ。テクノロジーの進化により、人的資本の測定と改善がより身近になった今こそ、その恩恵を最大限に活用する時代と言えるだろう。
最後に、馬奈木氏は「人的資本経営を成功させるために企業が押さえるべき原則」として、次の3つを挙げた。
❶ 科学的根拠に基づいた投資判断を行う
❷ 完璧を求めず、継続を重視する
❸ 組織の意思決定プロセス改革を優先する
「ウェルビーイングは、統計的に測定可能で、明確なROI(投資利益率)を算出できる投資対象です。企業経営者の皆さんには、データに基づいた投信判断をしていただきたいと思います。
次に大切なのは、完璧よりも継続が重要であることです。100%の精度で1年間で終わってしまうより、60%の精度で継続する方が、はるかに価値があります。
最も大きな投資効果が期待できるのは、承認プロセスの簡素化です。これにより、従業員のモチベーション向上と業務効率化の両方が実現できます」と馬奈木氏は説明する。
人的資本経営は、企業の未来を左右する「投資判断」そのものである。
「“人を大切にする経営”を、理想論ではなく、科学として実装する時代がすでに始まっています。従業員のウェルビーイング向上は、企業の未来を支える最も確かな投資です。従業員1人当たり6000万円の価値を眠らせるのか、引き出すのか。その選択は、経営者の決断に委ねられています」(馬奈木氏)
※1 ピースマインド「【調査結果】はたらく人が抱えるストレスに伴う経済的損失は、男性で生涯平均約6000万円に」(2020年10月)
※2 九州大学都市研究センター・国際調査(2015年)による。論文は国際学術雑誌「Kyklos」に掲載。“Relative Income, Community Attachment and Subjective Well-being: Evidence from Japan”, Kyklos, 25 November 2018.

主幹教授・都市研究センター長
(株) aiESG 代表取締役社長
米国ロードアイランド大学大学院博士。2015年より九州大学教授。株式会社aiESG代表取締役社長、一般社団法人NCCC理事長、経済産業研究所(RIETI)ファカルティフェローを兼任。国連SDGs指標開発に携わり、過去10年の世界経済学論文ランキング(IDEAS)で日本トップの実績を持つ。研究領域はウェルビーイング研究、環境経済学、都市工学と幅広く、統計学を駆使した社会課題解決に取り組んでいる。
馬奈木俊介研究室 http://www.managi-lab.com/