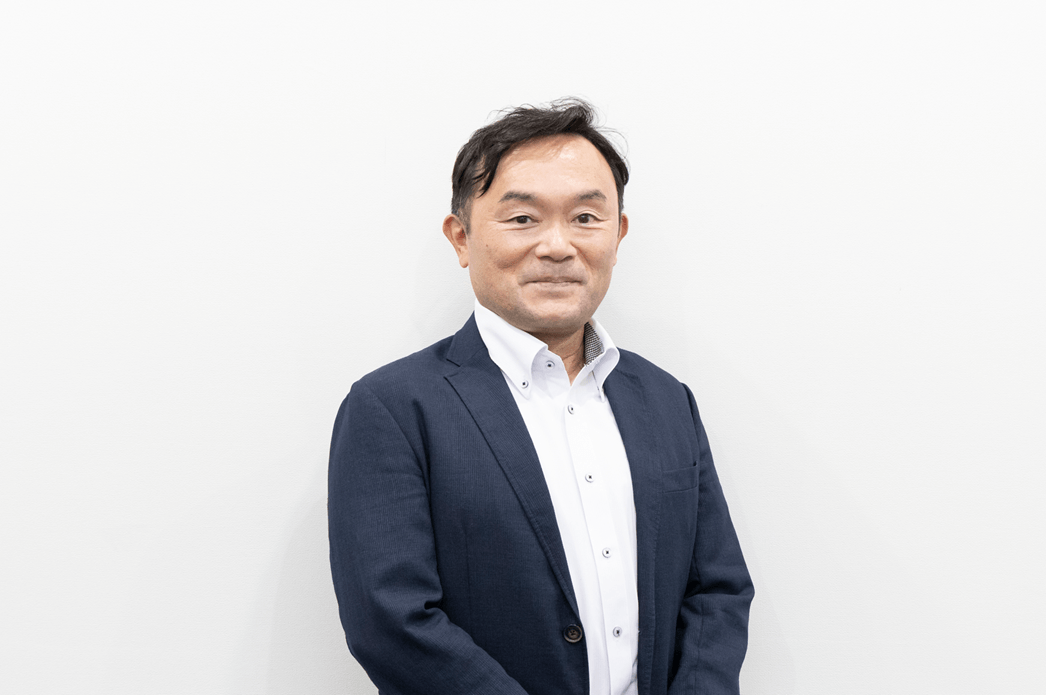
鈴木化学工業所 代表取締役社長 小幡 和史氏
樹脂製の精密自動車部品メーカーである鈴木化学工業所は、2010~2020年の10年間で新卒入社3年以内の離職率0%を実現し、年齢や部門の垣根を超えた取り組みやIoTの積極導入が評価されて、2020年に経済産業省の「はばたく中小企業・小規模事業者300社」と「地域未来牽引企業」にダブル選定された実績を持つ。同社の若手・中堅社員の活躍に向けた取り組みと経営幹部の育成方法に迫る。
技術力を生かし、オリジナル商品を開発
ブレーキオイルのタンクや冷却水タンクなど、自動車の重要保安部品を中心とするプラスチック部品の製造を手掛ける当社は、1952年に愛知県岡崎市で創業し、現在は額田郡幸田町に本社を構えています。
主力事業は自動車のプラスチック部品製造ですが、最近では自社商品の開発にも力を入れています。例えば、耐久10年・10万kmの自動車技術から生まれた、軽くて割れにくい二重構造の「十年急須」や、幸田町や当社のキャラクターグッズなどです。
こうした開発は、当社の技術力を生かした新たな挑戦です。自動車部品の製造で培った技術を応用し、耐久性や品質にこだわった商品を提供しています。社員のモチベーション向上や新たな市場開拓にもつながっています。
ただし、売り上げの99.9%は依然として自動車部品が占めています。自社商品の売上高比率はまだ0.1%程度ですが、これからの成長を期待しています。

哺乳瓶にも使われる飽和ポリエステル「トライタン」を使った、保温性が高く、結露しない「十年急須」

鈴木化学工業所の公式マスコット「すずたん」の3Dフィギュア

愛知県幸田町のオリジナルキャラクター「えこたん」(中央)の製作をきっかけに、さまざまなキャラクターを手掛けている
会社の成長と、社長としての成長の軌跡
当社の2024年9月期の売上高は39億4000万円、2025年1月末の従業員数は186名です。2015年の売上高は約22億円、従業員数は約120名でしたので、この10年で大きく成長しました。
リーマン・ショックやコロナ禍の影響もありましたが、社員の努力のおかげで回復し、2024年9月期には過去最高の売上高を達成できました。コロナ禍でも人員調整を行わず、雇用を守ったことが、回復が早かった大きな要因だと感じています。
当社では、外国人技能実習生を受け入れていません。地域に根差した企業として、地元の人々に働きやすい環境を提供することを目指しています。
当社の創業者は鈴木一幸、2代目社長は鈴木啓之、3代目社長が私です。私は1993年、20歳の時に鈴木化学工業所に入社しました。パソコンの専門学校を卒業後、会社説明会で鈴木化学工業所と出合い、熱心に誘っていただいて入社を決めたプロパー社員です。
入社後は製造部成形課で生産管理の仕事を担当しました。当時の従業員数は80~90名ほどで、品質に課題がありました。品質管理部門の課長が次々と辞めてしまう状況の中、2002年に私が品質管理課長に任命されました。品質管理の経験も知識もない中でのスタートでしたが、生産管理の経験を生かし、品質改善に取り組みました。
品質管理の仕事を通じて、製造部門との連携の重要性を学びました。お客さまからのクレーム対応や品質改善のための「なぜなぜ分析」を行い、品質向上に努めました。この経験が私の成長に大きく寄与しました。
その後、2007年にプラスチック成形技能士(特級)という国家資格を取得し、プラスチック成形技検定の試験官も務めています。試験官としての活動は現在も、これからも続けていく予定です。
2017年には社長に就任しました。当時、専務が10歳年上で、社内でも議論がありましたが、最終的に私が指名されました。2代目に理由を聞くと、「大変な時代だから若い力に期待した」とのことでした。2025年現在、社長として8年目を迎えています。
当社は地域貢献活動にも力を入れています。例えば、2020年から小学校の通学路にウォーターサーバーを設置し、夏の暑い時期に飲料水を提供しています。この活動は保護者や地域の方々から好評で、メディアにも取り上げられています。社員も楽しみながら取り組んでおり、会社の一体感を高めるきっかけにもなっています。
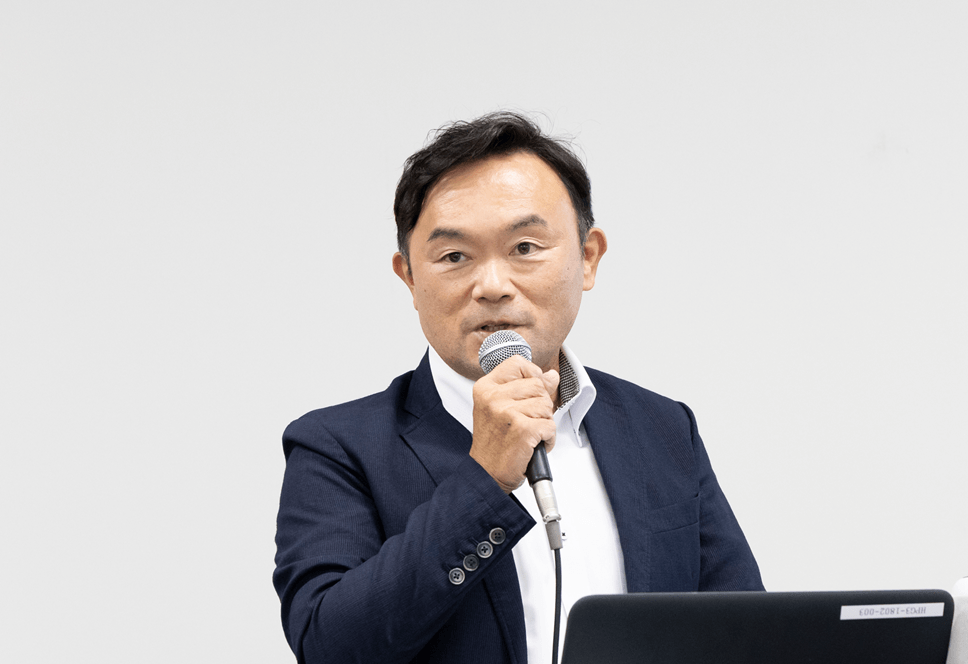
鈴木化学工業所 代表取締役社長 小幡 和史氏
中期経営計画の策定でリーダー人材を育成
当社では「強いチームづくり」を目指しています。個人戦ではなく、チームで課題に取り組む「ゾーンディフェンス」のような組織です。
チャレンジを評価し、失敗を恐れず挑戦できる風土を醸成することが重要です。失敗をマイナス評価するのではなく、挑戦しないことをマイナスとする評価基準を設けています。
また、中期経営計画を策定し、全社員で共有しています。第Ⅱ期中期経営計画「チャレンジS Part2」は、課長やグループリーダーが中心となり、合宿形式で策定しました。
合宿では、仕事終わりに集まり、夜遅くまで議論を重ねます。翌日は朝から再び議論を行い、計画を練り上げます。このプロセスを通じて、社員同士の一体感が生まれ、中計への理解と納得感が深まります。
完成した中計は、全社員が参加する発表会で共有します。発表会はホテルで開催し、おいしい料理を提供するなど、社員が楽しめる場を設けることによって参加率を高め、中計の浸透につなげています。

出所:鈴木化学工業所の講演資料
中計を実行に落とし込み、経営視点を養うプロジェクトを実施
さらに、中計を実行し、次世代の役員候補者を育成するため、2024年に「みらい創造プロジェクト」を実施。若手である課長を中心に6カ月間の研修を行い、リーダーシップや経営視点を養う機会を提供しました。
具体的には、参加者による部門横断メンバーで「チャレンジS Part2」の戦略テーマに基づいたプロジェクトテーマと目標を決定し、「Plan(計画、意志決定)」⇒「Do(周りを巻き込んで推進)」⇒「Check(振り返り)」⇒「Action(再実行)」のサイクルを回して、定量的な成果を上げるものです。
プロジェクトの推進を加速させる目的で、インプットの場(講義+ディスカッション)を設けながら、最終的な成果を全社員の前で発表するアウトプットも行い、参加メンバーが主体的に取り組めるようにしました。

出所:鈴木化学工業所の講演資料
今後の課題として、第3期中計の策定と、次期役員の指名を進めていきます。プロパー社員から社長になった私の経験を生かし、これからも主体的に人材育成に取り組んでいきます。社員の定着率を高めるため、公平な評価とコミュニケーションを重視し、成長を支援していきたいと考えています。
【コンサルタントの注目ポイント】
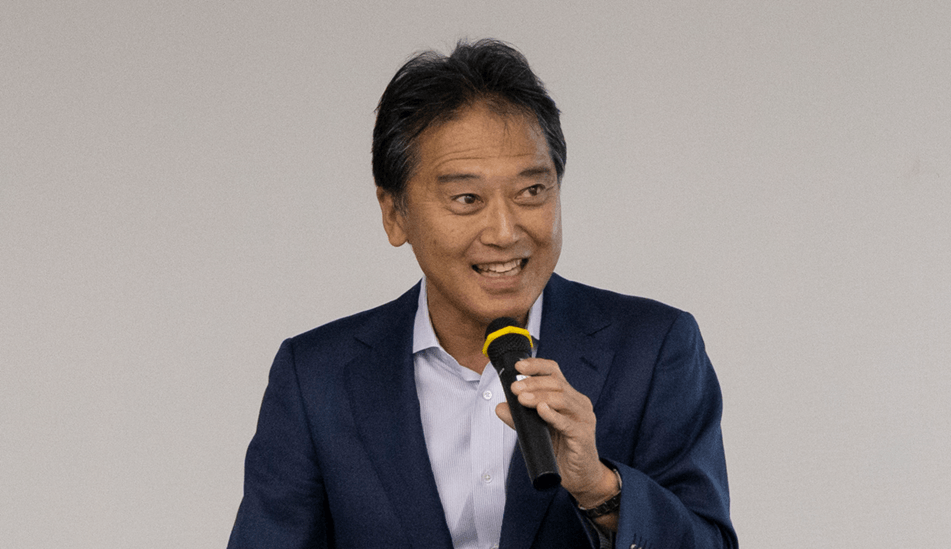
タナベコンサルティング エグゼクティブパートナー 種戸 則文
鈴木化学工業所の「強いチームづくり」に学ぶべきポイントは3つあります。
1つ目は、「チャレンジには失敗が付き物」という考え方です。失敗をマイナスと捉えるのではなく、「やったこと」を評価する。この考え方は多くの企業でなかなか実践できていません。しかし、この姿勢が風土を変え、成功につながる重要な要素です。
2つ目は、中期経営計画への全員参画です。策定や発表会への参加を全社員に求めることで、全員参加型の経営を実現している点が印象的でした。
3つ目は、社長の本気度を示すことです。これが会社の風土づくりに直結し、強いチームを実現する成功要因となっています。
※本稿は、2025年9月16日に愛知県名古屋で開催された、タナベコンサルティンググループ中部本部主催「経営者人材育成講演会『次世代を担う経営者の育成戦略:組織を成功に導く人材育成の秘訣」の講演内容を記事化したものです。
PROFILE
- (株)鈴木化学工業所
- 所在地:愛知県額田郡幸田町大字六栗字左右作2-1
- 創業:1952年
- 代表:代表取締役社長 小幡 和史
- 売上高:39億4000万円(2024年9月期)
- 従業員数:186名(2025年1月現在)





