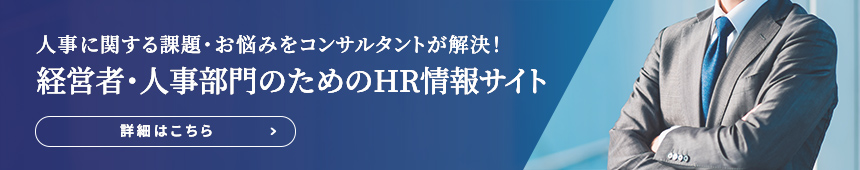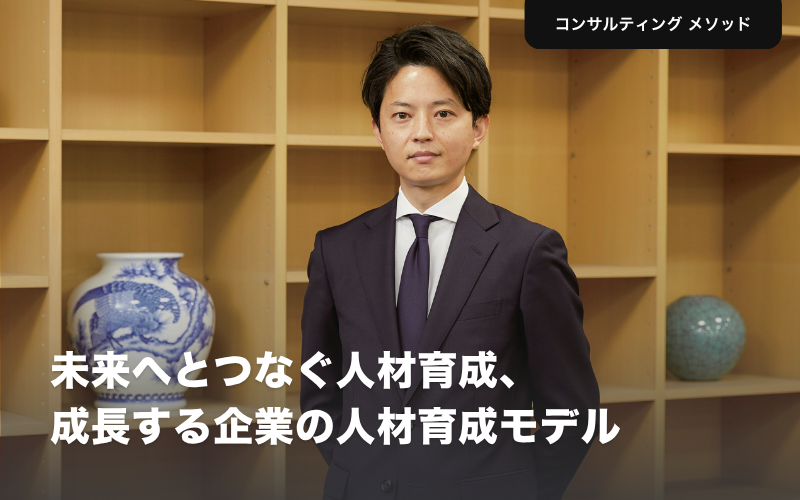なぜ今、リスキリングが重要なのか
一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブは、日本で初めてリスキリングの普及活動に特化した非営利団体です。まず、1つの問いを提示したいと思います。「働くことの見返りに、得られるものは何か」です。賃金だけでなく経験を通じたスキルも得ています。
昨今、優秀な若い人材ほど「どのようなスキルが得られるか」を重視する傾向があります。一方で、自社で働くことで得られるスキルを明確に言語化し、発信できている企業は多くありません。ここに、人手不足に悩む企業と求職者との間にある認識のギャップが見て取れます。
英国のある携帯電話会社が、「従業員にどのようなメッセージを発信するとリスキリングへの意欲が高まるか」という実証実験を行いました。経営陣が最も効果的だと考えていたのは、「テクノロジー企業へ変革するための経営戦略」というメッセージでした。
しかし、実際には、「自社で働き続けることで、デジタルの未来に対応するスキルと能力を習得できる」というメッセージの方が効果的であり、リスキリングを検討し始める従業員が14.7%も増加しました。
自社で働き続ける従業員の将来やスキルアップについて対話できることが、今後重要となります。
海外でリスキリングが浸透した背景には、AIやロボットなどの技術進化が労働力を代替する「技術的失業」との強い関係性があります。
世界経済フォーラム「仕事の未来レポート2023」(2023年4月)によると、AIなどの自動化技術の普及により、今後5年間で新たに6900万件の雇用が創出される一方、8300万件の雇用が消失し、差し引き1400万件の純減となる見通しです。実際に、米国では技術的失業と呼べる影響が出始めており、AI導入によりレイオフ(一時解雇)が発生すると回答した経営者が、750名中約44%を占めたという調査結果もあります。
こうした新しい雇用の流れは、日本にもやってくる可能性があります。これからは、AIやロボットと共に働く時代であり、人間側のアップデートも必要になります。だからこそ、リスキリングが今、全世界で大きな注目を集めているのです。
リスキリングに対する日本企業の誤解と課題
リスキリングとは、「DXや新たな事業戦略、組織変革を担う人材を育成するために、組織が従業員をreskillする」というのが本来の使い方です。
「学び直し」という和訳も存在しますが、リスキリングはあくまでも企業戦略として、従業員に習得してほしいスキルを学ぶ機会を提供する取り組みです。これらとは明確に区別する必要があります。
「リスキリングの機会提供が人材流出につながる」という誤解も少なくありません。若い世代ほどポジティブな影響があることが分かります。また、こうした機会提供が従業員のロイヤルティーやエンゲージメントを向上させ、結果として昇給・昇格といったキャリアアップにつながります。
つまり、リスキリングは「組織・企業が実施責任を持つ業務」であり、従業員の視点に立てば「新しいスキルを習得・実践し、新たな業務や職業に就くこと」なのです。
リスキリングの実践ステップは、①マインドセット、②学習、③スキルアップ、④キャリア形成の4段階で構成されます。特に「学んだスキルを実践する」段階に日本企業特有の課題が存在します。習得したスキルを新しい仕事で生かす機会があってこそ、スキルは定着し、企業の成長推進力となります。その機会がない「学びっぱなし」の状態は、転職を考えるきっかけにもなりかねません。
リスキリングは言わば「もろ刃の剣」であり、企業は新しいスキルを学ぶ機会と、それを社内で生かすチャンスや適切な配置転換を、必ずセットで提供する仕組みを構築する必要があります。
チャンスは「グローバル&デジタル」にある
リスキリングで成功している石川樹脂工業の取り組みを紹介します。
同社は、ロボットを導入。従業員がロボットを動かすプログラミングスキルを学習し、製造プロセスの自動化に成功しました。また、端数製品の販売をAmazonで開始。女性社員を抜てき、eコマースをゼロから学習し、BtoCの新事業は売上高の10%超を占めています。
さらに、「ARAS(エイラス)」という食器の自社ブランド化を推進し、本業に肩を並べるまでに成長しています。成功の理由は、経営者が自らリスキリングに取り組み、社員はもちろん、外部人材も巻き込んでともにリスキリングを推進したことにあります。
「これからどのような分野にリスキリングをすれば良いか」と考える企業には、グローバルとデジタル分野のリスキリングを提案しています。グローバル市場は成長分野であり、デジタルを上手に活用し、販売することで企業変革のチャンスです。
私はいつも、「リスキリングは三方良し」と伝えています。成長事業を担う人材が成長し、売り上げや利益が増大し、従業員の給与も向上する。海外企業においては、リスキリングの仕組みをつくることが採用募集時の最大のアピールポイントになります。
人間とAI・ロボットが共に働く時代になる中、DXに必要な従業員の人材育成、成長を支えていくリスキリングにぜひ取り組んでいきましょう。

早稲田大学政治経済学部卒業後、1995年に富士銀行(現みずほ銀行)入行。営業、マーケティング、教育研修事業を担当。2001年に米・ニューヨークへ移住後、グラウンドゼロの救済ボランティアに参加。2002年にグローバル人材育成を行うスタートアップをニューヨークで起業。2008年に帰国後、2011年に米・社会起業家支援NPOアショカの日本法人を設立。米国フィンテック企業の日本法人代表、通信ベンチャーの国際部門取締役を経て、アクセンチュアにて人事領域のDXと採用戦略を担当。2019年にAIスタートアップのABEJAにて事業開発、AI研修の企画運営、シリコンバレー拠点を設立。2021年に日本初のリスキリングに特化した非営利団体である一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。主な著書に、『自分のスキルをアップデートし続けるリスキリング』(2022年9月、日本能率協会マネジメントセンター)。