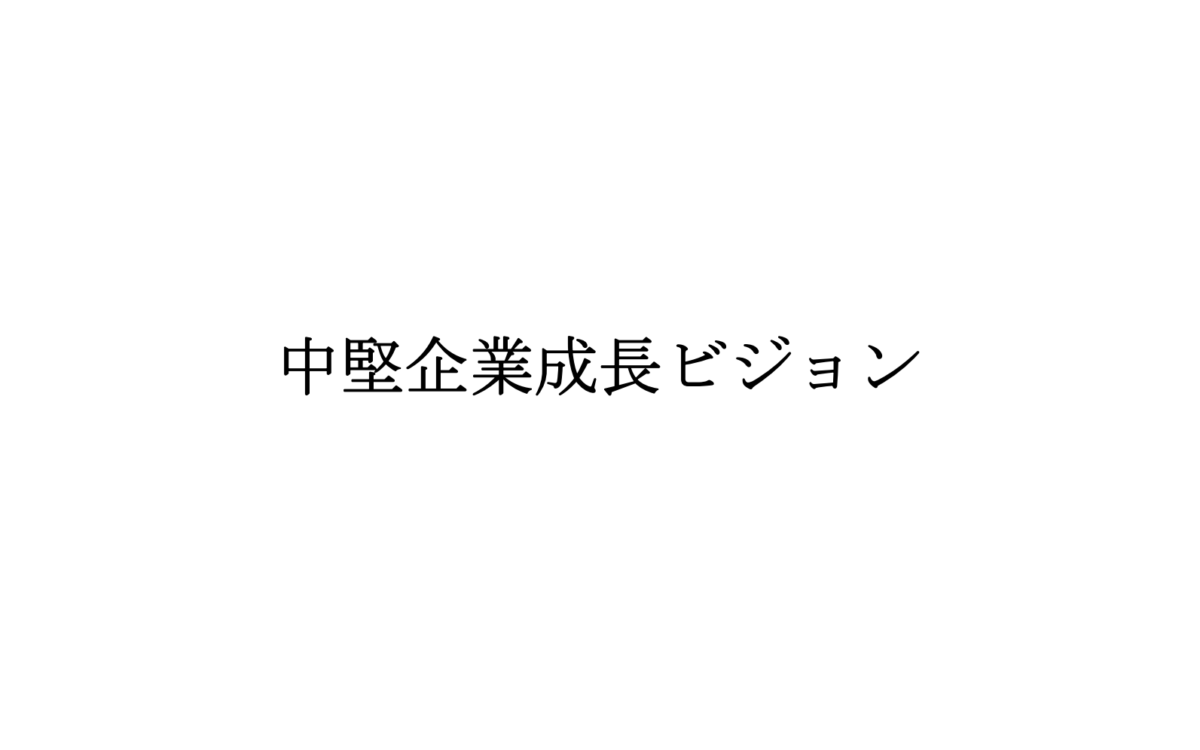「中堅企業成長ビジョン」について、前編ではその全体像を解説した。具体的には、同ビジョンが掲げる目標(KGI・KPI)、業種ごとの成長パターンと官民で取り組むべき課題について取り上げた。
今回は後編として、中堅企業が自律的に成長していくために必要な環境について掘り下げていきたい。具体的には、次の2つのポイントに分けて整理する。
1つ目は「中堅企業の成長ビジョンとガバナンス」、そして2つ目は「中堅企業を支える伴走支援者のノウハウやマッチング精度を高度化・普遍化するための仕組み、いわゆる“ソフトインフラ”」についてである。
特に2つ目のソフトインフラについては、多くの経営者にとって身近な課題が含まれているのではないだろうか。例えば、①資金調達、②人材確保、③M&A、④イノベーション、⑤海外展開、⑥専門家活用、⑦GX・DX、といったテーマである。
これらは、どれも中堅企業が成長していく上で避けて通れない重要なテーマである。しかし、これらの課題にどう向き合い、どのように解決していくべきか、具体的な道筋が見えずに悩んでいる経営者も少なくないだろう。
本コラムではこれらの課題を整理し、それぞれに対して官民でどのように取り組むべきかを考察する。本記事が経営者の皆さんが次の一歩を踏み出すためのヒントとなれば幸いである。
目次
1.中堅企業の成長ビジョンとガバナンス
成長ビジョン
ガバナンス
2.伴走支援・ソフトインフラを活用しよう
経営課題①:資金調達
経営課題②:人材確保
経営課題③:M&A
経営課題④:イノベーション
経営課題⑤: 海外展開
経営課題⑥:専門家の活用
経営課題⑦: GX・DX
中堅企業の成長ビジョンとガバナンス
【成長ビジョン】
中小企業から中堅企業へ成長する過程で、これまで経営者の経験や現場の勘、暗黙知によって対処できていた課題が、次第にそれだけでは対応しきれなくなる場面が増えてくる。
こうした状況においては、経営管理手法(ビジョン・パーパス策定、社外の知見の取り込み、CXO 設置・分業化、業務の形式知化・標準化、グループ・事業部・複数拠点管理など)を駆使した、組織能力を用いた対処が必要になる。
これらは、経営者一人の力だけではなく、組織全体の能力を高めることで初めて実現できるものである。
しかしながら、持続的に企業価値を高めるための長期的な成長ビジョンや、それを実現するための経営体制が整備されていない企業も少なくない。その結果、資金や人材といった経営資源の獲得や、それらを有効に活用することに苦戦するケースが見受けられる。こうした状況を踏まえると、中堅企業にとっては、経営者自身の能力向上に加え、成長ビジョンと経営体制の整備が重要な経営課題となる。
中堅企業の持続的成長には、まず成長ビジョンや経営体制をしっかりと整備することが必要である。その上で、ステークホルダーに対して積極的に情報を発信し、企業の成長期待を形成することが求められる。これにより、資金や人材といった経営資源を確保しやすくなるだけでなく、適切な伴走支援者を活用しながら、大胆な成長投資を実践することが可能となる。
中堅企業の経営者にとって、これらの取り組みは決して簡単なものではない。しかし、これを乗り越えることで、企業は次のステージへと進むことができる。今こそ、成長ビジョンと経営体制の整備に向けて一歩を踏み出す時である。
政府の取り組み:成長志向の企業がポテンシャルを十分に発揮し、中小企業から中堅企業、さらにその先への成長を後押しするシームレスな政策体系を構築する。
具体的には、施策対象を成長志向の企業に重点化し、先進的な経営を実践する企業の認知度を高めることで、企業の成長意欲を喚起する。加えて、伴走支援者や資本市場・労働市場等に対して成長志向の企業を可視化するため、支援企業の取り組みや成長ビジョンを広く社会に対して情報発信するとともに、企業がステークホルダーと円滑に対話するための環境を整備する。
【この章のポイント】
・中堅企業への成長過程において経営者の経験や勘だけでは対応できない課題が増えるため、組織能力を活用する必要がある。
・長期的な成長ビジョンと経営体制の整備が重要である。
・ステークホルダーへの情報発信で成長期待を形成し、資源を確保する。
関連記事:100億企業成長ポータル
【ガバナンス】
中堅企業の多くは、中小企業に比べて財務健全性が高いため金融機関からのデットガバナンスが働きづらい。また、大企業に比べて株主・投資家からのエクイティガバナンスも働きづらく、ガバナンスの機能不全が顕在化する事例も見られる。
中堅企業は、金融機関やPE ファンド・投資家など伴走支援者との中長期成長に向けた対話・関与を強めるとともに、株主だけでなく、顧客、従業員や地域社会など幅広いステークホルダーからの成長期待を集め、双方にとって有益な関係を構築することが重要である。
また、企業が持続的に成長するためには、取締役会が経営陣・取締役に対する助言や監督等の役割を適切に果たすことができるよう、独立社外取締役を活用することも有効である。
中堅企業の中には、上場企業・非上場企業、創業経営者・非創業経営者、ファミリービジネス・非ファミリービジネス、独立型・子会社型など、さまざまな経営・所有形態の企業が存在するため、最適なガバナンスは各社ごとに異なる。
しかし、企業規模の拡大とともに、所有・経営・家族の関係が複雑化する中で、ステークホルダー全体の意向に配慮しながら企業価値向上に向けて最適なガバナンスを選択することは、いずれの形態の場合も重要である。
上場企業については、コーポレートガバナンス・コードなどの指針類が整備されてきたが、ファミリービジネスに関する意思決定を行う仕組み(以下「ファミリーガバナンス」)に関する政府指針は存在せず、ノウハウも十分に浸透していない。
独立型中堅企業の過半を占めるファミリービジネスは、日本経済の成長には重要な存在である。ファミリービジネスは、一般的に、長期志向で迅速な意思決定が可能という長所を持つ。一方、経営者の独善的行動や成長意欲の減衰、革新派と守旧派の対立といった「お家騒動」による企業価値毀損、親族内後継者の経営能力不足という、短所となり得るリスクを有する。
中堅企業への成長過程において、事業承継や外部資本受入・上場などの経営体制の転換点を迎えると、「経営と所有」や「監督と執行」の分離が徐々に進展し、経営者、所有者である株主、相続権を有する創業家も含めた関係性が複雑化する。そのため、ファミリービジネスの長所を残しつつ、短所となるリスクに適切に対処するファミリーガバナンスが、中堅企業の成長に必要不可欠となる。
政府の取り組み:ファミリービジネスの中堅企業が、長期志向や迅速な意思決定といった長所を生かしつつ、成長意欲減衰やファミリー内の対立などのリスクに適切に対処しながら成長を目指すためのファミリーガバナンスを構築するための規範を策定する。
【この章のポイント】
・中堅企業の多くはデットガバナンスやエクイティガバナンスが弱く、機能不全が起こりやすい。
・金融機関や投資家との対話を強化し、幅広いステークホルダーと関係を構築する。
・ファミリーガバナンスを整備し、長所を生かしつつリスクに対応する。
伴走支援・ソフトインフラを活用しよう
中堅企業の7つの経営課題とポイント、政府の取り組みについて、以下のようにまとめた。
【経営課題①:資金調達】
中堅企業は、中小企業や大企業と比較して無借金経営の企業が多く、高い資金調達ポテンシャルを持つ。一方で、金融機関を含む支援機関間の地域や国を超えた連携が未発達であることなどが原因で、最適なファイナンス手法や支援ノウハウを有するパートナーを選択できず、支援機関間の空隙が生まれている。
その結果、支援機関からの資金調達や、使途に関する適切な提案・助言が行き届かず、海外展開やM&A、長期にわたる大規模投資などの非連続な成長機会の資金調達ポテンシャルが充分に満たされていないケースも存在する。
こうした課題に対応し、金融機関・ファンドなどの伴走支援者が非連続な大規模成長投資を支援するため、政府は中堅・中小大規模成長投資補助金などを通じ、他の企業にも再現性のある中堅企業の成長経路のモデルケースを創出。融資やファンド活用も含めたファイナンス手法の高度化を図り、段階的に支援規模を縮小しつつ、幅広い企業が市場において資金調達が可能になる環境の構築を目指すという。
未上場の中堅企業であっても、出資の活用は企業価値向上の観点で有効であり、資金調達の観点だけでなく、経営パートナーとしてPE ファンドなどを活用する余地が大きい。
上場中堅企業の場合、株主・投資家からの働きかけ(エンゲージメント)も成長のために有用になり得るが、現状、中長期の成長に貢献するエンゲージメントファンドは、規模・数ともに不足している。
政府の取り組み:中堅企業向けの新興エンゲージメントファンドの創出や、PEファンドによるM&Aや事業承継支援の好事例を集約し、「エクイティ活用ガイドブック(仮)」を作成する。
また、コロナ禍で債務が重荷となっている中堅企業に対し、GX・DXなどの変化に対応しつつ、倒産や技術・人材の散逸を防ぐため、金融負債の整理を通じた早期事業再生を支援する制度基盤を整備する。
【資金調達のポイント】
・中堅企業は無借金経営が多く、資金調達ポテンシャルが高いが、支援機関間の連携不足が課題。
・非連続な成長投資(海外展開、M&A、大規模投資など)の資金調達が十分に進んでいない。
・PEファンドやエンゲージメントファンドの活用が有効であり、出資を経営パートナーとして活用する余地がある。
【経営課題②:人材確保】
中堅企業は、規模拡大とともに現場人材の不足感が強まる。また、中小企業段階では経営者個人が管理・外注していた機能の内製化に伴い、コーポレート機能を備えるための経営人材(後継者候補、番頭人材など)および専門人材(ファイナンス、マーケティング、HR、DX、海外事業関連など)の確保・育成 が必要になる。
人材確保・育成に関する手段も多様化・高度化しており、さまざまな民間サービスが利用可能だが、中堅企業における人手不足感は根強く存在している。
大企業ではポテンシャルを十分に発揮し切れていない経営人材および専門人材が、中堅企業に移動して活躍できる余地は大きい。それにも関わらず、特に都市部から地方部への転居を伴う場合、大企業から中堅企業などへの人材の流れは必ずしも大きくない。
背景には、中堅企業などの求人情報の掘り起こしやマッチングに手間がかかるために、人材仲介サービス、特に、単価が安い兼業・副業の場合の人材仲介サービス企業にとっての採算性が低く普及が進まないこと、求人企業と求職者が希望する賃金水準のギャップが大きいこと、中堅企業などが成長ビジョンや人材投資方針を十分にアピールできていないこと、などの課題がある。
このミスマッチを解消するためには、日頃から中堅企業の経営状況を理解した上で成長ビジョン実現に必要な経営支援を行う、金融機関の役割が重要になる。そして、金融機関や人材仲介会社の仲介機能が向上し、中堅企業への経営人材・専門人材の流れが定着することを目指し、一定規模の実績を積み上げる必要がある。
より長い時間軸の中では、中堅企業が、成長ビジョンと連動した人材戦略を策定し、教育機関等と連携して、経営人材も含めた人材育成に取り組むことも重要である。
政府の取り組み:金融機関や人材仲介会社を伴走支援者として、中堅企業の経営人材・専門人材の獲得を支援する。また、省力化投資による労働生産性向上を促進し、賃上げを伴うモデルケースを普及させる。
さらに、人的資本経営を通じた給与水準の向上や人材育成を後押しし、労働市場への情報発信を支援する。
【人材確保のポイント】
・現場人材や経営人材、専門人材の不足が課題である。
・中堅企業の求人情報の掘り起こしやマッチングが進まず、都市部から地方への人材流動も限定的。
・金融機関や人材仲介会社の仲介機能を向上させ、人材戦略を策定する必要がある。
【経営課題③:M&A】
中堅企業にとって事業の成長、すなわち販路拡大、人材や資産の獲得の有効な手段の一つが、他の企業や事業の合併、買収、事業譲渡など(M&A)である。経営力が高い企業によるM&A を通じて、買収する側の経営資源の補完だけでなく、買収される側の事業の合理化等による労働生産性の向上、成長分野への円滑な労働移動が実現され、日本経済全体の労働生産性の向上になる。
また、後継者不足による中小企業の倒産や廃業が進む中、M&A は、中堅企業の経営資源の散逸を防ぎ、雇用を維持する意義もある。
しかし、中堅企業では成長戦略としてM&A を位置付けることは一般的ではなく、M&A の実施も大企業に比べ低調である。さらに、買収先企業とのシナジー効果を発揮する上での肝となる、買収後の経営方針や業務、企業文化の統合といったプロセス(PMI)の実施は、わずかに留まっている。
中堅企業にM&A が経営拡大の有力な手段として普及していくには、買収先の価格やリスクの評価(デューデリジェンス)や売り手・買い手のマッチング、PMI が相応の価格で提供されることや、M&A を選択肢とする売り手側企業が増えること、中堅企業へのファイナンスの充実が求められる。
このような課題を踏まえ、M&A 事業者、PE ファンド、金融機関といった伴走支援者は、手数料の透明化、利益相反の禁止、経営者保証の解除など、健全な市場環境整備のために必要な事項に留意の上、M&A 後の成長を実現するサービスを提供する必要がある。
政府の取り組み:中堅企業におけるM&A が普及するまでの間、中堅・中小グループ化税制といったインセンティブを通じ、買い手・売り手双方の生産性向上や賃上げを実現するM&A を後押しする。さらに、社会全体として望ましい経営資源の集約を阻害する、買い手側・売り手側双方の課題の所在を明らかにし、解決していく。
【M&Aのポイント】
・中堅企業におけるM&Aは、成長や経営資源の補完、労働生産性向上の手段として有効。
・PMI(買収後の統合プロセス)の実施が不十分であり、M&Aの普及が進んでいない。
・デューデリジェンスやマッチング、PMIの支援体制を整備する必要がある。
【経営課題④:イノベーション】
中堅企業、とりわけ製造業では、研究開発に積極的な企業ほど付加価値額が高く、ニッチ分野のコア技術を強みに周辺技術の獲得やローカライズ化を進めることで成長につなげており、研究開発や新事業展開は成長の重要な要素である。
中堅企業は、大企業とは異なり研究開発や新事業展開に必要な人材・設備・技術を自社で保有することは難しい。一方で、スピーディーに経営判断を行いやすく、外部との機動的なオープンイノベーションの素地を備えている。他方、取引先、大学・公的研究機関、スタートアップや知的財産(以下、知財)などの専門家との連携に関して、適切なパートナーに巡り会えていない現状にある。
政府の取り組み:中堅企業の研究開発や新事業展開を後押しするため、税制の活用やイノベーション促進策を検討するとともに、大学や公的研究機関との連携を強化する。
また、NEDOや産業技術総合研究所が研究機関間の結節点として中長期目標を設定し、知財活用や標準化制度を通じて中堅企業の先端技術の活用を支援する。
【イノベーションのポイント】
中堅企業は研究開発や新事業展開が成長の鍵だが、必要な人材や設備の確保が難しい。
外部とのオープンイノベーションの素地はあるが、適切なパートナーとの連携が進んでいない。
大学や研究機関、スタートアップとの連携を強化し、技術や知財を活用する必要がある。
【経営課題⑤: 海外展開】
各業種の中堅企業の輸出実施企業比率は中小企業の倍以上であり、海外売上比率が高い中堅企業は、労働生産性も高い。
さらなる成長に向けて、国内か海外か、国内で高付加価値型の製品・サービスを生み出し、輸出やインバウンドも含めて、海外需要向けのローカライズに対応しながら商圏を拡大し、企業価値を向上させていくことが重要である。
商社や越境EC、日系企業向けの輸出のみならず、新規に海外顧客を獲得し、現地に生産・販売拠点も有する段階になれば、市場分析も含めた海外展開戦略の策定、法務・税務対応、現地パートナー探しといった課題に対応する必要がある。
政府の取り組み:
JETROを中心に中堅企業の海外展開支援を強化し、ハンズオン支援の対象拡大や支援機関間の連携体制を構築する。
また、NEXIは貿易保険を中堅企業向けに拡大し、JBICは地域金融機関と連携して海外展開を支援する。さらに、中堅企業を先導役として中小企業と共に海外市場を開拓する取り組みを推進する。
【海外展開のポイント】
・中堅企業の輸出実施比率は中小企業の倍以上であり、海外展開は成長の重要な手段。
・海外市場での商圏拡大には、現地拠点の設置や法務・税務対応、パートナー探しが課題。
・市場分析や戦略策定を進め、海外展開を支援する体制が必要。
【経営課題⑥:専門家の活用】
中小企業ではSaaSなどの均質のサービスで経営課題の多くが解決できる一方、中堅企業は規模が拡大するにつれて業態や展開地域が広がり、経営課題の幅も、金融、人材マネジメント、GX、DX、M&A、マーケティング、研究開発など、広範かつ高度なものとなり、それぞれに最適なコンサルタントや弁護士、会計士といった専門家を活用する必要がある。
しかし、このようなコンサルティングサービスは大企業向けには充実しているが、中堅企業のニーズに合う程度のサービスの提供は十分とは言えない。専門家も都市部に集中しており、中堅企業は経営の軸足を地方に置く割合が高いがゆえにアクセスが限られるなど、ミスマッチを解消する必要がある。
コンサルティング企業や士業の専門家には、中堅企業が求める成果に見合う報酬でのサービス提供や、ハンズオン型のファンドに代表されるように、中堅企業に出資などの形で関与し、経営改革の実践を通じて企業価値を上げて報酬を得る成果連動型サービスの拡大が期待される。
政府の取り組み:地域円卓会議を起点とし、地域特性と多様な業種及び課題に対応できる専門家のネットワークを構築する。さらに、地域特性に応じた適切なKPI を設定し、中堅企業からの評価や企業価値向上の実績を蓄積し、一定の能力を有する専門家を可視化することで、ユーザー側の視点が専門家サービスに反映される自立的なサイクルを確立する。
【専門家活用のポイント】
・中堅企業の経営課題は高度化しており、専門家(コンサルタント、弁護士、会計士など)の活用が必要。
・都市部に専門家が集中しており、地方の中堅企業へのアクセスが限られる。
・成果連動型サービスの拡大や専門家ネットワークの構築が求められる。
【経営課題⑦: GX・DX】
中堅企業は、GX・DXの事業環境の変化に柔軟に適応するポテンシャルを有するものの、GX・DX で大きな成果を出すためには中長期的に取り組む必要性、GX・DX を推進する人材・ノウハウ不足などの課題から、取り組みが進みづらい傾向にある。
サプライチェーンによっては、脱炭素の取り組みやデータ活用・管理の体制などが取引先から求められることもあり、こうしたリスクに直面する企業を中心に対応策を講じる必要がある。
また、DX は、デジタルツール活用による業務効率化に留まらず、ビジネスモデル変革を通じて、企業価値の向上につなげるための取り組みであるが、企業の意識向上や年々深刻化する人材不足が課題として挙げられる。
政府の取り組み:
中堅・中小企業のGX推進のため、CO₂排出量の見える化や省エネルギー設備導入支援、地域での支援体制構築を進める。
DX推進では、デジタルガバナンス・コードや支援機関向けガイダンスを活用し、優良事例を広げる。さらに、デジタル人材育成のため、教育コンテンツの一元化やデジタルスキル情報の可視化に取り組む。
【GX・DXのポイント】
・GXやDXの推進が成長に不可欠。
・人材やノウハウ不足、意識の低さが課題であり、取り組みが進みにくい状況。
・ビジネスモデル変革を目指し、デジタル人材の育成や支援体制の整備が必要である。
中堅企業成長ビジョン(中堅企業等の成長促進に関するワーキンググループ策定) は、中堅企業に焦点を当てた日本初の国家戦略である。このビジョンでは、中堅企業が直面するさまざまな課題が明らかにされており、それらに対する具体的な施策を着実に進めていくことが重要である。
さらに、このビジョンは、中堅企業の課題を体系的に解きほぐす初めての試みでもある。そのため、大学や研究機関といった外部の知見を積極的に取り入れながら、課題の継続的な分析を進めていく必要がある。こうした取り組みを通じて、中堅企業が持続的に成長できる環境を整備していくことが求められる。