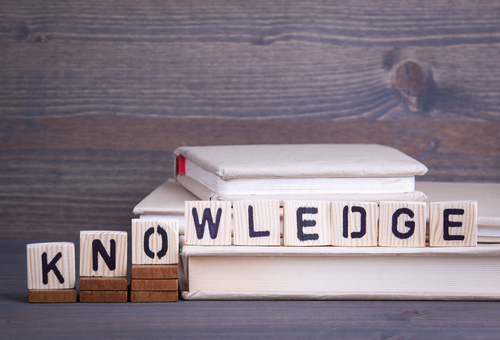ブレイン 「がん細胞診断支援システム」
大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで、ブレインは4月13日の開幕日からの8日間、がん細胞診断支援システムを紹介するブースを出展した
すでに存在するものに光を
何を手掛かりに新たな商品の開発に臨むか。企業の経営者や企画担当者、マーケッターにとって、これはもう極めて大きなテーマと言って良いかもしれません。
世の中に存在する課題を解決できるような商品を創出できれば大ヒットを呼び込めそうですが、そもそも、どのような課題があるのか、それを抽出するのも大変です。
1つのヒントとなりそうなのは、「すでにそこにあるもの」に光を当てて生かす、という考えかもしれません。自らの会社にある技術、あるいはそうでなくても、社外にある素材などです。
この連載でこれまでに紹介してきた事例から2つ、あらためて簡単におさらいしてみましょう。
例えば、東京・港区の松本商店(本誌2024年11月号)は、京都の呉服商の蔵に眠ったままで行き場を失っていた和服用の反物を活用したトートバッグの開発に挑んでいます。これによって、和装市場の縮小で元気を失いつつあった呉服商や職人たちとの新たな協業の場をつくり上げると同時に、消費者に和服の生地の美しさを手軽に体感してもらえる機会を提供できています。
福井市のサカセ化学工業(本誌2025年4月号)は、病院向けのカート・キャビネットの市場でシェア70%を獲得している企業です。同社は、全国各地に数々ある病院に横たわる課題を、営業活動を通して発見しました。カートやキャビネットの既製品を提案しても、病院に対しては絶対に高い満足度をもたらせないと気付いたのです。病院内でのカルテや薬、手術用の道具といった物の流れは病院によって千差万別だったからです。
そこで同社は、病院ごとに商品の仕様を細かく変えて納入する方針を掲げます。樹脂、金属、木材それぞれの加工を、同社が全て内製できる「町工場の集合体」とも言える体制を取っていたのを生かしたのです。
病理医の悩み
ここからが今回の本題です。兵庫県のブレインは、設立から40年のコンピュータシステム研究・開発に携わる企業です。
同社が2017年から開発を続けているのが、AI(人工知能)によるがん細胞診断支援システムです。これまでは、病理医が顕微鏡で撮った画像を1枚ずつ、目で確かめながら、がん細胞の有無を判断していました。その作業を助けるシステムがこれで、画像識別を短時間のうちにAIで行うことによって、病理医の診断を助ける力になれると言います。すでに一部の医療機関でテスト運用を進める段階にまで到達していると聞きました。
同社の社長である神戸壽氏によると、「がん細胞の診断は病理医にとって根気を要する仕事だった」そうです。頑張っても1日に50例を診るのが限界で、集中して臨めるのは2時間が良いところ。しかし、このシステムを用いることで、これを1日200例まで可能にしようと目指し、実際にその域にほぼ達しているそうです。
まさに、世の中に存在する課題を救うシステムと表現できると私は感じましたが、このシステムを開発する契機が実に興味深いものでした。
話はいったん、がん細胞とは全く異なるところに飛びます。
2013年、ブレインは「世界初」とうたった、ある商品を世に送り出します。それは、パン専用のレジでした。ベーカリーでは、販売するパンの種類をスタッフが覚える作業がとても大変だった。しかし、同社のレジは、顧客がトレーに乗せて運んできたパンを瞬時にスキャンして、カレーパンやデニッシュといった商品を識別。たやすく会計できるというシステムです。
これもまた、まさしく課題解決型の商品ですね。発売から4年ほどたったころ、このパン専用レジの特性の面白さと便利さを、関西のテレビ局が番組で特集を組んでくれたそうです。
きっかけは1本の電話
話が急展開したのは、ここからでした。その番組を偶然観た1人の病理医が、ブレインに電話をかけてきたそうです。
その病理医はこう話したと言います。「パンが、がん細胞に見えました」。どういうことか尋ねると、微妙に形の異なるパンたちの姿を見分けていくレジの仕組みは、病理医の目でがん細胞を識別する仕事に似ているというのですね。そして、その仕事は実に大変なのだとも話してくれたそうです。
そんな会話を交わしていく中で神戸氏は、この病理医とともにがん細胞師団支援システムを共同開発しようと決意します。
ただ、ここで私などは思うのですが、パンとがん細胞では違う部分もあるのではないかとも気になります。そもそも大きさに差がありますし、がん細胞の診断支援となると、患者さんの生命にも関わってきますから、診断支援の精度が極めて重要になってきます。
その点を神戸氏に聞いたところ、意外な答えが返ってきました。
「パンとがん細胞は、ほぼ一緒でした」。システムを開発する上で、両者の違いが大きなネックにはならなかったというのですね。神戸氏はさらに言います。「ベーカリーなどが扱うパンは通常100種ほどです。それに対して、がん細胞の大きな特徴は5つでした」。がん細胞が異なるのは、白血球などが一緒に写り込むこと。それらをどう取り除いて判断させるかが、いわば勝負どころであったそうです。
2022年に膀胱がんの細胞診断支援システムが完成。2025年には子宮頸がんの細胞診断支援システムも確立できました。そして現在は、肺がんの分野の開発に着手しているそう。
学会で大きな反響
がん細胞診断支援システムは、すでに一部の医療機関でテスト運用に入っているほか、医療関連の学会でも大きな反響を呼んでいると聞きます。
「私たちの会社が学会に参加して良いのかと躊躇しましたが、『使ってみたい』との声がいくつも届きました。国際的な学会で講演するという機会にも恵まれ、「私たちにも学会での出番はあるのだと感じました」と神戸氏は振り返ります。
話を整理しましょう。ブレインはもともと、パン専用レジで「世界初」を成就していました。それはベーカリーで働くスタッフの悩みを解消したいという一念でした。そして、1人の病理医が伝えてくれた言葉を聞いただけに終わらせず、それを新たな商品開発の突端として、しっかりと生かしています。すでにあるものを用いて、さらに社外から得られた刺激を生かし切った、そうした点から大きなヒントを学べるのはないかと、私は感じました。
私がこの事例を知ったのは、大阪・関西万博の会場でのことです。4月の開幕日からの最初の8日間、期間限定で同社が出展していたのでした。万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。同社の取り組みは、社会課題の解消に向けたデザイン=解決策の明示、であると思えました。

製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門領域とする一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画する。
日本経済新聞社やANAとの協業のほか、経済産業省や特許庁などの委員を歴任。サイバー大学IT総合学部教授(商品企画論)、秋田大学客員教授。