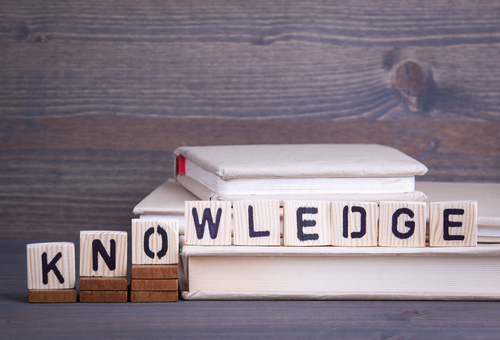大木製作所 「タワー型室内物干し」 「大木のらくらくピンチ ステンレスハンガー」
大木製作所のステンレス製の生活用品。「タワー型室内物干し(小)」は2万350円(税込み、左)「大木のらくらくピンチ ステンレスハンガー DL-2」は6490円(税込み、右)
コモディティー化にあらがう
ものをつくり続ける中堅・中小企業の経営をおびやかす要素の1つに、コモディティー化が挙げられます。企業間での技術競争がある段階まで行き着いてしまうと、機能や性能をそれ以上は磨きづらく、あとは価格面での競争しかなくなります。そうした状態に陥ることをコモディティー化と言います。
このコモディティー化はとりわけ成熟商品領域でしばしばみられる現象です。こうなりますと、「体力勝負でどうしても厳しい立場となりがちな中堅・中小企業は、市場から撤退せざるを得なくなる」という解説は、よく目にするところですね。しかし、です。コモディティー化の波にさらされた中堅・中小企業は本当に打つ手がないのか。落ち着いて少し考えてみたいというのが、今回の趣旨です。全ての企業に当てはまるかは置いておくとしても、コモディティー化にあらがって戦っている中堅・中小企業は現実に存在します。
今回はそんな1つの事例を取り上げてみたいと思います。
東京都練馬区に、大木製作所という社員数10名弱の小さな企業があります。1947年の創業から一貫して手掛けているのは、家庭用品の金物分野です。同社がとりわけ得意としているのは、洗濯物を干すハンガーや物干しといった商品群。ステンレスを素材に使ったものが主力です。
洗濯用品に注目が集まる
こうした洗濯用品というのは、それこそコモディティー化の最たるものと表現できるかもしれません。大木製作所が開発・販売するようなステンレス製の商品を選ばずとも、樹脂製ではるかに安いものが市場にあふれています。ホームセンターに行けば手軽に買えますし、ごく一般的な消費者にしてみれば、ハンガーや物干しの購入に際して吟味に吟味を重ねるという人は少数派でしょう。
加えて、町の金物屋さんは激減している状況にもあり、大木製作所が作るような商品は、販路の確保にも難儀しそうです。
そんな逆風下にありながら、「大木製作所の洗濯用品でなければ」というファンも多数付いていると聞きます。一体どういうことか。
主力商品を2つ、お伝えしておきます。1つは、「タワー型室内物干し(小)」。衣類を室内干しするための商品です。普段は小さく折りたため、本体に組み込まれたスプリングによって、軽い力で縦に広げられます。写真を見ていただくと分かるかと思いますが、端正な機能美を感じられる作りで、それもまた魅力に思えます。
ただし値段はというと2万350円(税込み)。かなり立派です。それでも、消費者からの指名買いが相次いで、ちゃんと売れている。第一号モデルは2004年発売だそうですが、現在では最初の年に比べて2倍の販売数だと言います。年を重ねるごとに、勢いが弱まるどころか、むしろ実績を伸ばしているという話です。
もう1つは、「大木のらくらくピンチ ステンレスハンガー DL-2」。ベランダなどに吊り下げて使うハンガーです。洗濯物を指で挟むところの面積が大きく、つまみやすくできています。日常的に使う商品では、こうした部分の工夫が大事になります。毎日の小さなストレスを取り除いてくれる機能は、積み重なっていくと大きな違いとして実感できるものです。こちらの値段は6490円(税込み)。やはり高い。でも、当初の目標通りに売れているらしい。
ファンをつくる姿勢を貫く
このように、家庭用品の金物分野で小さな企業が戦いを続けられています。しかも、価格帯は高いにもかかわらず、です。同社の社長である大木和利氏に話を聞くと、そこにはそれ相応の理由があると理解できました。
まず、同社の販売戦術です。セレクト系の通販チャネルを主軸に据えていると聞きました。そう知って、これは絶妙な判断であるなあと思いました。
安価な樹脂製商品の価格競争とは距離を置けるというのが1点。次に、一般の量販店を販路に選ぶよりも固定ファンを創出しやすいという点です。セレクト系の通販チャネルに消費者が求めるのは、安さにもまして商品の独自性であると考えられるからです。
大木氏は言います。
「大木製作所のファンを1人でも多くつくる、というのは一貫したテーマです」
それがあっての販路選択であったわけですね。そして、この判断が正しかったことは、商品の売れ方を見ても確かなところです。
商品開発の側面からは、どのようなことが見てとれるか。大木氏は「長くじわじわと売れる商品づくりを意識している」と話します。ぱっと開発して売り切る戦術とは真逆であるということ。中小企業である同社にとって、これもまた大事ではないかと感じさせます。ただし、大手どころの企業が同社の後追いをしてくるケースもあるため、細部の仕様の改良を重ねることで、商品特性面での優位性を保ち続けられるよう意識しているとのこと。
今回取り上げた商品は、いずれもデザイン性に優れていると思わせますが、そのデザインは社員が担っていると聞きました。10名弱の会社でありながら、デザインを担当する社員を擁しているのですね。その社員は「デザインは極力シンプルに、そしてステンレスの弱点とも言える切り口部分の処理を美しくすること」を大事にしているそうです。また、ステンレス素材は原価の高いものをためらわずに選ぶことで、後追い商品に対するアドバンテージを保つようにしているらしい。
機能面だけでなくデザイン面にも抜かりなく注力することで、ファンをつかんでいるのだと理解できます。
最後に、同社の商品はアフターケア対応もしっかりとうたっています。「うちは逃げませんから」と大木氏は笑います。小さな修理にもすぐに応じるとのことですし、普通に使用すれば、今回の2つの商品は「最低10年は使えます」と大木氏は力説します。
成熟商品でも進化を目指す
これらから、大木製作所の商品は、いわゆる「過剰品質志向」だと分かります。そこまでやるか、という過剰品質志向は企業にとって悪手ではないのか。私はそうは思いません。
過剰品質は、中堅・中小企業のものづくりにおいて大きな武器となるのではないかと感じることが、しばしばあります。「メガヒットを飛ばす必要まではない、確実に一定の愛用者をつかむことができれば事業は存続できる」という規模の企業にとっては、過剰品質によって商品の独自性を創出することが、実は賢明と理解できる事例は、同社以外にもたくさんあります。
大木氏は最後にこう話しました。
「成熟商品の領域であっても進化は果たせますし、何より進化を目指すことで、この会社は生きていけます」
少なからぬ経営者層や商品開発担当者にとって、とても励みになる言葉であると私には感じられました。

製品・サービスの評価、消費トレンドの分析を専門領域とする一方で、数々の地域おこしプロジェクトにも参画する。
日本経済新聞社やANAとの協業のほか、経済産業省や特許庁などの委員を歴任。サイバー大学IT総合学部教授(商品企画論)、秋田大学客員教授。