持ち株会社制への移行を実施(表明)する上場企業が最近、相次いでいる。中でも話題を呼んだのがソニーグループ(2021年4月に社名変更、以降ソニーG)とパナソニックだ。ソニーGは、グループ本社機能と事業運営機能を分離して事実上の純粋持ち株会社(自ら事業は行わず、株式を持つグループ各社の監督機能に特化した会社)に移行。パナソニックも2022年4月に社名を「パナソニックホールディングス」へ改め、持ち株会社制へ移行する。
日本企業で初めて事業部制を採用(1933年)したパナソニックと、日本企業で最初にカンパニー制を導入(1994年)したソニーG。日本における組織改革の先駆者がそろって持ち株会社制へ移行したインパクトは大きい。今後は企業規模や上場・非上場にかかわらず、ホールディングカンパニー(持ち株会社)を設立する動きが国内で活発化するとみられている(ちなみに日本初の純粋持ち株会社は1999年発足の「大和証券グループ本社」)。
持ちただ、持ち株会社化への流れは最近に限った話ではない。経済産業省が毎年実施している「企業活動基本調査」によると、親会社が持ち株会社である企業の割合は2018年度時点で33.1%と、リーマン・ショック直後(2009年度=13.1%)から2.5倍に伸びた(【図表1】)。つまり企業の3社に1社は持ち株会社の傘下にあることになる。内訳は「純粋持ち株会社」が8.5%(2532社)、監督のほか自らも事業を営む「事業持ち株会社」が24.6%(7325社)だった。
【図表1】親会社が持ち株会社の企業割合
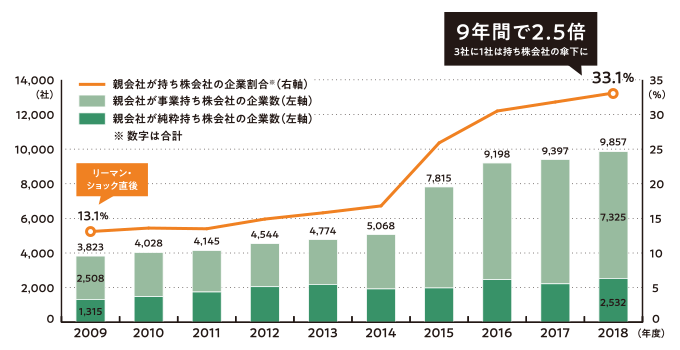
※有効回答企業全体(親会社がない企業を含む)に占める割合
出所:経済産業省「企業活動基本調査(確報)」よりタナベ経営作成
持ち株会社化を図る企業が近時に増えた背景として、大きく次の3つが挙げられる。「M&Aの推進」「意思決定の迅速化」「後継者人材の育成」である。それぞれ現状を見ていこう。
まず、新規事業の獲得や既存事業の底上げを狙ったM&Aが増えている。レコフデータの調べによると、M&A件数は2019年(4088件)に過去最高を更新。2020年(3730件)もコロナ禍の影響で減ったものの、高水準である(【図表2】)。「中小企業白書(2021年版)」によると、買い手企業がM&Aを検討したきっかけや目的として「売上・市場シェアの拡大」が最も高く、「新事業展開・異業種への参入」が続いた。他社の経営資源を活用した業容拡大や事業多角化を目指す様子がうかがえる。(【図表3】)
【図表2】M&A件数の推移
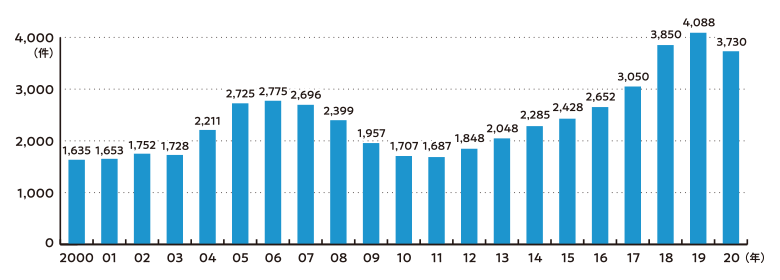
※レコフデータ調べ 出所:中小企業庁「中小企業白書(2021年版)」
【図表3】買い手としてのM&Aを検討したきっかけや目的
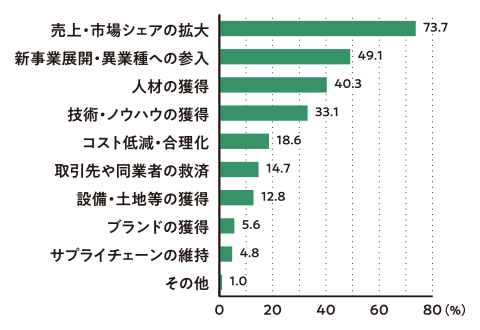
※複数回答、n=1,341 出所:中小企業庁「中小企業白書(2021年版)」
M&Aでは、複数の企業が共同の親会社となる純粋持ち株会社を新設し、その傘下に入る「経営統合」がよく行われる。人事制度や賃金水準、情報システム、社内風土などが異なる企業同士を1つの法人に集約する「吸収合併」と比べ、純粋持ち株会社による経営統合は各企業が独立性を維持できるため、統合がスムーズで混乱も少なくスピーディーにシナジー効果を発揮できる。
また、2021年3月1日に施行した「株式交付制度」も、企業に持ち株会社化を促す追い風になるとみられる。同制度は自社(買い手)が他社(売り手)を子会社化する場合、売り手の株式を譲り受ける対価として、現金の代わりに自社の株式を交付できるというものだ(【図表4】)。従来の「株式交換制度」でも自社株を対価とする企業買収は可能だったが、買収対象を完全子会社(100%子会社)化する場合に限られ、しかも対象会社での株主総会(特別決議)を必要とするなどの制約があった。新制度では売り手会社の一部の株式取得(議決権50%超100%未満)も可能で、事業再編がさらに行いやすくなる。
【図表4】株式交付制度
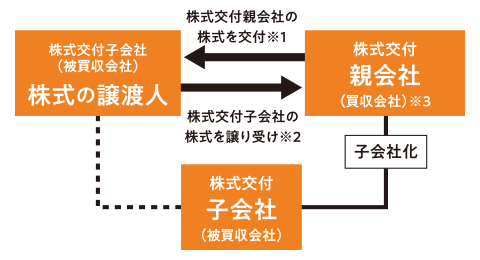
※1 株式に加えて株式以外の金銭等を交付することもできる。
※2 株式と併せて新株予約権等を譲り受けることができる。
※3 株式交付親会社(買収会社)においては、株式交換等と同様に、株式総会の決議、債権者異議手続き等をとる。
出所:法務省パンフレットを基にタナベ経営作成
経済産業省が公表したアンケート調査結果によると、日本企業の取締役会は「個別の業務執行」に関する議題に平均して7割近く(69.4%)の時間を割いており、中長期の経営戦略・経営計画のために使っている時間は全体の2割に満たない(17.4%)とされる。(【図表5】)
【図表5】取締役会全体の議題別検討時間の割合
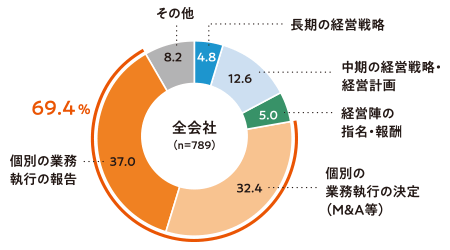
出所:経済産業省「社外取締役に関するアンケート調査結果」(2020年7月31日)
現在は、経済環境が高速化・複雑化かつグローバル化しており、目先の業務に関する経営判断が多く求められるようになった。一方で、通常の企業の取締役会は取締役の業務監督に加え、業務執行の決定に関する機能を持っている。監督と執行を兼ねているため、取締役会では個別の業務執行に関する議題の検討と決議に多くの時間が割かれ、中長期的な経営方針やグループ全体の戦略策定は遅れがちになる。
純粋持ち株会社の設立は、個々の事業に関する権限をそれぞれグループ会社に委譲することで、本社(ホールディングカンパニー)はグループ経営に集中できるメリットがある。一方、各グループ会社はそれぞれが担当する事業に専念し、自らの裁量で業務を遂行できるため、グループ全体の意思決定が迅速になる。
経産省の別の調査(「企業活動基本調査速報(2019年度)」)を見ると、子会社(関連会社を含む)全体に占める完全子会社(出資比率100%)の割合は年々増加(1994年度:42.1%⇒2019年度:60.7%)している。一方、出資比率20%以上~50%以下の関連会社の割合は年々減少(34.0%⇒18.7%)している。(【図表6】)
【図表6】国内企業の子会社・関連会社の出資比率推移
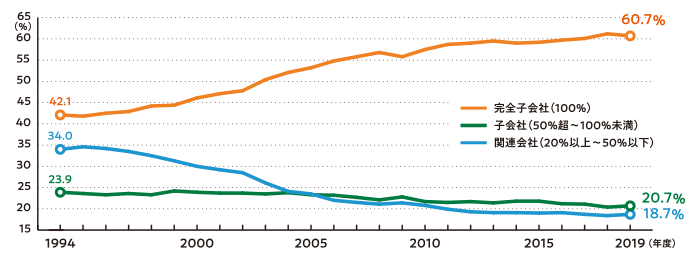
出所:経済産業省「企業活動基本調査速報(2019年度実績)」(2021年3月31日)
親会社主導による意思決定の迅速化を図るため、株式移転(単独または複数企業が全発行済み株式を新設する持ち株会社に移転し、それぞれが完全子会社になること)や株式交換(被買収会社の株主に対価として買収会社の株式を交付し、完全子会社化すること)により純粋持ち株会社制への移行を進める企業の動きが見て取れる。
帝国データバンクの調べによると、全国企業の「後継者不在率」(2020年)が65.1%と3年連続で低下した。しかし、3社に2社は後継者がいないという状況に変わりはない。
一方で、近年の事業承継は同族承継が減少傾向にあり、2020年は同族承継(34.2%)と内部昇格(34.1%)の割合がほぼきっ抗している(【図表7】)。今後は少子化の影響もあり、従来の主体だった親族承継から、親族外承継へとシフトしていくことは明らかである。
【図表7】近年に事業承継をした経営者の就任経緯
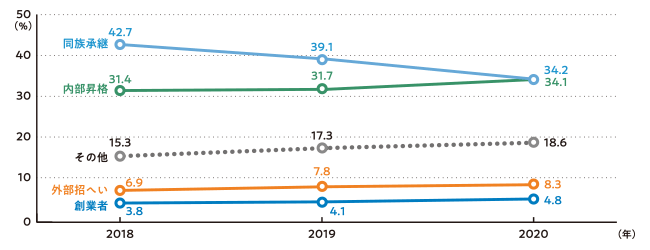
※「その他」:買収・出向・分社化の合計値
出所:帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査(2020年)」
事業承継は、後継者人材の発掘から育成、候補者の絞り込みに至るまで長期間を要する。そのため、できるだけ早いうちに組織経営の実務経験を積ませる必要がある。そこで、親族外から後継者人材を発掘し、早期育成を図る手段として持ち株会社制の活用が有望視されている。
例えば、純粋持ち株会社を新たに設立して本社の管理部門を移行するとともに、社内の事業部門を完全子会社として傘下に切り出し(新設分割)、有望な人材をそれぞれのトップに据えて経営実務に当たらせ、後継者人材を育成する企業が増えている。
また、後継者不足のために事業売却を志向する企業も多い(【図表8】)。通常の企業グループの支配下に入るよりも、純粋持ち株会社制を導入している企業の事業子会社になった方が、事業方針の裁量範囲が広いため社内の抵抗感も抑えられる。
【図表8】売り手としてM&Aを検討したきっかけや目的(複数回答)
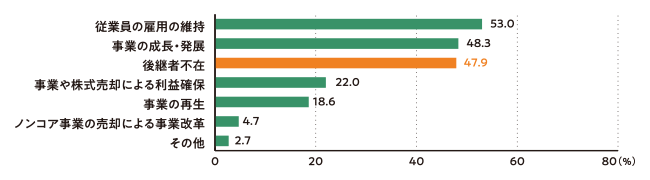
資料:東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
出所:中小企業庁「中小企業白書(2021年版)」
一方、買い手企業は高い技術や独自の販路などを持つ後継者難の企業を買収し、そのトップに自社の後継者候補を送り込んで(出向させて)育成することも可能である。売り手企業は事業存続と雇用の維持を、買い手企業は事業拡大と後継者人材の育成を図ることができる。
いずれにせよ持ち株会社制の導入は、事業ポートフォリオの再構築やグループ子会社の再編だけでなく、経営の持続的発展につながる有力なマネジメント手法の1つといえそうだ。




