生産年齢人口の減少と日本のグローバル競争力
既知の通り、少子高齢化の進行によって日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少し(【図表1】)、総人口も2008年をピークに減少に転じている。総務省「国勢調査(2015年)」によると日本の総人口は1億2709万人、生産年齢人口は7629万人である。
また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(2017年)によれば、総人口(出生・死亡中位)は2030年に1億1913万人、2053年で1億人を割り、2060年には9284万人にまで減少すると見込まれている。生産年齢人口については2030年には6875万人、2060年には4793万人まで減少するとされている。
次に、主要国におけるGDP(国内総生産)を見てみたい。これは、いわゆる国内で生み出された付加価値の総額であるが、人口減少がほぼ確定した日本の未来においては、この付加価値を上げていかなければ危ういと言える。(【図表2】)
【図表1】日本の生産年齢人口の推移
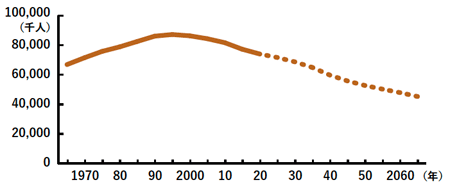
出典:2015年まで、総務省「国勢調査」、「人口推計(各年10月1日現在)」、2016年以降、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年4月)」(出生中位・死亡中位推計)
【図表2】主要国GDP推移
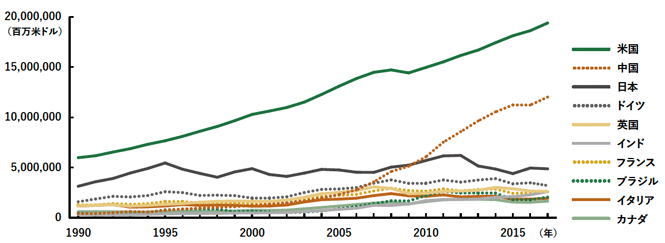
出典:IMF(タナベ経営により加工)
世界で広がる「考える教育」
本稿で注目したいのが「国際バカロレア」(InternationalBaccalaureate、以降IB)教育である。IBとは、1968年にスイスのジュネーブで設立された国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムだ。チャレンジに満ちた総合的な内容が特徴である。現在、認定校に対する共通カリキュラムの作成や、世界共通の国際バカロレア試験、国際バカロレア資格の授与などを実施。国際的に通用する大学入学資格(国際バカロレア資格)を与え、大学進学へのルートを確保しているというものである。
国外ではすさまじいスピードでIB認定校数が広がっており、2009年10月には2956校であったのが、2017年3月には6052校と増加率は204.7%になっている。だが、日本ではまだまだ知名度が低いのが現状である。
IB教育の細かな内容については本稿では割愛するが、簡単に言うと、「急速に進むグローバル社会を生き抜く上で、学び、そして働き続けるために必要な知性、人格、情緒、そして社会的なスキルを身に付けるための教育」である。これまでの日本が行ってきた知識詰め込み型の教育でなく、答えのない問いに対して自分で考えて答えを導き出す(付加価値を生む)ことが重視されているのだ。
私自身もIB校を視察したことがある。その内容は極めて素晴らしいものであった。例えば、子どもの人権について調査するためにアンケート項目を考える小学3年生、英語で行われるさまざまなカリキュラム、ダイバーシティーを認めるためのプログラム、「なぜか」を常に考える環境がそこにはあった。
昨今では、プログラミング教育や小学校英語教育の開始、大学入試センター試験廃止などの環境変化が激しい。私たちの仕事の約49%がAI・IoTに置き換わる時代が来るといわれており、今後、考える力(付加価値を生み出す)がよりいっそう求められる。
考える力を養うには
自社の人材(もしくは自分の子ども)をどのように育てていくのか?アプローチの方法はさまざまであるが、私は会社の中に“大学”をつくることを提案している。
社内大学がなぜ有効なのか。例えば、ある日突然、複数の事象が同時に発生したとする。自社の幹部・部下はその対策順・理由・手段を正しく判断することはできるだろうか?
仕事は生き物であり、昨日の正解は必ずしも今日の正解ではない。その時に状況を総合的に判断し、最適な判断をしなければならない。従って、マニュアルを作り、「教育のための教育」をしていては効果が薄いと言える。それらはいずれ、AIやIoTに置き換わってしまうからだ。
故に、私は、会社の経営理念・ミッション・ビジョンを踏まえた教育の設計を展開している。これを「大学」と呼んでいるのは、教育制度として体系的に組み立てて、さらに社外・社内にも分かりやすくするためである。社内大学として対外的にも存在をアピールすることで、「この会社で働きたい」と思ってくれる人を増やす「採用ブランディング」を行い、取引先からは「そこまで教育をしっかりしている会社なら、ぜひ仕事を任せたい」と信用を勝ち取る「営業ブランディング」を行うといった具合である。
さらに、環境変化が激しく、人材の早期育成が成果の鍵を握る現在の環境下で、この社内大学の効果は大きいと考える。
社員教育は、強制的な教育としてではなく、あくまでプラットフォームとして捉えてほしい。実際、全ての社員が真面目に受講することはあまりないかもしれないが、その比率の向上と内容の濃さを追求することが、今後ますます重要になってくる。
また、近い未来には、先述の「考える教育」を受けた若手人材が会社に入ってくるという事実に対しても、会社としてその人材を育て続けるプラットフォームを用意しなければならないのである。



