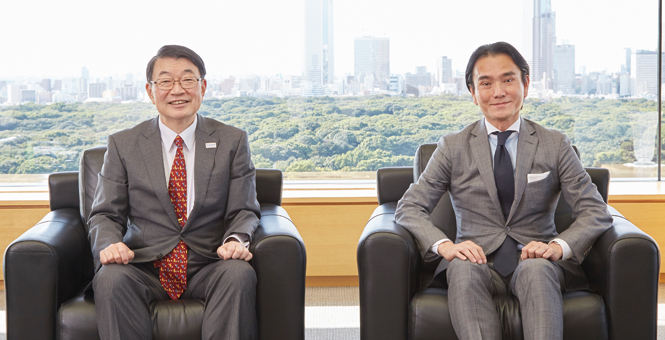日本初の警備会社としてセキュリティー業界を牽引してきたセコム。「社会システム産業」としてメディカルや保険、情報通信、地理情報サービスなどの事業ドメインを展開している。創業55年で、連結売上高9280億円、従業員数5万8000人にまで成長した同社は、社会がスピードを上げて変化する今日、安全を進化させることで変わらない安心を提供し続ける。セコムが描くビジョンについて、代表取締役社長の中山泰男氏に伺った。
日本初の警備会社でイノベーションを起こした
若松 セコムは1962年に日本初となる警備会社を創業されました。拙著『100年経営』では、トヨタ自動車の「カンバン」とヤマト運輸の「宅急便」、そしてセコムの「ホームセキュリティ」を日本の三大ビジネスモデルとして挙げています。世界に誇る日本発のビジネスモデルは、どのように生まれたのでしょうか。
中山 創業者の飯田亮(現取締役最高顧問)は、学生時代の友人だった戸田壽一(元取締役最高顧問、故人)と起業の夢を語り合う仲でした。欧州に警備を業務とする会社があることを知り、かねてより「社会から評価される事業」「誰もやったことのない事業」「前金が取れる事業」などを起業の条件と考えていた2人は、すぐに日本初の警備会社を興しました。しかし、当時の日本は「水と空気、安全はタダ」という時代でしたから苦戦したようです。そうした中、1963年に東京オリンピック組織委員会から警備の依頼が舞い込みました。内容は、工事の段階から大会終了までを通した選手村の警備。大きなチャンスでしたが、大会終了後も雇用した大勢の社員を養う仕事量が確保できるのか――。難しい経営判断を迫られましたが、セコムの基本理念は「社会に有益な事業を行う」こと。オリンピックは国を挙げた事業であり、その安全を担うことは社会にとって大事な仕事であるとの判断から引き受ける決断をしました。私が強く感じるのは、飯田が根っからの事業家であること。これが新しいビジネスモデルを成長させた大きな要因といえるでしょう。
若松 オリンピックの開催自体が日本で初めての大イベントであり、大きな挑戦でしたからご苦労も多かっただろうと想像できます。
中山 骨の折れることも多かったと聞いていますが、見事にやり抜いたことで組織委員会から表彰を受けるなど、高く評価されました。その結果、世間に警備の仕事や「セコム(当時は日本警備保障)」という社名が知れ渡るようになり、事業が大きく拡大。テレビ局の目に留まってセコムをモデルとした『ザ・ガードマン』というドラマが誕生し、人気を博しました。これによって、一段と契約数が伸びていきましたが、飯田のすごいところはイノベーション精神です。それまでの人による巡回警備、常駐警備から一部を機械化する警備へと大きく経営のかじを切りました。
若松 事業が順調に成長している中、普通なら現在の延長線上で事業拡大を図るところです。「機械警備」という新たなビジネスモデルに挑まれた理由は、どこにあったのでしょうか。
中山 24時間体制で常駐警備を行うには、交代要員も含め少なくとも1カ所につき5人の警備員が必要です。契約が順調に伸びていく中、将来的に警備員の人員確保が難しいことは明らかでした。もう1つ、飯田は人を大切にしていましたから、社員の負担を減らそうと機械で危険のシグナルを察知する仕組みを考えました。そうして生まれたのが、人と機械の融合を図る「SPアラーム」。機械がモニターして異常を察知し、警備員が駆け付ける現在の「オンライン・セキュリティシステム」ビジネスモデルの原型です。
若松 ビジネスモデルを発明した創業者だからこそ、自由な発想で事業を成長させ、逆にその限界を見極めて新たな領域への転換ができたのでしょうね。
中山 楽観主義とビジネスの絵を描く能力、この両方を飯田は兼ね備えていました。SPアラームはIoTの先駆けといえるでしょう。しかし、サービスを開始した1966年当時はあまり受け入れられませんでした。一方、従来の人による警備の需要はうなぎ上り。そうした中、1970年の幹部会議で飯田は「SPアラーム1本で行く」ことを提案。もちろん幹部全員が反対したそうですが、将来を見据えた飯田の決意は固く、このあえて難路を選ぶ決断が、現在は当たり前になった機械警備の普及へとつながっていきました。
若松 経営者として最大の決断ですね。私はコンサルティングで「取締役会で全員が賛成する事業はやめた方がよい」とよく申し上げます(笑)。まさにその決断ですね。事業の絵を描いた本人だからこそ、事業の先を見ておられたのでしょう。
中山 もう1つ、飯田が優れていたのは情報に対する認識の高さです。機械警備においても普通なら既存の通信回線を使うでしょうが、独自の通信網を構築したところに先見性を感じます。情報が重要な社会インフラになることが分かっていた。1982年には警備にとどまることなく、健康・医療や情報通信分野を視野に入れて「安全産業」元年を宣言。さらに、7年後の1989年には「社会システム産業」元年を宣言し、「あらゆる不安のない社会を実現する」というミッションを掲げました。持てる資源を使って社会や暮らしに役立つ、「安全・安心・快適・便利」な社会を実現する産業を創る。この考えは今日においても、事業のベースとなっています。

飯田亮氏、戸田壽一氏が日本初の警備会社として、日本警備保障(現セコム)を東京・芝公園で創業(1962年)。巡回警備、常駐警備を開始した。写真(上)は創業当時のもの(後列左から戸田氏、飯田氏)
「警備会社」という存在が広く知られていなかった1964 年当時、東京オリンピックの選手村の警備を請け負った。無事、無事故で会期を終えたことで、組織委員会から感謝状が贈られた。この東京オリンピックを経て、社会から高い評価と信頼を得て、仲間の士気も一気に高まった(下)
警備会社から「社会システム産業」へ
若松 社会システム産業を標榜するセコムの事業領域は、セキュリティーを中心に防災、メディカル、保険、地理情報サービス、情報通信、不動産事業へと7つのドメインを展開されています。
中山 目的はあらゆる不安のない社会の実現。そのために必然的に事業を積み上げたというのが正しい解釈です。常に企業ドメインが先にあり、社会課題を解決するために必要なものとして、結果的に事業ドメインが増えていったわけです。
若松 企業ドメインは、あらゆる不安のない社会の実現であり、「安全・安心・快適・便利」を実現するサービス価値の提供がもたらす結果なのですね。それを具現化するのがセキュリティーや防災、地理情報サービスなどの7つのドメインというポジション。企業ドメインがぶれていないから「安全・安心」というブランドイメージが定着しています。セコムとしてのブランド戦略についてはどのようにお考えですか?
中山 今は情報発信が大事な時代です。企業のブランド力は現場の一人一人が築くものですが、会社としてイメージを発信することでブランド力は強くなっていくと私は考えています。しかし、セコムは実直な会社で、良い活動をしているのに実践が大事という考え方で、あまり情報は発信してこなかった。「安全・安心」を事業とするセコムにとってブランド力は大事ですから、お客さまの信頼を高めるためにも発信力をさらに高めているところです。
若松 私たちは「ブランドとはお客さまとの約束」と定義しています。特に昨今は、企業の姿勢を発信することがブランド力を高める上で重要なポイントになっています。
中山 実は、以前からセコムは環境に対して先進的な企業でした。「安全・安心・快適・便利」な社会の実現をなりわいとする当社にとって、地球環境の保全は重要な課題の1つであり、2012年から社会・環境推進部という専門部署をつくってさまざまな活動に取り組んできました。2016年には、著名な国際的環境NGOである「CDP」が実施した気候変動への対応に関する調査において、最高評価の「Aリスト」企業に認定されました。その年にAリストと認められたのは国内で(当社を含め)22社だけです。
若松 メーカーと比べてCO2の排出目標などを達成することは難しい面がありますから、サービス業での認定は大きな意味があります。外部から評価されることで、セコムの姿勢が多くの人に伝わるきっかけになりました。
中山 ブランド価値は会社がつくるもの。その1つの成果です。「社会課題の解決」という発想は以前からありましたが、それを積極的に発信していくことが大事な時代です。社会と共に課題を解決して利益を出して再投資していく。そうしたサイクルの中で社会と共に成長していくというモデルをはっきり打ち出していこうと考えています。